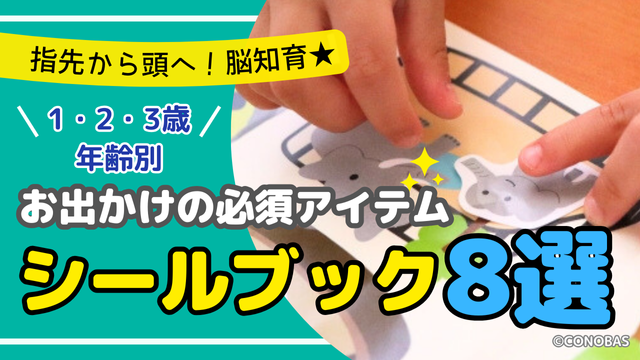
1・2・3歳おすすめシールブック!選び方&遊びの工夫も紹介
この記事を書いた人
まさと
- 幼稚園教諭
- 保育士
保育士歴15年。
現在はパート保育士とベビーシッターをしています。
5歳の双子の娘と2歳の娘、3人の子どもがいます。
木育遊びが好きで、木のおもちゃを集めては、子ども達と一緒に遊んでいます!
お出かけ先で、子どもの落ち着きがない。ゆっくりご飯も食べられない…という悩みは、子育てあるあるですね。
「少しでも落ち着いてもらうために、何か良い方法はないかな?」と思ったときは、シールブックを活用してみるのはいかがでしょうか?
シール貼りは、子どもが楽しみながら集中できる遊びです。
この記事では、シール遊びのメリットやシールブックの選び方と活用方法、年齢別おすすめのシールブックを紹介します。
3歳前後までは子どもにつきっきりになることが多く、愛おしくもありながらも子育てが大変だなぁと思うことも多いかもしれません。
上手にシールブックを活用して、少しでも余裕を持って「にこにこ・のびのび」子育て時間が過ごせるといいですね。
目次
1.シール遊び(シールブック)の知育効果とは?

シール貼りは指先の発達を促すことができる遊びです。
シールを貼るときに指先の動きに注目すると、「つまむ」「引っ張る」「ひっかく」「こする」「押す」といった細かな動作を行っています。
今後ハサミやお箸を使うときに、思うように動かせないというストレスが減り、スムーズに道具を使うための下準備を整えることができます。
また、「これは電車だね。こっちはショベルカーだ」など、シールを使ってモノと言葉をつなぐコミュニケーションをとることもできます。
<シール遊びの主な知育効果>
- 指先の発達
- 集中力が身につく
- 想像力が豊かになる
- 興味の幅が広がる
- ゴミ捨て習慣が身につくきっかけになる
- 親子のコミュニケーションで言葉の発育に繋がる
2.指先の発達とシール(シールブック)を選ぶときのポイント

子どもの指先の発達は「身体の成長」と「動かす経験」に基づいて、徐々に進んでいきます。
1歳前後になると、親指と人差し指を使って物を「つまむ」ことができるようになりますが、小さなものをつかむのはまだ難しいです。
2歳頃になると、大きめのボタンをかけたり外したりできるようになり、手先の器用さが向上します。そして3歳頃には、小さなビー玉やブロックをつまんで容器に入れたり、ハサミを使うことができるようになります。
このような指先の発達を考慮すると、シールを選ぶ際には「剥がしやすい」ものや適切な「大きさ」のものを選ぶことが重要です。
また、シールを貼る台紙である「シールブック」の大きさや管理方法にも注意を払うことが大切です。
次に、シールやシールブックを選ぶ際の具体的なポイントを見ていきましょう。
2-1.シール選びのポイント①「剥がしやすさ」でやる気を継続させる
シールが剥がしにくいと、シールがちぎれたり破れたりする原因になります。
シールを台紙から剥がすというところでつまずきを感じると、「うまくできない」→「やらない」につながってしまいがちです。
親としては、「剥がしにくいシールでも、きれいに剥がせるようになるための練習になる」と考えがちですが、乳幼児期には子どもの発達や特性に応じた「できた」という達成感を育むことがより重要です。
また、本来楽しいはずの「遊び」を教育的な視点で行うと、子どもは遊びの楽しさを感じられなくなることがあります。
1歳児前後には、ぷっくらした立体感のある剥がしやすいシールや、シールが離れて並んでいる台紙がおすすめです。
どうしても剥がしにくいシールを選んでしまった場合は、シールの台紙に折り目を入れてあげることでシールを剥がしやすくなり、自分で剥がせたよろこびを感じることができます。
2-2.シール選びのポイント②適切な「大きさ」で達成感を育む
子どもの発達や年齢によってシールの大きさを変えてみましょう。
1歳前後の子どもには、剥がしやすくて「貼った!」というインパクトのある「大きめのシール」を選ぶと、シール貼りの楽しさを強く感じることができます。
3歳頃になると、「絵柄が多く、小さなシール」に挑戦することで、より表現豊かなシール遊びが楽しめるようになるでしょう。この時期の活動は、将来的な箸のトレーニングにもつながる指先の練習にも適しています。
年齢はあくまで目安ですが、重要なのは子どもがストレスなく遊び続けられるサイズであることです。
もし子どもが「小さなシールで遊びたい!」という意欲を見せたら、まだ早いかもしれないと思っても、挑戦させてみましょう。その際には、大人がシールを剥がして手渡すなど、サポートしてあげてください。
また、1〜2歳頃はシールを誤飲する可能性があるため、注意して見守ることが大切です。
2-3.「シールブック」は面が大きく頑丈なものがおすすめ
シールブックは、シールを貼る面が大きいものがおすすめです。
貼れるスペースが狭いと、シールが重なって取れなくなったり、思うように貼れずに癇癪を起こしてしまうことがあります。
また、お出かけ先で使う際には、まだ貼っていないシールがカバンの中で散らばったり、シールブックが折れ曲がってシールが飛び出してしまうことを避けたいものです。
そのため、ある程度厚みのある頑丈な台紙のものを選ぶと良いでしょう。薄いシールブックの場合は、ファイルなどに挟んで持ち歩くのもおすすめです。
3.1歳児におすすめのシールブック3選

ここからは、1歳児におすすめのシールブックをご紹介します。子どもの好みに合わせてあげると集中して遊んでくれますよ。
アンパンマン ぷっくりシール
アンパンマン ぷっくりシールは立体的でお子様1人でも剥がしやすいのが特徴です。
シールも32枚入っていて、5つの場面を楽しむことができます。パパママと一緒に遊ぶことで、ごっこ遊びにも繋がりそうです!
いないいないばあっ! はじめてのシール絵本
「いないいないばあっ」でおなじみのワンワンと仲間たちのシールブックです。
シールには爪があり、剥がしやすく、何度も遊べるようになっています。シールの大きさもちょうどよく、1歳の子どもでも貼って遊べますよ。
注意点として、何度も貼って剥がすを繰り返すと、粘着力が弱くなります。また、強度は普通のシールと変わりません。破れることもあるため、誤飲には気をつけてくださいね。
新版あかまる ぺたっ!
特徴はマグネットシールです。シールも大きく何度も貼れて遊ぶことができます。
知育にも適していて、それぞれのページにお題があり「同じ形を重ねよう」「同じ形を並べよう」など何度でもチャレンジすることが可能です。
子どもも「できた!」という達成感を味わえる1冊となっています。
4.2・3歳児におすすめのシールブック5選

次は2・3歳児におすすめするシールブックを5つ紹介します。
2〜3歳頃になると、手首の動かし方が上達し始める時期です。スプーンを下手持ちするようになったり、お絵かきで連続の円を描けるようになったりし始めます。
この時期のシール貼りは、子どもの興味を広げると同時に、発達に合わせたシールブックを購入すると良いでしょう。
【2歳向け】はっけん!シールブック
キャンドゥやセリアなどの100円ショップに売ってある商品です。おうちやお散歩でよく目にするモノを見つけて、シールを貼るという親子で一緒に楽しめる工夫がされています。
「貼って剥がす」はできませんが、ちょうど良い大きさのシールで、頑張ったら剥がせるくらいの大きさです。
「シール探検」で、言葉や興味の広がりを発見してみてください。
【2歳向け】ゆっくとすっくのごほうびシール
こちらはご褒美シールブックです。トイレトレーニングやパンツトレーニング、歯磨きなどの習慣を身につけることができます。
「できたね」「あと少しだったね」など、結果だけでなくトイレに行こうとしたときなどの過程を認め、シールを貼ることで習慣が身につきやすくなりますよ。
【2歳後半向け】2歳シールであそぼう
「どうぶつ・おみせやさん・ひらがな・ちえ」と「たべもの・のりもの・ひらがな・ちえ」の2種類があります。子どもの興味に合わせて選んであげると良いでしょう。
シールの大きさは様々で、今の子どものレベルに合わせて楽しくシールを貼ることができます。
様々なページがありますが、自由にシールを貼らせることがポイントです。「自我」が生まれてくる時期のため、自分で思った通りに貼ることで「こうしてみよう」とチャレンジ精神が芽生えやすくなりますよ。
【3歳向け】小学館の図鑑NEO まるごとシールブック
子どもが特定のモノに興味を持っている場合におすすめなのが、まるごとシールブックです。
小学館の図鑑NEOシリーズがそのままシールブックになりました。シールブックを見ているだけでも図鑑として活用できます。
また、ひとつひとつのシールが珍しいものばかりなので、お気に入りのシールをノートやカバンに貼ることで、宝物になりますね。
注意点としては、シール図鑑となるため、シールを剥がしてもシールブックに貼る場所はありません。一度剥がすと図鑑としては機能しませんが、シールを剥がした跡をシルエットクイズ遊びとして活用することも可能ですよ。
【3歳向け】モンテッソーリ はじめてのシールブック
モンテッソーリ教育総合研究所が監修したシールブックです。対象年齢は3歳〜とありますが、やや難しめに感じると思います。
大人が一緒に見守ることが前提のシールブックのため、子どもが困っているときは「こうしてみるといいかも」などヒントを出してあげると親子で一緒に達成感を味わえるでしょう。
このシールブックの特徴として、図形がメインなところです。形に合わせて貼っていくことができれば、論理的な思考力や構成力、空間認知能力など知育に適した内容となっています。
5.シール・シールブックの活用方法

ここでは、シール遊びやシールブックの活用法について紹介します。
シール遊びは指先の発達や知育効果だけでなく、外出しているときや、子どものやる気アップなど、子育てのさまざまな場面に活かせることも多いです。
ぜひ、参考にしてみてくださいね。
5-1.お出かけ時に活用
シールブックの便利な使い方としては、外出先で騒ぐと迷惑がかかるときにシールブックを与えることです。
シールブックは指先を使うため、集中して遊んでくれます。そのため、公共の交通機関などで大いに力を発揮してくれます。
また、子どもにとって興味のあるシールブックにすることで、より集中して遊んでくれるでしょう。
大人が関わるのも効果的です。例えば、お買い物のシールブックでは「お母さんが好きな果物ってなーんだ」などクイズ遊びにするなど発展させることで、長時間の移動でも遊ぶことができますよ。
普段からスマホゲームやYouTubeに偏ってしまうと悩んでいる方はぜひ試してみてください。
5-2.習慣・ルールを覚えるために活用
「頑張ったら、シールを貼る」「できたらシールを貼る」というように、ご褒美にシールを使用すると、子どもの主体性を高めながら生活習慣が身につきます。
しかし、「先にシールを貼りたい!」「貼ってからやる!」とぐずってしまうこともあります。そんなときは、先にシールを貼らせてあげましょう!
「できたら貼る」のご褒美シールの役割は、「主体的に行動する」という生活習慣を育むことです。「今日はできなかったからシールを貼りません」と、厳しく制限してしまうと主体的にやろうとする意欲がそがれてしまうこともあります。
先にシールを貼ることになった場合は、あらかじめ「シールを貼ったら一緒にやろうね」と声をかけて、習慣づけると意外とうまくいきますよ。
5-3.なりきり遊びへ活用│遊びの幅がUP!
シールはノートや本に貼るものと思っているかもしれませんが、子どものおでこや手のひらに貼って、動物や乗り物になりきる遊びもおすすめです。
例えば、体の一部にうさぎのシールを貼って「みてみて!うさぎさんになったよ」と伝えるだけでも、ぴょんぴょん飛び跳ねて遊び始めることができます。
雨の日に外で遊べないときや、おもちゃ遊びに飽きてしまい新しい刺激が欲しいときなどに、とても使えますよ。
子どもは、好きなものに何にでも変身できます。可愛らしい仕草を見せてくれるため、想像力や表現力などの非認知能力への向上にも有効です。
非認知能力とは、想像力・粘り強さ・コミュニケーション能力・表現力・計画性など数値などでは測定できない能力のこと。
国が定めた幼児期の終わりまでに育って欲しい10の姿の1つにも、「豊かな表現力と感性」の項目があり、表現力や想像力は幼児の育ちにとても重要な役割を果たしていると考えられています。
6.シール遊びのバリエーションを楽しもう

シール貼りはシールブックだけでなく、100円ショップで購入できますね。ここでは丸シールとマスキングテープを使ったシール貼り遊びを紹介します。
6-1.「丸シール」でアートを描いて遊ぶ
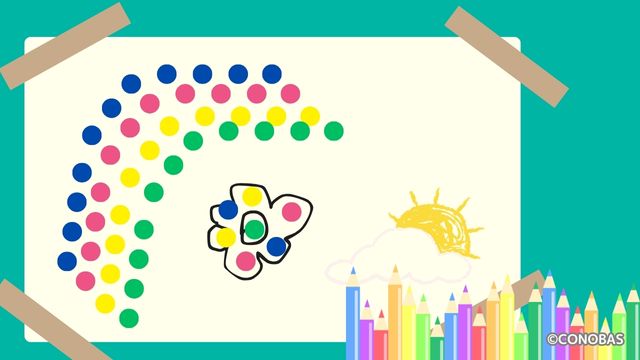
まずは、丸シールよりも少し大きめの丸印を大人が描いておくことで、印に合わせるようにシール貼りをする遊びの紹介です。
単純に貼るだけだと飽きてしまう可能性もあるため、カラフルな丸シールを用意しておくなどをすると「虹みたいになったね」と楽しんでくれます。
今は印刷でも丸シール遊びの台紙は用意できるため、いろいろな遊びができますよ。
次に、丸シールで生き物を作る遊びです。
丸シールを半分に切って魚のウロコに見立てたり、小さな丸シールは目に、大きな丸シールはほっぺたにしたりなど、自分の顔を作る遊びも面白いですよ。
最後にお絵かきをして、可愛く仕上げると楽しみも増えますね。
6-2.貼る遊びの応用編「マスキングテープ」遊び
マスキングテープはカラフルで剥がした跡も傷がつきにくいため、様々な場所に貼ることができます。
私がベビーシッターに行っている家庭では、マスキングテープを部屋の家具に貼って宝探しをしました。椅子の下やソファーの後ろにくっつけて探し回ることで、子どもたちも楽しんでくれますよ。
また、体に貼っておしゃれをする遊びは女の子に評判が良いです。ブレスレットやマニキュアのようにつけてあげるとお姫様に変身できてご機嫌に踊ってくれます。
7.シール(シールブック)を活用して楽しくできるを増やそう!

シールブックで遊ぶことは指先の発達や知育にも役立ち、さらには興味や表現の幅が広がる楽しい遊びと言えます。
使い方や工夫次第では、子どもの現状に合う遊びができるので、ぜひシールブックやシール貼りを試してみてください。
利用者No.1「トイサブ!」積み木、ごっこ遊び、音が出るおもちゃ、パズル…多様な玩具が選べる[PR]
おもちゃを買うのも選ぶのも、子どもがいるご家庭ならではの楽しみですね。
一方で、どんなおもちゃがいいか分からないといったお悩みや、高くて何個も買ってあげられないといった声も聞きます。
色々なおもちゃで遊ばせてあげられればいいな…と思ったら、トイサブ!を活用してみてはいかがでしょう?
トイサブ!は、国内・海外メーカー約250社から選定した1800種類以上の玩具の中から、一人ひとりに合った知育玩具をお届けするレンタルサービスです。
★トイサブ!の魅力
- 2か月ごとに、定価合計17,000円以上の知育玩具を5~6点お届け
- おもちゃ評価データ100万件以上を活用し、個別プランを作成
- 気に入った玩具は、レンタル継続やお得な価格での買取も可能
- 遊び方や子どもが興味を持たない場合など、メール・チャットで相談できる
- 破損しても原則弁償不要で、安心して自由に遊ばせられる
- 返却期限なし、延滞料金なしなど、子育て世帯の声をもとに柔軟な仕組みを採用
「買ったおもちゃもすぐに飽きてしまう」
「おもちゃが部屋に溢れている…」
「買うと高価な知育玩具を購入前に試してみたい」
そんな親御さんにもおすすめです◎
▶▶詳しくはトイサブ!の公式サイトをチェックしてみてください!
関連トピックをご紹介!
・「電車でじっとしていられない」原因と対策、現役ママの暇つぶしアイデアを紹介
・待ち時間に子どもと楽しめる遊びやおもちゃを紹介【スマホ以外の暇つぶし】
・3歳おすすめ!買ってよかった知育おもちゃ8選│話す・聞くの発達を伸ばす遊び






