
幼児期からできる時計の勉強!自然に時計が読めるようになる教え方
この記事を書いた人
yurinako
- 司書教諭
- 幼稚園教諭
- 小学校教諭
- 子育て支援員
小2と年長の娘のママ。
小学校教員として15年間勤め、小学1年生から6年生までの担任を経験し、
のべ1500人以上の子どもたちを指導してきました。
小学校教諭、幼稚園教諭、司書教諭、子育て支援員の資格を持っています。
親子で一緒に、本やダンス・料理を楽しんでいます!
「時計が読めないと、小学校に入ってから困るのではないかしら」
「何回も教えているのに、なかなか時計が読めるようにならなくて困っている」
など、「幼児が時計を読めるようになるにはどうしたらいいのだろう?」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。
今回は、幼児期のお子さんが時計を読めるようになるためのステップを順番に解説していきます。さらに、時計学習に役立つアイテムもご紹介します。
皆様のお悩み解消に少しでもお役に立てれば幸いです。
目次
1.時計は何歳までに読めればいいの?

大人は1日の時間を区切って、時計を見て管理しています。
朝起きてから寝るまで、時計を見ずに行動する方はいないでしょう。
何時に何をして、何時までにはこれを終わらせたいなど常に時計を意識しているのではないでしょうか。
しかし、お子さんはどうでしょう?乳幼児の間は、大人が管理する時間に従って動いてはいますが、自分で時計を見て時間管理をしているわけではありませんね。
では、時計は何歳までに読めればいいのでしょうか?あるいは、時計が読めないと困るのは何歳くらいでしょうか?
まずは、時計学習が必要な年齢の目安から見ていきましょう。
1-1.時計学習の年齢の目安
小学校での「時計学習」に照らし合わせると、「小学2年生(~8歳前後)が終わるころまで」に時計が読めるようになるのが理想です。
小学1年生から3年生の算数の授業で、「とけい」「時こくと時間」に関する学習があります。
これらの学習の目安として、小学2年生の終わりまでには時計の読み方を確実に理解し、使いこなせるように指導しています。
そのため、幼児で時計が読めないからといって焦る必要はありません。
[各学年での学習内容]
【小学1年生 後半】
・時計の読み方を知る(何時、何時半、何時何分)、時計のイラストに針を書き込む
【小学2年生 前半】
・時刻と時間の違い(*)、午前・正午・午後、1日は24時間であること
【小学3年生 前半】
・「秒」~「日」までの時間単位、24時間表記で時刻を表す
(*)時刻と時間の違い
時刻…そのときが「何時何分」であるかを示す
時間…ある時刻からある時刻まで、どれくらい経過したかを示す(「何時間」「何分間」と表す)
※自治体によって教科書が異なりますので、学習する時期については若干の差があります。
1-2.急がなくて大丈夫!本格的な「時計」学習は小学校からがベスト
「時計を正確に読むこと」は小学校低学年(7歳前後)からで大丈夫です。
小学校に入学してすぐに求められるのは、まず「時計を読むこと」よりも「時間割に合わせて過ごすこと」です。
小学校生活の中で1時間目、2時間目といった時間感覚がしっかり身についてきます。
その後、算数の授業で「時刻と時間」を学習し、小学3年生(9歳前後)以降では、自分で時間を意識して行動することが求められます。
例えば、授業開始5分前には体育館に集合する、12時には給食を開始するなど、時計を見ながら行動できるようになっていきます。
小学校入学前の幼児期には、まず、朝起きて夜寝るまでの時間の流れを体感し、この流れが時間なんだな、となんとなく理解できていることが大切です。この単純なイメージ理解がその後の「時計学習」につながります。
2.幼児期から始めたい!時計学習の土台作り

幼児期に時計の読み方を教えても、なかなか読めるようにならないというお悩みをお持ちの方も多いかと思います。
就学前の幼児期になかなか時計が読めないのは、時計を学ぶための土台がまだできていないからです。
時計学習を始める前に、まずは時計を学ぶための土台作りから始めましょう。
一般的に「時計を読む」とは、アナログ時計を見て何時何分かがわかることを指します。
そのため、「数字が読めれば、時計も読めるようになる」と考えがちですが、それだけでは「時計を読める」ようにはならないのです。
時計を読めるようになるには、まず時計学習のための土台作りが必要です。
そして時計学習のための土台作りには、大きく分けて「時間感覚をつかむ」「時計が動くイメージをつかむ」「数字の読み方を身につける」の3つが必要です。
この3つの点について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1.時間感覚をつかむ
幼児期には、日常生活の中で時間の流れや、時間の感覚をつかむ経験が大切です。
乳幼児期は、朝起きたとたんに全開モードで1日を走り抜け、夜になると電池が切れたようにパタッと寝てしまうことがよくありますよね。
このような中では、時間の流れを意識することはほとんどありません。
それが、保育園・幼稚園へ行くようになると、朝起きる時間、保育園・幼稚園に行く時間、お昼ご飯を食べる時間、夕方お家に帰る時間、夜寝る時間といった1日の区切りと時間の流れを少しずつ感じるようになってきます。
生活習慣が整っていく中で、お子さんは時間の流れを体感していくのです。
時計学習の土台作りのためには、まず、意識的に「時刻の声掛け」をしましょう。
例えば、「6時だよ。起きようね。」「12時になったからお昼ご飯にしましょう。」「夜の8時だね。もう寝る時間だよ。」など、時刻の声掛けとともに生活リズムを整えていきましょう。
毎日繰り返される生活リズムの中で、お子さんは「何時は何をする時間だ」と生活と時間を結び付けられます。
こうして1日の時間の流れの中で、時間の感覚をつかめるようになっていきます。
2-2.時計が動くイメージをつかむ
時計学習の土台作りのためには、時間の経過とともに時計の針が動いているイメージを身につけることも大切です。
まずは、ご家庭にシンプルなアナログ時計を置きましょう。
お子さんの生活の中に当たり前にあるものというイメージを持たせられると良いですね。
時計は、1から12までの数字が大きくわかりやすいもの、長針と短針の区別がつきやすいものを選んで、お子さんが見やすい位置に置きましょう。
朝起きて、ご飯を食べたり、保育園・幼稚園に行ったり、お風呂に入ったりといった生活の区切りで時計を見てパパ・ママが時計の動きを口に出す習慣をつけましょう。
「朝起きたときは7時だったのに、もう8時過ぎたね。幼稚園に行く準備をしようね。」「もうすぐ夜8時だからおもちゃをお片付けして、8時になったらお風呂に入ろうね。」など、時間の経過と時計を関連付けて言いましょう。
時計はまだ読めなくて大丈夫です。時計を見る習慣をつけ、時間が経過すると時計の針も動くのだなとイメージできるように意識的な声掛けをしていきましょう。
2-3.数字の読み方を身につける
時計を読めるようになるには、数字の読み方を身につけ、数字を読んで数字の順番を理解することも必要です。
5歳頃になると、10以上の数を声に出して唱えたり、10くらいまでの数字を読んだり、数字と物を対応させて認識できるようになってきます。
しかし、時計を読むためには、もう少し数に慣れる必要があります。
まずは、数字を1から12まで読めることと、時計の数字は右回りに1ずつ大きい数字が順番に並んでいることに慣れましょう。
時計を見ることが当たり前になってくると、お子さんは自然に時計の数字の並びにも慣れることができます。
生活の区切りや、行動前のタイミングで時計を見ることを習慣化させましょう。
数字の順番の理解につながる日常生活でできる数遊び
■数に触れる経験・遊び
階段を上るときには1段ずつ数えながら登ったり、ブロックや積み木を1つずつ数えながら積み上げたりしましょう。
慣れてきたら、ブドウやアメなど小さいもの、細かいものを一つずつ数える経験も積んでおきましょう。
小さな物と数を対応させながら順番を間違えずに数えられるようにしておくと、時計の1分のメモリを読む準備が整います。
■数字と順番を意識した数遊び・声掛け
絵本の中で並んでいる動物を指しながら、「1、2、3。くまさんは三番目に並んでいるね」「うさぎさんは何番目に並んでいる?」と声に出して数えるのも良いですね。
エレベーターの階数を示す数字を指しながら、「今日は5階の上の6階に行くよ。」と話すことも効果的です。
さらに、カレンダーの数字を指して「10日は遠足だね。前の日の9日におやつを買いに行こうね。遠足の次の日の11日は、幼稚園お休みだよ。」というように、日常生活の中で意識的に数字の順番に触れる声掛けをしてあげましょう。
このように数字の順番の理解を深めるために日常生活や遊びの中で数に触れる経験を意識的に増やすといいですね。
その時すぐに理解できなくても大丈夫です。
少しずつ数字を読んで数字の順番に触れる経験が増えていくうちに、お子さんは自然に理解が進んでいきます。
幼児期の数理解に関しては、以下の記事でも取り扱っていますのでぜひチェックしてみてください。
【5歳児】数の理解が進む!おうちでできる「数遊び」5選~楽しく学んで力を育もう~
【5歳児】数の理解が自然と身につく!数字でたのしくあそべる知育玩具5選
【3~6歳】子どもはいつから数や数字を理解するの?発達段階に沿ってわかりやすく解説!
3.時計が読めるようなる教え方~5つのステップ~
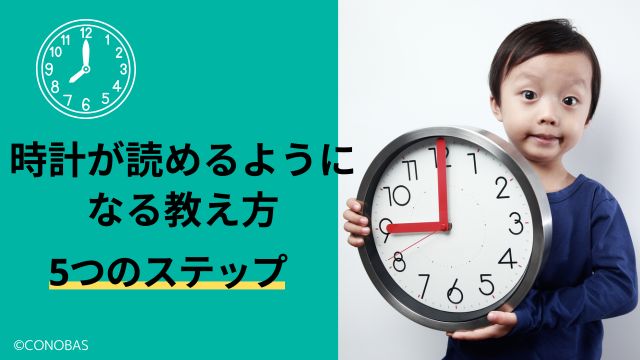
日常生活の中で時計を見る習慣ができ、時計学習の土台ができてくると、お子さんは時計の指す時刻に興味を示し始めます。
「いま何時?」と聞いてきたり、時計が読めなくても大人の真似をして「もう8時だね~」などと言ってきたりしたら、いよいよ時計の読み方を教えるチャンス到来です。
次の5つのステップを参考に、時計の読み方を教えてあげてください。
- 「正時(ちょうど)」を身につける
- 「半(30分)」を身につける
- 「正時の前」、「正時の後」を理解する
- 「1分」を身につける
- さらに時計に興味を持ったら
これら5つのステップについて、詳しく見ていきましょう。
3-1.ステップ1 「正時(ちょうど)」を身につける
まずは、1時ちょうど、2時ちょうど、3時ちょうどなど、正時の時間を教えてあげましょう。
時計の読み方を教えるには、自分で触って針を動かせる知育時計を用意すると便利です。
例えば、1時に時計の針を合わせて、「短い針が1の所にあるね。」「長い針は一番上の12のところにあるね。」「これは1時だよ。」と教えてあげましょう。
正時は、長針が常に12にあるので、短針を指して「短い針が1、だから1時」「短い針が2、だから2時」のように、最初は短い針の位置が「〇時」を示すことを強調して教えてあげましょう。
日常生活の中で、正時に行動する習慣があれば、お子さんに「朝起きるのは何時?」「おやつを食べるのは何時?」と聞いて、時計の針を合わせて見せてあげましょう。慣れてきたら、お子さんに自分でやらせてあげるといいですね。
[注意点]
「午前と午後」については、詳しく説明するとお子さんは混乱してしまう可能性があるので、「お昼の12時を過ぎると午後になるんだよ」だけで大丈夫です。
もしお子さんが「同じ時間が2回あるのはなぜ?」と疑問を持った場合は、「朝の6時と夕方の6時」「午前8時と午後8時」のように「朝、夕方、夜」あるいは「午前、午後」をつけて言ってあげましょう。
午前、午後の区別はあまり気にしなくて大丈夫です。まずは、正時(ちょうど)の時間を読めるようになることを重視しましょう。
[つまずきポイント]
長い針と短い針を間違えてしまうことがよくあります。短い針で「〇時」を読むことを、繰り返し教えてあげてください。
使用する時計は、長針と短針が色分けされているなど、区別しやすいものがいいですね。
3-2.ステップ2 「半(30分)」を身につける
「〇時半(30分)」の時間と読み方を教えてあげましょう。
「長い針が一番下、6のところに来たときは半って言うんだよ」「長い針がぐる~っと1周する時のちょうど半分の時間だから、半って言うんだよ」と説明しましょう。
例えば「1時半」「2時半」というように時計で示して、教えてあげましょう。
また、「半」の時の短い針の位置も必ず確認しておきましょう。
「1時半は、1時と2時のちょうど真ん中の時間だよ。だから短い針はちょうど1と2の真ん中にあるね」と短針の位置を示してあげましょう。
[注意点]
数字を読むのが得意で、デジタル時計や60分のメモリがついた時計で時計を読む場合は、「〇時30分」という言い方を教えてあげてもいいですね。
ただし、この場合でも、60分の半分が30分という理解は、後にとても大事になってきますので、「30分は60分の半分だから、〇時半とも言うんだよ」と教えてあげましょう。
[つまずきポイント]
お子さんは「1時30分」を「1時6分」と読んでしまうことがあります。
まずは、長い針が一番下にあるときは「〇時半」または「〇時30分」と言うんだよと、数字を読ませるのではなく、言い方を教えてあげる方が混乱しにくいです。
その後で、60分のメモリに数字がついている知育時計を使っている場合は、短針はどの数字を読み、長針はどの数字を読むかをしっかり教えてあげましょう。
3-3.ステップ3 「正時より前」「正時より後」を理解する
「正時より前」か「正時より後」かを区別できるように教えてあげましょう。
例えば、時計を2時50分に合わせて、「短い針は2を過ぎて、もうすぐ3だね」「長い針ももうすぐ12に来るよ」「この時計はもうすぐ3時。今は、3時より少し前だね」と教えてあげましょう。
長い針を動かしながら「チク、チク、チク、ポーン!今、ちょうど3時になったよ」と示してあげましょう。
さらに、長い針を動かして「長い針が12を過ぎたから、短い針も3を少し過ぎたね。次は4だね」「短い針が3と4の間にあるから、3時は過ぎていて、4時より前だよ」と教えてあげると良いですね。
正時の前後の動きを繰り返し見せてあげることで、お子さんは次第に「正時より前」「正時より後」の時間がわかるようになってきます。
[注意点]
長針の動きに従って短針が動く様子を繰り返し見せてあげることも大切です。
長針と短針が連動して動く時計を用意して、1時、2時、3時と順番に動く様子を見せてあげましょう。
ただし、「長い針が1周する間に、短い針は数字1つ分進む」というのは、幼児のお子さんには理解が難しく混乱してしまいますので、「長い針がぐる~っと回って1時、またぐる~っと回って2時」のような表現で示してあげると良いですね。
[つまずきポイント]
数字の順番の概念が十分身についていないと、お子さんは「3時より前」「3と4の間にあるから3時より後、4時より前」という考え方に混乱してしまいます。
慌てずに、数字の順番の数遊びをたくさん行ってから、「正時の前」「正時の後」を教えてあげましょう
3-4.ステップ4 「1分」を身につける
時計を読むのが楽しくなってきて、「いま何時何分?」などと、お子さんが詳細な時刻に興味を持つようになったら、「1分」ごとの時計の読み方も教えてあげましょう。
まずは、1から60まで数唱してみましょう。それが言えるようであれば、時計の分のメモリを示して「これはぐる~っと1周すると、60個のメモリがあって60分って言うんだよ」「1つのメモリは1分だよ」「1分、2分、3分と進んでいくんだね」と教えてあげましょう。
メモリを1つずつ数えて「1分、2分、3分」と読んでみましょう。また、1分の感覚も確かめてみましょう。
まずは秒針のついている時計かストップウォッチを見ながら1,2,3・・・と60まで一緒に数えてみましょう。
これが1分の長さだとわかってきたら、「1分あてっこゲーム」もしてみましょう。
目を閉じて、1分だと思ったところで「はい!」と手をあげます。時間を計測する人は、あとでそれが何秒だったか教えてあげたり、ちょうど1分の時間が来たら「はい、1分!」と教えてあげましょう。
2分や3分であてっこゲームをしてみても面白いですね。楽しみながら、短い時間感覚も身につけていきましょう。
[注意点]
数字を読むのが得意なお子さんは、デジタル時計で「分」の単位まで読めるかもしれません。
しかし、数字が読めたからといって「分」がわかっているとは限りませんので注意しましょう。
時間の「分」を教えるのは、アナログ時計の細かいメモリを60まで数えられるようになってからで大丈夫です。
[つまずきポイント]
「1分」を「いちふん」、「2分」を「にぷん」と読んでしまうことがあります。
助数詞の読み方や助数詞がついたときに数字の読み方を変えるのは、難しいことですね。
間違っていたらその都度「いっぷん」「にふん」と言うんだよ、と繰り返し教えてあげましょう。何度も聞くことで自然に身につくようになります。
3-5.ステップ5 さらに時計に興味をもったら
幼児の間は、時計は、正時(ちょうど)、半(30分)の時間が読めて、1分、2分と分のメモリを数えることができるようになれば十分です。
日常生活の中で、時計を見る習慣をつけることを大切にしましょう。
もし時計にとても興味を持って、もっと知りたいとか、どんどん覚えてしまう様子がみられたら、次のことも順番に教えてあげましょう。
まずは、5分ごとの時間が読めるように、5の倍数の数を唱えられるようにしましょう。
数表を見て練習すると、5倍の感覚も身につきます。「5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60」と唱えられるようになったら、アナログ時計の5分刻みを指し示しながら言えるようにしましょう。
1分ごとに読めるようになっていれば、それと頭の中でつながって、「5分、10分・・・」という5分刻みの時間がすぐに理解できるようになるでしょう。
その上で、60分は1時間と同じ長さということを教えてあげましょう。60分と1時間が同じ長さの時間なんだというところまでわかってきたら、時計の読み方はバッチリですね。
秒針のついた時計で、1秒、2秒・・・と秒針が1周して60秒経つと1分と同じなんだ、ということもすぐに理解できるようになっています。
4.楽しく時計が読めるようになるサポートアイテム

時計を読めるようになるためには、さまざまな角度から「時計」や「時間の感覚」に触れる経験をすることが大切です。
日常生活や遊びの中で、楽しく経験を増やすことで、お子さんは自然に慣れて理解も深まり、時計が読めるようになっていきます。
「時計」や「時間の感覚」を楽しく身につけられるサポートアイテムをいくつかご紹介します。
ぜひ、親子で楽しんでみてください
4-1.知育時計
お子さんが手に持って、針を動かせる知育時計を1つ用意しましょう。
時計の仕組みを理解するには、実際に自分で触ってみることが役に立ちます。
パパ・ママが時計の読み方を教えるときにも便利です。
知育時計は、幼児のお子さんにも理解しやすくなっています。
1から12の数字が大きくて見やすく、短針と長針が色分けされて区別しやすいものが多いからです。
さらに、外側の「分」を表すメモリには1分ごとの数字が1から60まで書かれているものをおすすめします。
幼児の間は2桁の数字に慣れていない場合も多いので、時計に刻まれている数字を繰り返し目にすることで、数字への認識力も高まります。
また、長針が動くのに連動して短針が動く知育時計だと、時計の仕組みもより理解しやすくなりますね。
4-2.絵本
絵本は、数に親しめる絵本、時間の流れに触れられる絵本、時計や時間を意識できる絵本が役立ちます。
絵本を読むと、登場人物に自分を重ねたり、お話の概要をとらえたりするようになるので、概念を理解する力や客観的なものの見方を身につけるのにも役立ちます。そうした成長が時計を読める力を養う土台にもつながるのです。
絵本は、絵やお話などにお子さんが興味を示すものを選びましょう。
興味を持って楽しく読んでいるうちに、自然に数や時間に親しみ、時計を読む土台が作られていきます。
4-3.ゲーム
数や時計に関するボードゲームやカルタは、楽しみながら数や時計に親しむことができます。
例えばすごろくのようなボードゲームは、マスを1つずつ数えたり、順序良く進むことが必要なので、数や順序に親しむのに良いゲームです。
また、ゲームはルールを理解した上でそれを運用する経験が積めるので、今後の時計学習にも役に立つ力が養われますね。
時計の絵がついたカルタのようなゲームでは、繰り返し遊んでいるうちに、時計がすばやく読めるようになります。
ゲームで遊びながら、楽しく時計学習の基礎を養っていきましょう。
4-4.プリント
就学前の5~6歳頃になると、プリントも楽しく取り組めます。
市販のプリント教材や、インターネットから無料でダウンロードできるプリントもたくさんありますので利用するといいですね。
時計がある程度読めるようになってきて、さらに定着させるために、プリントは効果的です。
自分で実際に時計の針を書いてみたり、時計の絵を見て数字で時間を書いてみたりすることで、しっかり理解できていることが確認できます。
数字や文字を書くことに興味がでてきたら、挑戦してみましょう。
5.親子で楽しく!日常生活のなかで自然に時計学習の基礎を身につけよう!

生活習慣の中で育まれる時間の感覚は、時計の勉強の第一歩でもあります。
小学校では「算数の勉強」として扱われる時計学習も、幼児期なら、日常生活や遊びの中で楽しく自然に学ぶことができます。
幼児期は、あわてず、時間感覚を身につけたり、数に慣れ親しんだり、時計を見る習慣をつけたりといった時計学習のための土台作りを意識しましょう。
生活の中で得られた時間の感覚と時計を結び付けるイメージは、お子さんの中にしっかりと根付き、深い理解へとつながります。
また、「時計で遊ぶのは楽しい!」という気持ちが、時計学習の意欲を高めてくれます。
時計が読めたり、「もう9時だから出発だよ」といった時間を意識した発言がでたら、たくさん褒めてあげましょう。
お子さんの意欲も高まって、時計を見て自主的に行動するお子さんに成長できますよ。
親子で楽しく時計学習の基礎力を養っていきましょう。
タブレット型の子供向け通信教育サービス「RISUきっず」[PR]
そろそろお子さんに「学習・勉強を始めようかな?」と考えたときに通信教育の利用を検討するママ・パパも多いのではないでしょうか?
RISUきっずは算数に特化した4歳~小学生向けのタブレット型の通信教育サービスです。
✓「無学年制」だから一人一人にあったペースで学べる!
✓学習データを分析して、教材のレベルが自動で変化
✓読み上げ機能付きだから、ひらがなに不安があるお子さんでも安心
1週間のお試しキャンペーンも実施中!
お問い合わせはこちらから>>RISUきっず
4歳・5歳の学びをピックアップ!
・【4歳・5歳から始める!】「お金の教育」の必要性と取り組み5選
・【5歳児】論理的思考力を育む!おすすめの知育パズル5選をご紹介!
・【4歳・5歳】元教師がひらがなの教え方を紹介!家庭でできる5つのアプローチとは?






