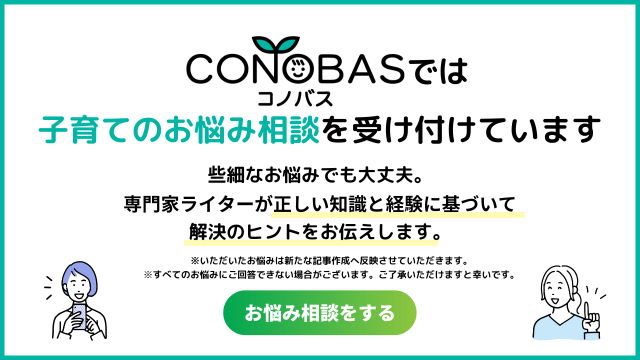場所見知りが激しい子〜幼少期にできる年齢に合った対応とは?
この記事を書いた人


中川さくら
- 保育士
- 児童指導員
学生時代に障害児福祉を学び、小学校の特別支援教育支援員や療育施設の保育士、学童保育、小学校などで、子どもたちやそのご家族と関わる仕事を約10年ほど経験しました。
今は、保育園に通う1歳の息子がいます。
昔バックパッカーだったので、いつか家族で世界を旅することが夢です。
知らない場所や不慣れな状況などに戸惑い、嫌がったり泣いたりすることを「場所見知り」と呼びます。
知らない場所へ行くと固まってしまう。慣れない状況だと泣いてしまって、おでかけが楽しめない…。
このような場所見知りの激しいお子さんに、悩んだことはありませんか?
CONOBASにも、「旅行へ行っても大泣きしてしまう」という激しい場所見知りをする3歳のお子さんのママから、お悩みをお寄せいただきました。
極度の怖がりで場所見知りが激しい…
3歳男の子 ママからのご相談
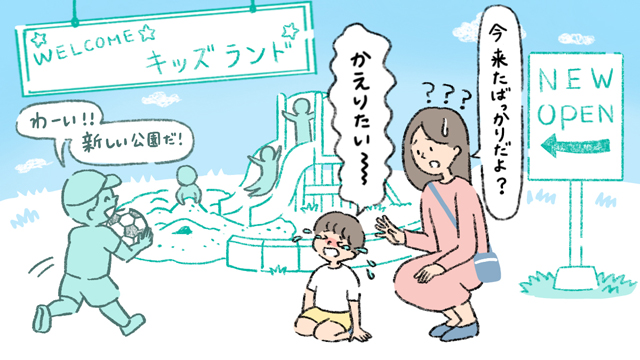
極度の怖がりで、場所見知りがひどく旅行先で大号泣します。発達障害の可能性があるのでしょうか。その場合、早めに療育したほうがいいと聞いたのですが…
買い物や病院、公園、知り合いのお家など、「初めての場所」へ行くことは日常で避けることができず、相談者様はそのたびに憂鬱な思いを抱えているかもしれません。
「いろいろな場所へ連れて行って、新しい経験をさせてあげたい」と思って行動しても、泣いてママにしがみつくお子さんに、悲しくやりきれない気持ちになることもあるでしょう。
長期間激しい場所見知りが続くと、このまま成長を待っていて良いのか、それとも早めに対応を考えた方が良いのか、不安に思う方もいますよね。

場所見知りをする理由を年齢別に整理して、幼少期にできる対応について一緒に考えていきましょう。
目次
1.【年齢別】場所見知りする理由

子どもが場所見知りをする理由は、年齢や発達段階によって異なります。
また、「場所見知り」と言っても、激しく泣く、じっと固まって動かなくなる、など現れ方はさまざまです。
発達の特徴と一緒に、場所見知りするお子さんの気持ちを読み解いていきましょう。
1-1.【0〜1歳】安心できる場所との区別がつく
赤ちゃんの「人見知り」はよく知られていますが、知らない場所で泣いたり不慣れな場所で不安がったりする「場所見知り」をすることもあります。
早ければ生後4~5ヶ月頃に人見知りが始まり、同じくらいの時期に場所見知りが始まることがあります。
この頃に人見知りをする理由は、特定の人との愛着関係ができたことにより「そうでない人」を区別できるようになった、いわば発達の証と考えられています。
「安心できる場所」がわかり少しずつ記憶できるようになったことで、「そうでない場所」との区別がつけられるようになり、「場所見知り」として現れる可能性があります。
1-2.【2〜3歳】認識力・記憶力の発達とイヤイヤ期
2〜3歳頃のお子さんは、記憶力や認識力が発達することにより「いつもと違う雰囲気」や「いつもの場所なのに違う人がいる」ことに、より一層気づけるようになります。
いつもと違うことに違和感や不安を感じると、「そこへは行きたくない」「抱っこじゃなきゃ嫌」など、したいこと・したくないことを強く意思表示するイヤイヤ期とも重なって、癇癪として現れることがあります。
「赤ちゃんの時は平気だったのに、急に場所見知するようになった」という子がいるのは、背景にこのような発達が関係している可能性があります。
幼稚園入園や習い事を始める子が多い年齢でもあり、プレ幼稚園や支援センターでママにくっついて離れない子もいるでしょう。
筆者にも引っ込み思案な2歳の子どもがおり、「せっかく来たのに」「みんな楽しそうなのにな」と、周囲の子と比べてしまった経験があります。
ですが、新しい人や環境と出会う時期だからこそ「安心したい」思いが強く現れているのでしょう。お子さんたちは好奇心と不安の狭間で、葛藤しながら成長しています。
1-3. 【4歳〜】ひとりひとりの気質
人見知りと同じように場所見知りも、年齢や経験を重ねるうちに、ピークの時期が過ぎて徐々に落ち着くことが多いため、心配しすぎる必要はないでしょう。
ですが、ひとりひとりの持っている気質によって、その後も場所見知りが続くこともあります。
なぜなら4歳頃になると、人いちばい繊細な子や、怖がりや慎重な子など、持って生まれた気質が徐々にはっきりと現れてくるからです。
そういった気質によっては、4歳以降も新しい人や場所に対して不安を感じやすい子もいます。
「ずっとこのままだったらどうしよう」と、不安をつのらせているママやパパもいるかもしれません。
4歳以降のお子さんが激しい場所見知りをするのにはどんな理由があるのか、何が苦手なのか、次の章で詳しく解説します。お子さんに合った対応方法を考えていきましょう。
2.4歳以降も場所見知りが激しい子が苦手なこと

場所見知りをする背景に、お子さんが苦手なことが潜んでいるケースがあります。
お子さんが抱えている困りごとを知り、対応のヒントにしていきましょう。
2-1. 先の見通しを持つのが苦手
場所見知りが激しいお子さんは、先の見通しを持つこと・今起きていないことをイメージすることが苦手なケースがあります。
新しい場所では、何が起こるかわからず見通しを持ち辛いため、想定外のことが起きて動揺したり、パニックになって大泣きしたりしてしまいます。
次の章で解説しますが、写真等を使って予告をして、これから起こることへの見通しを持てるよう配慮してあげることで不安な気持ちが和らぐことがあります。「大丈夫だった」という成功体験を積み重ねていくことが大切です。
2-2.いつもと違うことに強い不安を感じる
場所見知りは、危険なことや不安なものから「自分を守ろう」と自然と反応する「防衛本能」でもあると考えられています。
賑やかな雰囲気が好きで新しい場所にわくわくする子もいれば、慣れている場所や静かな空間に心が落ち着く子もいますよね。
場所見知りをするお子さんは後者であることが多く、感受性が強く心配性で繊細な傾向があります。
「ここが安全なのかわからない。何が起こるか怖い。」と防衛本能が強く働いているのかもしれません。楽しめそうな場所へ連れて行っても、不安感から帰りたがることもあるでしょう。
まずはお子さんの不安に寄り添い、「知らない場所はドキドキするよね、一緒にいるから安心してね」と伝えて少しずつ慣れさせたり、繰り返し経験したりするのがおすすめです。
「ここは大丈夫なんだ。ママがいるから怖くないんだ。」と思える場所を、1つずつ増やしていくことを目指しましょう。
2-3.特定の感覚が過敏すぎる
普段と違う場所の物音や賑やかな声、チカチカした電気や日の光、匂いなど、他の人が気にならないようなことに敏感に反応するお子さんもいます。
その感覚の不快さを明確に言葉で伝えられず、「帰りたい」「ここは嫌」と拒否をする、大泣きして訴える、という行動が激しい場所見知りに見える可能性があります。
どのような時に、どんな刺激を苦手としているのか、お子さんを日頃からよく観察することでヒントが得られるかもしれません。
また、年齢が低い時の方が過敏さが強く出やすいので、成長と共に許容範囲が広がっていくことも多く見られます。
お子さんが抱えている辛さを受け止めることを第一歩に、徐々に刺激を緩和する方法を一緒に探していけると良いですね。
・感覚過敏とは?子どもが過ごしやすくなる対応法や現場での事例を紹介
3.場所見知りが激しい子におすすめの対応

3-1.行く場所を写真で予告する
見通しが持つのが苦手なお子さんや、普段と違うことに不安感を強く持つお子さんには、できる限り予告をすることがとても大切です。
言葉よりも、写真など目で見た物の方がイメージが湧きやすい子が多いです。「想像したものと実物が違う」ことを防ぐため、できれば実物の写真や動画を見せるのがおすすめです。
お子さんの年齢や理解度に合わせて、以下のことを伝えてください。
- 行く場所
- 行く方法
- 何をする場所か
- どんな人がいるのか
目的地だけでなく、電車、バス、車や自転車など、交通手段もお子さんには大切な情報です。予告をすることでイメージしやすくなり、気持ちの準備をすることができます。
3-2. 無理強いしない
大人でも、苦手な環境や安全かわからない場所で「リラックスしてたくさん楽しまなきゃダメ!せっかく来たんだから」と強制されることを想像してみてください。そんな荒療治では好きになれないどころか、むしろ逆効果ではありませんか?
お子さんも同じで、嫌がる理由があるのに「せっかくきたんだから遊ばなきゃだめでしょ」とママからむりやり引き離すと、拒否が一層強くなってしまうでしょう。
「入らないで見るだけでも大丈夫だよ。」「やりたくなったら、ここまで入ってみようか。ママも一緒に行くよ。」とお子さんのペースを尊重してあげると、「ここまでなら大丈夫」という範囲を広げていくことができます。
個人差があり、時間がかかるかもしれないですが、「行ってみよう」というお子さんの好奇心と勇気をバックアップできるのは、大好きな人からもらえる安心感なのです。
3-3.新しい場所の中で安心材料を作る
新しい場所へ行く時に、事前に安心材料を用意していくのはいかがでしょうか。
たとえば旅行なら、いつもの枕やお気に入りのぬいぐるみなど「これがあると安心する」と思える物を、お子さん自身が選んだり、ママと相談して選んだりしても良いですね。
初めて行く公園なら、写真を見せながら「いつも行く公園と同じで、ブランコがあるから嬉しいね!」と「共通点探し」をするのも方法の1つです。
また「初めて見るものはあるかなぁ?」「この滑り台は、いつもの所と色や高さが違うんだね。」と、行く前に「初めて探し」をしてみるのも、心の準備をすることに繋がるかもしれません。気持ちの安心材料を用意してみましょう。
3-4.診断の有無より、まずは特性を理解する
近年は発達障害が広く知られるようになったこともあり、「うちの子育てにくい…。もしかして発達障害?」と不安に思う方がたくさんいます。
明らかにお子さんにとってサポートが必要な場合は、早期療育が有効なケースもあるでしょう。
しかし、3〜4歳頃までは発達障害の診断が困難なケースも多くあります。発達障害の診断を急ぐより、まずはお子さんの特性をよく理解して、苦手なことをサポートする方法を探すことが大切です。
場所見知り以外にもお子さんの発達に気がかりなことがある場合や、相談できる人がいなくて悩んでいる時には、以下のような地域の施設へ相談することもおすすめです。
- 保健センター
- 子育て支援センター
- 児童発達支援センターなど
どこへ相談したら良いかわからない場合は、自治体の子育て相談窓口で聞いてみると、案内してもらえます。
相談に行く際には、ご家庭でのお子さんの様子以外にも、保育園等での様子も参考になりますので、先生に事前に聞いておくとなお良いでしょう。
4.場所見知りが激しいのは、おうちや家族が安心できるからこそ

激しい場所見知りは、普段の生活でも大変な場面があるでしょう。旅行をして家ではできない体験や家族の思い出作りをしたいというのも、お子さんを思う自然な気持ちですよね。
成長していくうちに旅行での楽しみを知ることもありますし、初めての場所に慣れるまでの時間が短くしていけたら、まずは良いのではないでしょうか。
もし新しい経験が今はできなくても、毎日同じ公園や散歩道の中でも、季節ごとに変わる花や虫を探したり、違う道を通ることから始めたりすると、新しい発見や経験ができるかもしれません。
何よりもお子さんが「自分の家が安心できる。ママがいると落ち着く。」と思える環境で育っているからでもあり、とても素敵な関係を築けているからこそではないでしょうか。
いずれ手が離れていってしまうお子さんとの時間を、人よりも多く過ごしていると思い、心が少しでも軽くなることを願っています。
こだわり・癇癪がひどい、落ち着きがない、言葉がゆっくり…子どもの発達に悩んでいませんか?[PR]
思い通りにいかない毎日に、イライラしたり、不安になっていませんか?
それは子どもの「言葉にできないSOS」かもしれません。
お子さまの行動の背景には、その子特有の「感じ方」や「学び方」が隠れていることがあります。
リタリコジュニアは、遊びを通して「生きる力の土台」を育む、児童発達支援の専門教室です。
★リタリコジュニアの特徴
✓ 「遊び」が「学び」になるオーダーメイド指導
お子さまの「好き」なことから始め、遊びを通して自然に言葉やコミュニケーションを促します。無理なく「できた!」を重ねることで、自己肯定感を育みます。
✓ 癇癪やこだわりの背景にある気持ちに寄り添う
なぜ癇癪を起こすのか、なぜこだわるのか。その理由を専門家が一緒に考えます。「見通しを立てる」などの工夫で、お子さまの不安を安心に変えていきます。
✓ 保護者の心が軽くなるサポート
お子さまへの指導だけでなく、保護者向けのサポートも充実。「どうして分かってくれないの?」という悩みが、「こうすれば伝わるんだ!」という発見に変わります。子育ての孤独感から解放されましょう。
いつも本当に、お疲れさまです。
まずは相談だけでも大丈夫です。困ったときは抱え込まず、専門家にも頼ってみてくださいね。
<無料>個別相談・体験授業のお申し込みはこちら>>リタリコジュニア
・怖がりすぎる子どもが心配!保育士が考える原因と克服法をご紹介
・家以外では黙ってしまう。初めての人と話せない…。対応のポイントは?【言語聴覚士に聞く】
・いつまで続く?3歳で人見知りがひどくなる原因と克服方法