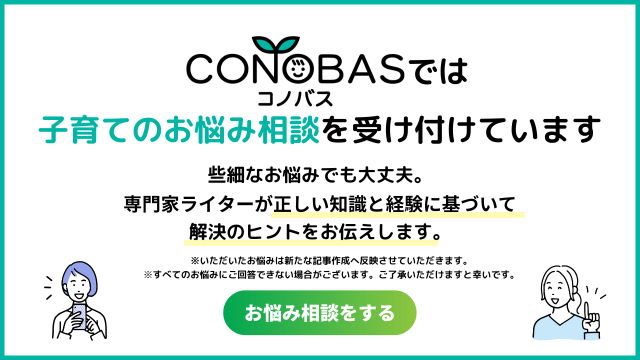よその子・きょうだいとの比較をやめる方法、比べることのデメリット
この記事を書いた人
久美子
- 公認心理師
- 臨床心理士
5歳と7歳(小1)の息子のアラフォーママ。
公認心理師・臨床心理士の資格を持っています。
心理士の仕事をしながら、発達心理学の視点も踏まえて、日々、子育て奮闘中。
夫にも積極的に育児に参加してもらい、親子でハッピーになれる時間を模索しています。
前半に引き続き、5歳の娘を育てる「TA」さんの「他の子と我が子を比べてしまい辛い」というお悩みにお答えしていきます。
お悩みの回答者は、今回も公認心理師ライターの久美子さんです。
前半では、「なぜ比べてしまうのか」についてお話しいただきました。
【前半】他の子と比べてしまう…「比べる病」やめられないのはなぜ?
後半の今回は、「よその子・きょうだい間での比較がもたらすネガティブな影響・比べない方法」についてです。
「比べる」ことが悪影響だと聞きますが果たして本当でしょうか? きょうだい間での比較についてもお聞きしています。
我が子を他の子と比べてしまい、辛いです……
❚ 5歳女の子のママ「TA」さんからのご相談
こんにちは、5歳の娘の母親TAと申します。どうぞよろしくお願いします。
娘が通う幼稚園のクラスには、子どもたちがその時々に描いた可愛い絵が飾られています。先日、公園に遠足に行ったときの絵も飾られていました。年長になって急に、みんなとても絵が上手になっていました。
娘の絵はどれだろうと探してみて、ビックリ。娘の絵は、3歳児が描いたようなぐちゃぐちゃな殴り描きのような絵でした……。
もちろん、子どもひとりひとり違うと言うことは分かっています。でも、なんだか軽いショックを受けてしまいました。
そういえば、娘の友達は、もう上手にひらがなが書けて、ママに手紙を書いてくれるそうです。娘も簡単なひらがなは書けるようになってきましたが、手紙を書くなんてまだまだ考えられません。
こんな風に、他人の子と比べるのはよくないと、自分に言い聞かせているんですが、どうしても比べてしまって私自身苦しいです。
どうすれば、比べないでいられるようになるでしょうか?
今回も、心理学の研究結果を紹介しながら、
「比べる」ことにどんな影響があるのか、
比べないために親ができる対処法について紹介していきます。
それでは、一緒に考えていきましょう!
目次
1.「よその子と比べる」子どもへの影響・デメリット

〇ママTA:
すごく気になるところですが、やっぱり「比べられる」のって、子どもにもよくない影響がありますよね?
私も親に比べられたことがあったのですが、何とも言えない気持ちになったことを覚えています…。
〇心理師・久美子:
そうですね。比べることは避けたほうが良いと言われています。
自分よりもできる子と比べられると、子どもは「イライラや妬み、孤独」を感じやすくなります。大人でも、自分よりも優秀な人と比べられたら、自尊心が低下してしまいますよね。
例えば、テストの成績を返される場面を思い浮かべてください。
もし、我が子のテストの点数が悪かったとしたら担任の先生からどんな言葉がけで返してほしいですか?
「70点だった」とただ点数を言われるのと、「みんな100点だったのに、あなただけ70点で他の生徒よりも低かった」と言われるのとでは、どちらが好ましいと感じるでしょうか?
海外の中学生を対象とした研究では、他の生徒と比べて成績をフィードバックされた生徒は、勉強への自信が低下していたそうです。
つまり、よその子と比べられて「できない」と指摘されると、子どもは自信を失いやすいことが示唆されます。
研究では、担任の先生でしたが、親からのフィードバックにも同じことが言えます。
特に学業については、勉強への自信が低下すると、学ぶ意欲やモチベーションも損なわれてしまいます。そうすると、子どもの学力そのものの低下に繋がることが考えられます。
1-1.気づかずやってしまいがちな「きょうだい比較」も要注意
〇ママTA:
やっぱり影響があるんですね!? 小学校に入ったら、ますます比べることも多くなりそうですが、気をつけないと。
下の子は赤ちゃんなので、まだ今は比べるってことはないのですが。
私の夫は三人男兄弟で、あるとき母に、お手伝いをしないことを怒られたときに、「お兄ちゃんなら、もっとしてくれるよ!」と言われて、やる気をなくしてよけいにお手伝いしなくなったそうです、汗。
やっぱり、きょうだいで比べるのも問題がありますよね?
〇心理師・久美子:
きょうだい比較はデメリットが大きいと感じています。
きょうだいは自分にとって、一番身近な存在ですよね。必然的に親から比べられることも多くなります。
ここでひとつ、親からのきょうだい比較が子どもたちの心理面に与える影響についての研究を紹介します。
ある研究では、大学生に子どもの頃を思い出してもらい、きょうだいよりも親の愛情を注いでもらえたかどうか尋ねました。
その結果、「きょうだいよりも愛情を注がれなかった」と感じている学生は、きょうだいへの劣等感が高いことがわかりました。特に、比較対象が「兄・姉」の場合は、劣等感が高くなったそうです。
子ども時代を思い返してみると、確かにお兄ちゃんやお姉ちゃんは弟や妹よりも年齢が上なぶん、先にできてしまうことが圧倒的に多かったですよね。
生まれた順番で下の子ほど、劣等感を感じやすい環境にいるという視点は子どもの自尊心を守るためにも重要です。

┋ 心理師・久美子の子育て話:どっちが好き?どっちが偉い?
娘からよく「ママは私とお兄ちゃんどっちが好き? どっちがえらい?」と聞かれます。そんなときは、これは試されているなと思い、絶対にどちらかが「上と下」「えらい・えらくない」という話はしないように心がけています。
「ママはどっちも好きだし、二人とも頑張ってくれていると思ってるよ」と返すと、娘はにっこり笑って「そうなんだ」と言ってほかの話をしてきます。
もしかしたら、「あなたのほうが好き。あなたのほうがえらいよ」と言ってもらいたかったのかな?と頭をよぎることもありますが、いまのところきょうだい仲は良いです。
私自身も両親からきょうだいで比べられたことはほとんどなく育ってきましたので、きょうだいの仲がいいねとよく言われています。
子どもにとっては世界でたった一人のパパとママです。親の愛はきょうだいで半分に分け合うものではなく、きょうだいの分だけ愛情は2倍、3倍に増えるものです。きょうだいを仲良しでいさせてあげられるのも、親次第です。
【エッセイ】子どもは10歳前後で対人比較を始める(研究の紹介)

小学校に通う年齢の子を児童期と言います。児童期の子どもは自分が物語の「主人公」です。
発達的にも「自己中心性」と呼ばれる自分が世界の中心だと考えて生きている時期です。この時期の子どもは、自分自身をポジティブに見ているので、「こんなこともできるんだよ」「わたしが一番すごい」などが口癖ですね。
10歳前後(小学校3年生〜4年生頃)から、子どもは年齢が上がるにつれて、他者の視点に立って、相手の意図や考えといった「心の状態」を理解するようになります。すると、子ども同士でも「対人比較」を始めます。誰かと自分を比べることで、自分を客観的に見ることができるようになります。
このことを示唆する研究として、児童期の万能だった自己評価や自尊心が10歳前後で低下していくことがわかっています。
高学年になると、友達や仲間といった集団での人間関係が増えるので、人と比べる機会も増えます。そうすると、年齢が上がるにつれて自己評価の低下も起こりやすくなります。
また、自己評価の低下で、相手への妬みといったネガティブな感情も抱きやすくなります。
もし、子どもが自信をなくしてしまったり、嫉妬などのネガティブな感情でつらそうな場合は、子どもの話を傾聴することでそのつらさを軽減することができます。
また、自分の気持ちを伝えるのが苦手な子は、ソーシャルスキルトレーニング(SST)が有効だとされています。
10歳以降の子どもたちが置かれている環境は、意外とシビアです。大人同様、人と比べることが増えること、客観的に自分の能力や立ち位置を知ることになります。
自己評価や自尊心の低下が感じられたら、まずは子どもの話に耳を傾けてあなたの味方だよという姿勢を表すことが大切です。
2.どうしてうちの子は…比べるのをやめる方法・練習

〇ママTA:
他人の子と比べるのはよくないことなのだと、改めてよく分かりました。
でも、「悪いからやらないようにしなきゃ」と頭では分かっていても、なんというか、反射的にしてしまうんですよね…。他人と我が子を比べない方法って何かあるんでしょうか?
〇心理師・久美子:
もし反射的に比べてしまったとしても、大丈夫です。そのあとに挽回できる方法はあります。
もしよそのお子さんと比べてしまいそうになったら、「過去の我が子」と比べてみてください。
先ほど紹介した担任の先生が成績をフィードバックする研究にヒントがあります。
他の生徒と比べて成績を伝えると学業への自信が低下しやすいとありましたが、過去のその子の成績と比べてフィードバックした生徒は、現在の成績が低くても高くても学業への自信は低下しなかったそうです。
つまり、個人の中での比較は、自尊心の低下を防ぐことができるということです。
TAさんの娘さんも日々成長しています。「おしゃべりが上手になった」「ぬり絵の線からはみ出なくなってきた」など、1年前と比べたらできることがかなり増えていることに気づくと思います。
ささいなことでも、以前は全くできなかったことに気づいたらできていることもあります。0が1になるのはすごいことです。

また、「できた・できない」の成果だけで判断するよりも、できるようになるまでの成長のプロセスの方を大切にしてあげましょう。
何事もできるようになるにはある程度の練習が必要になります。いまできるようになっている事柄は、娘さんが少なからず練習し、努力したプロセスがあったからです。
過去の我が子と比べて、成長が実感できると、我が子への愛おしさで胸がいっぱいになるでしょう。そうすれば、他の子と比べたくなる欲求を抑えることができます。
┋ 心理師・久美子の子育て話:「なんでうちの子は…」から「頑張っているんだな」へ
私の7歳の息子は1年前はプールに顔をつけることができませんでした。
スイミングに習わせましたが、最初の3ヶ月はやっぱり水に顔をつけられず、他のお子さんが恐れずにもぐっているのを見て、「なんでうちの子は……」と毎回思っていました。
4ヶ月目に、ようやく顔をちょっとだけつけられるようになりました。一度できると自信がつき、自由時間に自分で顔をつける練習を始めました。自発的に練習している我が子を見て、「ああ、この子なりに頑張っているんだな」と愛おしくなったことを覚えています。
スイミングを習ってもうすぐ1年になり、息子は「けのび」ができるようになりました。他の子よりもゆっくりとした歩みですが、この子はこれでいいと思っています。
2-1.子育てで活かせる「ものはかんがえよう」の心得 <リフレーミング>
〇ママTA:
過去の子どもと比較するって、いいですね! これ、参考にしてみます!
あ、だけど、全然成長してなかったらどうしよう。娘は、運動も苦手で、公園で練習しているのにまだ、前回りもできなくて…。
正直、消極的な娘にイライラしてしまうこともあるんです。
〇心理師・久美子:
比べてしまってお子さんの不得意な面ばかりが見えてしまう場合は、「リフレーミングで短所を長所に言い換える」のがおすすめです。
リフレーミングとは、コミュニケーション心理学で「対象の枠組みを変えて別の感じ方を持たせること」です。
例えば、鉄棒の前回りの練習をしてもすぐにやめて、他の遊具で遊びはじめてしまうとき、親の目には「めんどくさがり」で「飽きっぽい」という短所に映ります。こんなときは、枠組み(フレーム)を変えてみましょう。
「めんどくさがり」は、興味を持ったことには熱中できる、物事の切り替えが早いと言い換えられますし、「飽きっぽい」は、素直で好奇心旺盛と言い換えることができます。「消極的」は、調子に乗らず落ち着いてこつこつと取り組める、となりますね。
このように、ポジティブな側面に光を当ててみると、「いいところもあるじゃない。ものは考えようだな」と許すことができます。
リフレーミングは企業の人材育成でも使われるスキルです。その子の短所を「プラス思考で考える」、「ネガティブな表現を別の表現に言い換えてみる」といった習慣をつけてみましょう。

それでもイライラしてしまったときは、アンガーマネジメントで怒りと上手に付き合ってみましょう。「怒り」の感情は、ピークの状態になる前にいくつか段階を踏むことがわかっています。具体的には以下の6段階があります。
ステップ1 疑惑、疑問
ステップ2 困惑、戸惑い
ステップ3 不満、納得できない
ステップ4 ムカつく、イライラする
ステップ5 怒り、カッとなる
ステップ6 暴力、暴言
怒りをコントロールするには、早めの段階で気がつくことが大事です。自分の体の状態や表情を観察してみてください。
ステップ3ぐらいになると、「少し呼吸が荒くなってる?」「口調が強くなってる?」かもしれません。
ステップ4のイラっとしたときは、いわゆる鬼のように唇が「へ」の字の形になって、眉尻が上がっているかもしれません。
このときは、自分でコントロールできるギリギリの「怒り」を感じていますので、思い切ってその場から離れてみましょう。
家にいる場合は、トイレに行ったり、ベランダや庭などの外に出てみましょう。あるいは、別の部屋でお茶を飲んだり、軽くストレッチしてもいいです。人は、怒りの対象が視界から消えると、自然と怒りの感情が下がっていきます。
すぐに離れることができないシチュエーションでは、ゆっくり呼吸をしてみましょう。呼吸で気持ちが落ち着くと、怒りをやり過ごすことができます。
親子で実践!「アンガーマネジメント」をマスターして怒りの感情を上手に扱おう!
心理学的には、人は「自分が大事にしている物や信念が壊されそうなとき」「他者に侵害されそうなとき」に怒りを感じるとされています。子育て中に怒りを感じてしまうのも、ママ自身が大切にしている価値や信念があるからこそです。
子どもが自分の思うようにいかないのが子育てですから、イライラや怒りを感じたときは、自分が大事にしていることを守りたいから「怒り」を感じるのだと捉え直してください。少し、気持ちが楽になるはずです。
そして、ママが大事にしていることが我が子にとっても本当に必要で大事なことなのかは、別問題ですので、冷静に対処する必要があります。
2-2.アドラーに学ぶ<ポジティブ>な思考
〇ママTA:
なるほど、リフレーミングですね! 娘は、苦手なことが多いから伸びしろも多い! それに、苦手な事にも挑戦していて偉い! 私自身もこんな風に考えられたらなぁ。
〇心理師・久美子:
伸びしろ、その通りです。それでは、親子でできる自尊心を向上させる方法をご紹介します。
1日1回、「自分を肯定する時間、良いことを思い出す時間」を作りましょう。これは、ポジティブ心理学のセリグマンが推奨している方法です。
寝る前が一番、効果的です。子どもと布団に入ったら、ポジティブタイムを始めます。
お子さんに「今日の楽しかったこと、嬉しかったことを教えて」と聞いてみましょう。
きっと、幼稚園や小学校でお友達と遊んで楽しかったとか、ママに縄跳びができるところを見せてあげられた、などと答えてくれます。
また、自分自身に対しても問いかけてみてください。例えば、自分の好きな本を読んでいたり、趣味に没頭していた時間は、楽しい時間と答える人が多いです。
お子さんとポジティブになれた時間をシェアして、満たされた気持ちで眠りにつくと、親子で自尊心を高めることができます。
周りと比べてもんもんとするより、自分を褒める時間、良いことを思い出す時間を作るようにしましょう。
2-3.それではここで、練習してみよう(リフレーミング問題)
最後に、他のお子さんと我が子を比べてしまったときのリフレーミングの練習をしてみましょう。
< 問題 >
- 「引っ込み思案」をリフレーミングすると?
- 「頑固」をリフレーミングすると?
- 「しつこい」をリフレーミングすると?
- 「騒がしい」をリフレーミングすると?
- 「消極的な」をリフレーミングすると?
< 解答の例 >
- 引っ込み思案
→答え:思慮深い、慎重 など - 頑固
→答え:信念がある など - しつこい
→答え:粘り強い、諦めない強さ など - 騒がしい
→答え:元気、明るい、活動的 など - 消極的な
→答え:落ち着いている、慎重 など
3.「比較」するなんてもったいない!子ども時代はあっという間

〇ママTA:
ありがとうございました。耳の痛いところもありつつ、汗。心理学や社会学から考えてみると、また違った視点から理解できて面白かったです。
すぐに比べないでいられるかというと、難しそうですが。。教えていただいた方法を取り入れて、他の子と比べることを無くしていきたいと思いました。自分自身もポジティブタイムですね!
〇心理師・久美子:
はい、できるところから取り入れてみてください。
なぜ人は比べてしまうのか、その理由を知っていれば、自分を責めすぎなくて済みます。
特に、SNSは比べたくなるような刺激が多いため、ストレスがかかっているときは思い切ってSNSから離れることが有効です。そして、大事なことはお子さんの小さな成長を見逃さないように、常に過去の我が子と比較することかもしれません。
赤ちゃんの頃の写真を見ると、成長を感じられますよね。毎日、目につくように今より小さい頃の我が子をスマホの待ち受けにしたり、ホーム画面のウィジェットに写真アプリを配置しておくのもオススメです。
<編集後記>
日本人は他人軸の人が多いので、他人からの評価や見られ方をより大切にしてしまいがちです。
一方、自分の心や感情に従って生きている自分軸の人は、周りにいるだけでポジティブな気持ちにさせられることがあります。
他人との比較をせず、自分の過去を受け入れながら成長していくことが、親子双方が自分らしく生きるための秘訣かもしれませんね。
主な参考文献
・岩井俊憲(2016)感情を整えるアドラーの教え 大和書籍
大須賀隆子 児童期の認知発達と心理発達の特徴と支援について.帝京科学大学教職指導研究1(1)161-167
・叶少瑜(2019)大学生のTwitter使用、社会的比較と友人関係満足度との関係.社会情報学8(2)111-124
・重村菜月・外山美樹(2020)集団的自尊心と社会的比較志向性がネガティブな結果フィードバック後の自尊心に及ぼす影響の検討.筑波大学心理学研究第58号13-19
・大和美季子・吉岡和子(2011)きょうだいに対する劣等感と養育態度の認知との関連.福岡県立大学人間社会学部紀要20(1)61-69
・吉川祐子・佐藤安子(2010)対人比較が生じる仕組みについての心理学的検討.心理社会的支援研究 創刊号 41-53
関連トピックをご紹介!
・自分の意見が言えない「自己主張」できない我が子への親の関わり方
・幼児期から適切な自己主張「アサーション」を学ぼう!トレーニング方法やタイプは?
・子どもの自己肯定感は「傾聴」で伸ばそう!効果的な話の聞き方と6つのポイントをご紹介!