
人に頼る・助けを求める力「受援力」の育て方とは?公認心理師が解説!
この記事を書いた人
狩野淳
- 公認心理師
- 臨床心理士
大学、大学院にて発達心理学と臨床心理学を専攻していました。
臨床心理士と公認心理師の資格を保有しております。
子ども達とその保護者の方の支援を仕事にしており、子ども達へは主に応用行動分析を認知行動療法用いて、保護者の方にはブリーフセラピーを使ったアプローチを行っています。
もうすぐで1歳になる男の子がいて、毎日癒されています!
「困っていても人を頼ることができない」
「助けてもらうのをじっと待っているのが気になる」
我が子の助けてもらう姿勢について、お悩みはありませんか?
この記事では、小学生の子どもの「助けを求める力」=「受援力」を高めるにはどうすればよいのか、受援力を下げてしまう要因としてどのようなものがあるのかについて紹介しています。
受援力の発達は、子どもの生活力や生きやすさに直結します。ぜひ今回の内容を参考に、お子さんの受援力を伸ばしてあげてください。
目次
1.受援力とは?│人に頼る・助けを求める力を高めるべき理由

受援力とは、「困ったときに助けを求める力や心構え」を指します。
「助けを求めるなんて簡単でしょ」と考える方もいらっしゃると思いますが、様々な理由から助けを求めることを避けようとする子どもも一定数います。
受援力は子ども、特に小学生以降で非常に重要な力になります。
まずはどうして受援力が必要なのか、受援力が低いと子どもにどんな影響が生じてしまうのでしょうかについて解説していきます。
1-1.受援力が大切な理由
子どもは成長するにつれて、様々な出来事に出会います。
なかには自分1人では出来ないこと、わからないことといった「壁」にぶつかることもあるでしょう。
親御さんが近くにいれば一緒に考えたり、解決したりしてくれる手伝いをしてくれますが、いつでも親御さんが一緒にいるとは限りません。
そんな時に周囲の人に助けを求めたり、意地を張らずに素直に助けを受けることのできる心構えが重要になっていきます。
そうして壁を乗り越え、精神的に成長し、またひとつ大人になっていくのです。
1-2.受援力が低いとどうなってしまうのか
しかし、受援力が低いまま成長してしまうと、「きっとどうにかなる」「もう考えたくない」など、他力本願な思考や安易な考えをもったまま大人になってしまいます。その結果、気づいたときには取り返しのつかない状況に陥っていることも少なくありません。
大人になった彼らに対して、世間は必ずしも優しくありません。
「自己責任」として自分で何とかしなければなりませんが、協力を得る経験がないまま1人で問題を抱えてきた場合、はたして大人になったからといって問題に対応できるでしょうか。自立した彼らの身は自分で守るしかないのです。
少し極端な話になってしまいましたが、「人に助けを求める経験」「人から助けてもらった体験」「援助を受け入れる心」がなければそうなるケースがある、ということは覚えておいてほしいです。
2.助けを求められない子どもの心理とは?

受援力の大切さについて解説してきましたが、そもそもどうしてお子さんは助けを求めてこないのでしょうか。どのような心理が働いて今の状況になっているのでしょうか。
次に助けを求められない子どもの心理について解説していきます。
2-1.助けを求めたことによる成功体験が少ない
助けを求められない心理として、「助けを求めたことによる成功体験が少ない」ことが挙げられます。
「助けを求めたものの、助けてもらえなかった」「助けを求めたが『そんなことぐらい自分でやれ/考えろ』と注意されてしまった」などの経験から、「助けを求めても無駄だ」という心理が働いている可能性があります。
周りの大人からすれば些細なきっかけでも、子どもにとっては大きな傷つき体験になることもあります。
自分たちの言動を振り返り、そのような出来事がなかったか振り返ってみるといいでしょう。また、今後についてもそのような体験をさせないようにしていけるといいですね。
2-2.「助けを求める」=「恥ずかしいこと」という思いがある
また、子どもの中で「助けを求める」=「恥ずかしいこと」という思いがあるかもしれません。
特に長子の場合、「お兄ちゃん/お姉ちゃんになったから自分でやろうね」「こんなこともできないの?」「もう赤ちゃんじゃないでしょ?」という声掛けをしてしまうことも。
これにより、「自分で何とかしないといけない」「お願いすることは恥ずかしいことだ」という気持ちが強まり、助けを求められなくなることがあります。
親御さんとしては何気なく言った言葉でも子どもは大きく、重く受け取ってしまうことがあります。
そうならないように、頼ってきたこと自体は認めつつ、少しずつ自分で出来るようになる必要があることを伝えながら、1人で出来る環境も作り上げていきましょう。
2-3.「言わなくても助けてもらえる」という誤学習がある
日頃から自分で助けを求めなくても周囲の大人が助けてくれる環境にいると、「誰かが助けてくれる」「困ったら大人が何とかしてくれる」という誤った認識を持ち続けることになります。結果として、助けを求めることができなくなってしまいます。
いきなり自分1人で全てをやらせようとすると、「見捨てられた」「嫌われた」といった誤解を招く恐れがあります。
そのため、段階的に自分で行うことを増やし、助けを求めるまで手を出さずに見守るなどの工夫が必要です。
3.受援力を下げてしまう親のNG行動
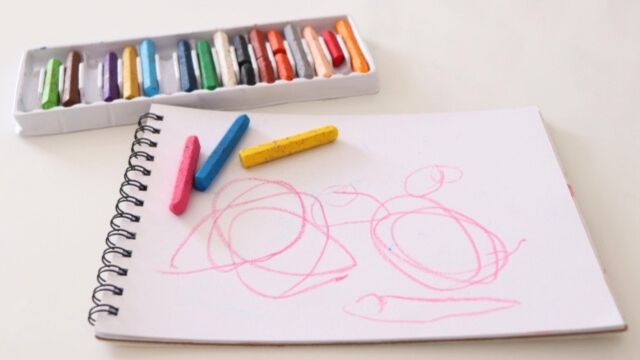
受援力が低い子どもの心理について解説しましたが、子どもの受援力が最初から低いわけではなく、様々な要因が組み合わさり受援力の低下に繋がってしまいます。
今回は特に子どもに大きな影響を与えやすい親御さんのNG行動を3つ解説していきます。
3-1.子どもが失敗しないように立ち回る
1つ目は「子どもが失敗しないように立ち回る」という行動です。
「我が子には悲しい思いをしてほしくない」と願う親御さんはとても多いです。筆者の私も子ども達には何不自由なく、毎日楽しく暮らしてほしいと願っています。
しかし、その思いが強すぎるあまり、子どものやることを先回りして、失敗しないようにレールを引いてしまう親御さんはとても多いです。
そのように子どもが失敗しないように、失敗しても落ち込まないように動きすぎてしまうと、「自分でやらなくても親がやってくれる」「親が何とかしてくれる」という思考が日常化し、受援力の低下を招いてしまうのです。
3-2.子どもの気持ちを察知してすぐ動く
2つ目は「子どもの気持ちを察知してすぐ動く」ことです。
子どもが何を感じているのか、どう思っているのかを察知する力が高いことは、それだけ普段からお子さんと関わり、お子さんのことを考えている証拠なので、とても素晴らしいことです。
しかし、お子さんの感情の変化を感じ取ってすぐに動いてしまうと、結果として「自分でやらなくても周りが何とかしてくれる」と考えるようになることも。
そのまま成長していくと「私が困っているのにどうして助けてくれないんだろう」といった「受け身思考」や「助けられて当たり前」といった好ましくない思考を持ってしまい、受援力を育てることができないのです。
3-3.助けを求められても後回しにする
最後が「助けを求められても後回しにする」です。
これもついついやってしまう親御さんは多いのではないでしょうか。
私も日々の暮らしの中で「やってー」「おねがーい」と息子から言われるのですが、家事や下の子のお世話をしているときなど手が離せず、「後でね」「ちょっと待っててね」と言ってしまうこともあります。
そのために、「息子の助けてほしいタイミング」を逃したり、手伝うこと自体を忘れてしまうこともあります。
そうすると子どもによっては「助けてほしかったのに助けてくれなかった」「助けを求めても無駄なんだ」と解釈する可能性があります。
理想としては、求められたら即行動に移す、もしくは「すぐ行くからね」と伝え、できれば3分以内には対応するなど、「助けを求めたら助けてもらえた」という経験に繋がるように日常生活を送れるといいですね。
4.頼る・助けを求める力を高める関わり

ここまで助けを求められない子どもの心理や受援力を下げてしまうNG行動について解説してきました。
では受援力を高めるにはどのようにすればよいのでしょうか。ここでは日常生活にも取り入れられる関わり方について3つ紹介していきます。
4-1.親がモデルを見せる
心理学用語に「モデリング」というものがあります。モデリングは学習方法の1つで、他者の行動を観察し模倣することで学びを深めていくことを指します。
受援力についてもモデリングを活用することができます。具体的には、お母さんがお父さんに助けを求める姿を日常生活の中で子どもに見せていきます。
同様にお父さんがお母さんに助けを求める姿、親御さんがお子さんに助けを求めてみることで自然と助けの求め方や「大人も助けを求めるんだ」=「自分も助けを求めてもいいんだ」ということを学ぶことができます。
4-2.子どもからの言動を待ってあげる
また、子どもからの「助けてサイン」を待つことも重要です。例えば、宿題で行き詰っている場面などで「わからないんだろうな」「助けてほしいんだろうな」とわかっても、あえて子どもからのサインが出るまで待ってあげましょう。
その際に、「目線で訴える」「『わかんないな』などの独り言を言う」など「察してほしい」「気付いてほしい」サインで親御さんが動くことは避けた方がいいです。
このようなサインで周囲の人が動いてくれると誤学習してしまうと、「察してくれない周りが悪い」「自分が出来ないのは周りが気づいてくれないから」といった思い込みをもったまま成長してしまう可能性があります。
そのためきちんとした援助要求(「手伝って」「教えて」「分からないよ」など)が出るまで待ってあげてください。
4-3.助けを求められたこと自体を褒める
最後に紹介したいのが「助けを求められたこと自体を褒める」です。
大人からすれば「これぐらい自分でやってよ」と思うことでも、まずは助けを求めてきたこと自体を褒めてあげてください。
「それだと人に頼りっきりの子になるのでは?」と心配になるかもしれませんが、「ここまでは1人でやってみようか」と声掛けしたり、「ここからは一緒にやろうね」と区切りをつけ、段階的に自分でやることを増やし、できた部分を褒めていくことで子どもは自然と出来ることが増えていきます。
そのため、まずは受援力を高め、「頼っていいんだ」「助けてもらうことは悪いことじゃないんだ」と感じてもらうことが大切です。
5.受援力を伸ばして子どもが社会にはばたく準備をしましょう

人間は社会的な生き物であり、他の人の助けなしには生きていけません。
大人からすれば当たり前のことかもしれませんが、それまで助けられることが当たり前だった子どもからすれば「自分から助けを求めないといけない」ことは難しいかもしれません。
しかし成長するにつれて受援力を求められる場面はどんどん増えていきます。
子どものためを思うなら、今のうちから「助けてあげたい」思いをぐっとこらえ、本人から助けを求める言動が出てくるのを待ち、少しずつ受援力を高めていきましょう。
毎日ちょっとずつ、世界が広がる「朝日小学生新聞」受験対策にも◎[PR]
「ゲームや動画ばかりで、将来が心配…」 「もっと視野が広がってほしい」
そんなふうに感じたこと、ありませんか?
それなら、子どもの好奇心スイッチを押すきっかけに、『朝日小学生新聞』を活用してみませんか?
毎日のニュース、昆虫のふしぎ、宇宙の話、季節や自然、科学、文化など。
子どもの「なんで?」「すごい!」「やってみたい!」を引き出す新しい発見が、ぎゅっと詰まっています。
読む力はもちろん、考える力・話す力も自然とアップ。好奇心から始まる「知る楽しさ」が、子どもの未来をぐんと広げてくれます。
💡「朝日小学生新聞」の魅力ポイント
- 毎日届く1部8ページの小学生向け新聞
- 全ての漢字にふりがなが付き低学年でも自分で読める
- 時事ニュースを分かりやすく解説。中学受験対策にも最適
- 読み物や漫画など、子どもの興味を引き出すコンテンツが豊富
- 日々新聞を読むことで、自然と考える力や知識が育める
毎日の小さな学びが、未来の大きな成長につながるはずです。
親子でも子どもひとりでも楽しく読めます。
これからの未来を生き抜く力、学びの力を伸ばすために新聞をご活用してみてはいかがでしょうか。
関連トピックをご紹介!
・子どもの失敗に親はどう対応する?失敗を恐れずに挑戦できる子に育てるコツ
・小学校低学年のいじめが増えている?いじめの原因や対処法を深く解説
・子育てに活かせる心理テスト!性格診断「エゴグラム」うちの子はどんなタイプ?





