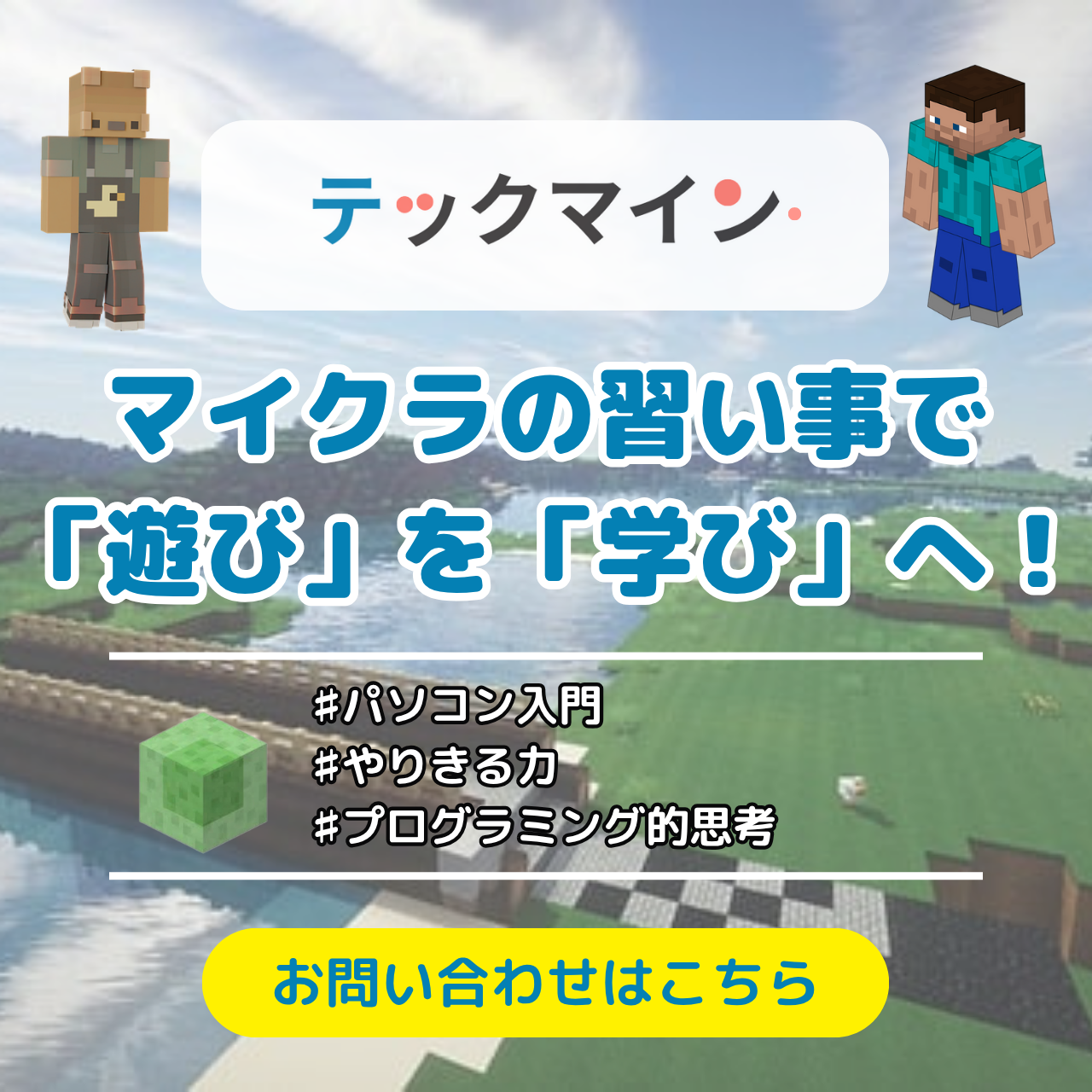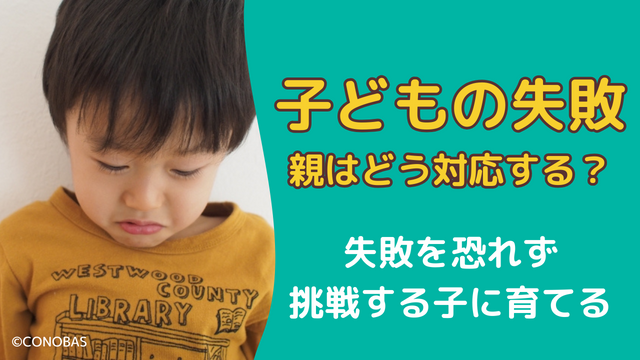
子どもの失敗に親はどう対応する?失敗を恐れずに挑戦できる子に育てるコツ
この記事を書いた人
平尾しほ
- 言語聴覚士
言語聴覚士免許を所有、児童発達支援センターでの勤務経験があります。
特に遊びの中でのことばの育ちを意識して個別療育を行っていました。
現在小学校2年生の息子がいます。
個別療育でのたくさんのご家族とのかかわりと子育ての経験を合わせて、皆様に分かりやすくお伝えしていきたいです。
飲み物をこぼす、忘れ物をよくする、物をなくすなど、日常のちょっとした失敗から、習い事の発表会や試合など、大事な場面での失敗するまで、子どもの失敗に直面し、親として対応に困ったことはありませんか。
失敗は子どもの成長に不可欠とは言っても、大事な場面で失敗して落ち込む子どもを見ると、先回りして失敗を回避したくなることもあるでしょう。
この記事では、言語聴覚士として児童発達支援センターに勤務し多くのご家族の悩み相談を受けてきた筆者が、子どもの失敗の受け止め方や、失敗を恐れずに挑戦できる子に育てるヒントを紹介します。
よくある子どもの失敗エピソードをもとに、適切な関わり方について親子の会話形式でお伝えしますので、ご家庭でのお子さんの様子と照らし合わせながら読み進めてみてくださいね。
目次
1.幼児期の失敗経験が大切な理由

失敗経験を積むことは、子どもにとって決してマイナスではありません。ここでは、なぜ幼児期の失敗経験が大切なのかをご説明します。
1-1.失敗は「学び」のチャンス
「失敗は成功のもと」とよく言われているように、失敗はなにかを成し遂げるためのひとつの過程です。
最初からなんでも上手にできることはないので、すべては失敗経験からはじまると考えられます。子どもは「失敗」から多くのことを学び、次にどう生かすかを試行錯誤する中で、成長していきます。
筆者の息子は5歳の時、洋服のボタンをうまく留められない時期がありました。何度も失敗を繰り返すうちに、息子はうまくできないことにイライラして、ボタンがついた洋服を避けるようになりました。
筆者はそのたびに「穴の方をボタンにひっかけるようにしてごらん」とボタンの留め方を丁寧に説明したり、「あと少しだね」「ボタンを留めるのって難しいよね」などと息子の気持ちに寄り添い、励ましたりしながら、練習しました。
するとある日、息子は「できた!」と満面の笑みで、ボタンをかけた服を見せてくれたのです。その表情は自信に満ちており、「失敗してもやればできるんだ」と実感した様子でした。
時間はかかりますが、失敗の積み重ねが成功につながります。「子どものために」とつい手を差し伸べたくなる瞬間もあるかもしれませんが、お子さんを信じて、失敗経験を見守っていきましょう。
1-2.失敗を乗り越えることで「生きる力」が身につく
失敗と向き合い、乗り越えることで身につく力もたくさんあります。
具体的には、
- 「悔しい」「悲しい」などの気持ちを切り替える力
- 周りの人が失敗したときに、気持ちを思いやる力
- 失敗から立ち直る力
- 試行錯誤して取り組み、やり抜く力
- 次に挑戦するときに不安に打ち勝つ力
などが挙げられます。
失敗を通して身に付く力は、さまざまな物事に前向きに向き合い、たくましく生きる力になるでしょう。
なるべく小さいうちに失敗して身につけておきたいですね。
1-3.失敗経験がない子どもはどうなるの?
失敗経験がない子どもは、失敗に対して耐性ができず、打たれ弱い人になる可能性があります。
大人になってから失敗した時に、落ち込んだり、立ち直れなかったりして、うまく気持ちが整理できずに、大きな挫折を味わうことになるかもしれません。
また、失敗から試行錯誤を重ねて「できた!」という体験も少なくなります。
失敗経験のないまま大人になってしまうと、物事に対する意欲も持続しにくく、あきらめやすい子になってしまうかもしれません。
2.子どもが失敗を怖がる理由
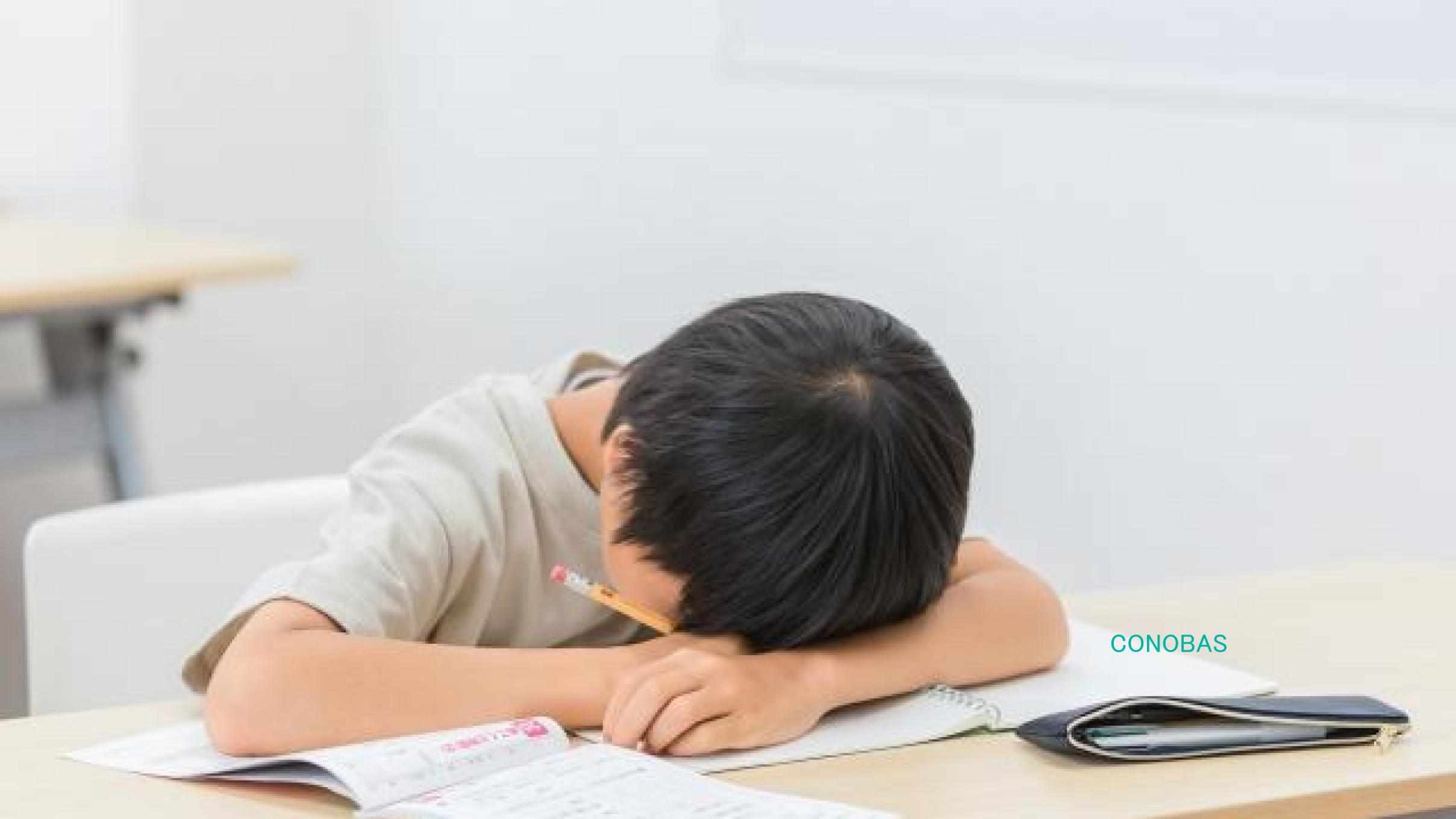
失敗経験は大切とは言っても、「失敗したくない」という思いを強く抱く子どももいます。そこには、どのような理由があるのでしょうか。
2-1.「予測がつかないこと」への恐怖
まず、「どうなるか分からない」「うまくいくか分からない」など、予測がつかず、未知なことへの恐怖心から失敗を怖がるケースです。
初めてのことや難しそうなことに対して、強い不安を感じ、消極的になってしまう子どももいます。特に、経験が少ない低年齢の子どもに多くみられます。
この場合は、「頑張ってやってごらん!」とお子さんを急かすのは、逆効果です。他の人の様子やお手本を丁寧に見せてから、お子さんのタイミングを見計らって挑戦を促しましょう。
2-2.「失敗したらどうしよう」という不安
「失敗したら怒られるかも」「恥ずかしい」という思いから失敗を怖がる子どももいます。
過去に失敗した時に、親から強く叱責されたり、友達から笑われたりしたネガティブな記憶が「恐怖」につながっているのでしょう。特に、「お母さんに怒られたくない」というのは、子どもの行動を決める大きな要素になります。
また、4〜5歳ごろからお友達との関係性が深まることで、周囲の目を気にしたり、比較したりするようになるのも要因のひとつです。
一度芽生えた気持ちをすぐに消すのは難しいですが、「失敗しても大丈夫」という大人の声掛けや安心できる環境づくりが重要になります。
2-3.「失敗=ダメなこと」という思い込み
完璧主義なお子さんは、「失敗してはいけない」と自分にハードルを課し、「失敗はダメなこと」と思い込んでいるケースもあります。
小さな失敗でも「自分はダメだ」と自己否定に陥る傾向があります。常に失敗を避けるため、試行錯誤を重ねて成功する達成感も得にくいというデメリットもあるでしょう。
このタイプのお子さんは、できないことも含めて、今のありのままの自分を受け入れられる経験が必要です。
3.子どもが失敗した時の親の声がけ・対応のコツ

子どもが失敗してしまった時は、どのように声をかければよいのでしょうか。具体的な場面を挙げて、対応方法をご説明します。
3-1.飲み物をこぼした時
食事の準備で子どもがお茶を運んでくれた時、つい手が滑ってお茶がこぼれるという失敗はよくあると思います。
声がけのポイント:
・「お茶がこぼれてしまって悲しいね。びっくりしたね」→目の前で起きた客観的な事実と子どもの気持ちを想像して言葉にする
・「ふきんで拭こうね」「次はコップをまっすぐ持とうね」→失敗に対する解決策や次からできる改善点を冷静に伝える
5歳を過ぎると、先を見通して論理的に考えられるようになってくるので「どうしたらいいと思う?」と解決策を一緒に考えるのもよいでしょう。
親の気持ちに余裕がないと、「もう、何やってるの!」と言ってしまうこともあるかもしれません。なるべく子どもの気持ちに寄り添い、成功体験に繋げられるような声掛けを心がけましょう。
3-2.お皿割ってしまった時
お皿を割るという失敗は、「もう元に戻せない」という学びがついてきます。食後に食器を下げるお手伝いをしている時、お子さんがシンクに強くお皿を置いたことで、お皿が割れてしまった場面を想像してください。親はどのような対応をするのが適切でしょうか。
声がけのポイント:
・「大丈夫?怪我しなかった?」→お子さんに怪我がないか確認する・「割れてしまったね。びっくりしたね。お皿は割れるともう元に戻せないね」→お子さんの気持ちに共感しながら、目の前で起きた事実を伝える
・「危ないからお母さんが片付けるね」「次は両手でしっかり持とうね」「よそ見をしないようにしよう」」→解決策や改善点を伝える
お子さんの気持ちに寄り添いながら、お皿は割れてしまうと元に戻せないことを共有し、「大事なものが壊れて使えなくなったら悲しいね。次は両手でしっかり持とうね」「よそ見をしないようにしよう」など、具体的な解決策を示すことで、物を大切にする心が育まれていくでしょう。
3-3.忘れ物をした時
子どもの忘れ物は、特に就学後に目立つ失敗経験です。もしお子さんが忘れ物をして、「学校で困った」と落ち込んで帰宅したら、どのような対応をすれば良いのでしょうか。
声がけのポイント:
・「忘れ物すると困るよね」→落ち込んでいるお子さんの気持ちに寄り添う
・「これからは寝る前と学校に行く前の2回、持ち物の確認をしてみたらどうかな?」→忘れ物をしないための改善策を提案する
小学校に入学してすぐの頃は、持ち物の確認を親子でしますが、その後は子どもが自分で準備できるように促しましょう。例えば、指差しで確認をする癖をつける、チェックシートを作るなどです。
もし子どもの忘れ物に気付いたとしても、親がすべてをカバーするのは避けましょう。子どもは「忘れ物をした」という失敗を通して、「困ったな」「ちゃんと用意すればよかった」という気持ちを味わい、失敗を繰り返さないための改善策を考えるきっかけにつながります。
4.子どもの失敗にやってはいけない関わり

子どもの失敗に対して親がしないほうがよい関わりはどんなものでしょう。子どもの行動は、親の態度や表情一つで変わります。気を付けるべき3つのポイントを見ていきましょう。
4-1.大きな声で責める
子どもが失敗してしまうと思わず「だめじゃない」「前も言ったでしょ」と声を荒げてしまうこともあるかもしれません。しかしこのような声掛けには、解決策や次の行動が含まれておらず、子どもは「怒られただけ」の印象を受けます。
このような接し方が日常的に繰り返されると、子どもは「怒られるから失敗したくない。だからなにも挑戦しない」という思考パターンに陥ってしまいます。
感情的に大きな声が出そうな時は、「やっちゃったね。びっくりしたね」などと明るく声に出してみましょう。少し気持ちが落ち着き、子どもの気持ちに寄り添う対応ができるはずです。
4-2.不機嫌な態度をとる
子どもは大人の様子をよく観察しています。お子さんが失敗した時に、「大きなため息をつく」「無口になる」などの態度はやめましょう。子どもは敏感に「自分はよくないことをしてしまった」と察知します。
失敗して1番落ち込んでいるのは、子ども自身です。うまくいかなかった事実も一緒に受け止め、次に活かせるよう解決策を伝えましょう。子どもが失敗した時は、親の方から先に気持ちを切り替えることも大切ですね。
4-3.親がすべて解決してしまう
子どもが失敗した時、親がすべて解決してしまうのは避けましょう。子どもが解決策を考えたり、学んだりする機会を奪ってしまいます。そうなると、失敗は失敗のままで終わってしまい、成功へのステップとして積み重なりません。
また、「困ったら親が何とかしてくれる」と他人任せな思考になってしまう可能性もあります。子どもが自分で失敗を受け止めることも大切です。「次はどうしたら良いかな?」など、子どもと一緒に解決策を考えることを心がけ、見守る姿勢を大切にしましょう。
5.失敗を恐れず、挑戦できる子に育てる方法

「失敗したくないから挑戦しない」となると、新たな経験も増えず成長の機会を逃してしまいます。失敗への恐怖を乗り越えて、さまざまなことに挑戦できる気持ちを育てるためには、親子の信頼関係が欠かせません。ここでは、親との関わりで重要なことを3つご紹介します。
5-1.安心できる親子関係をつくる
自分がしたことが成功でも失敗でも受け入れてくれる存在があるということは、子どもが新たな挑戦をする力になります。
子どもは大人の態度や表情をよく見ているので、些細な変化でも「失敗して残念」というメッセージとして受け取ることもあります。物事の結果で子どもへの対応を変えてしまうと「失敗した自分にがっかりされてしまう」と不安になり、積極的に挑戦できなくなってしまう可能性があります。
結果に関わらず、子どもの頑張りを認め、「いつでも味方だよ」のメッセージを言葉にして伝えてみましょう。日頃から「どんな結果でも大丈夫」と子どもが心から安心できる親子関係を築くことが重要です。
5-2.親の失敗を子どもに見せる
失敗を恐れず挑戦できる子どもに育てるには、親の失敗を子どもに見せることも大切です。
仕事や家事など、身近な失敗談を子どもに話してみましょう。失敗した時の気持ちや、立ち直り方だけでなく、「試行錯誤の様子」を丁寧に伝えるのがポイントです。
日常の小さな失敗を「あ、やっちゃった。でもこうすれば大丈夫。次はこうしよう!」などと、失敗から解決のステップを見せることで、「ママでも失敗するんだ」「失敗したことがあっても、パパのようになれるんだ」とお子さんも安心でき、挑戦に対する前向きな意欲も湧いてくるでしょう。
5-3.親が先回りをし過ぎない
「それじゃ失敗しちゃうよ」と失敗する前に、子どもの行動を正してしまうことはありませんか。
「子どもの失敗をさせたくない」「周りからきちんと子育てをしていると思われたい」という気持ちが強いと、無意識で先回りをしてしまう人も少なくありません。
このように子どもを思うあまり、過剰なまでに子どもの行動や考えを制限したり、失敗となり得る「障害物」を取り除いたりする親のことを「ヘリコプターペアレント」といいます。
海外の研究では、ヘリコプターペアレントに育てられた子どもは、幸福度が低く、青年期および成人期においてうつ病を発症しやすいことが明らかになっています。(※1)
いつも親が先回りをしてしまうと、子どもには失敗に対する耐性が身に付きません。失敗を乗り越えるために「試行錯誤する機会」を奪うことになります。失敗を乗り越えて成功したときの喜びや達成感も味わうことがなく、自信も育ちにくいでしょう。
親が必要以上に子どもに注意を払っていると、子どもの主体性が奪われ、挑戦意欲が沸きにくくなります。
【コラム】「失敗を回避してあげたい気持ち」とどう向き合えばいい?
大きな怪我につながったり、他人を傷つけたりしてしまう場合には、親が先回りをして止める必要があるでしょう。また、子どもの年齢や発達に応じて、手助けが必要な場合は適度にサポートしてもいいです。
たとえば、5歳の子が野菜を洗うお手伝いをするときに水道の蛇口に手が届かないため踏み台を用意するのは必要な手助けです。しかし水道の蛇口から出る水の量を調整し、野菜を1つ1つ手渡すのは、やや先回りしすぎという印象を受けます。
必要なサポートをして、ある程度、子どもに自由にやらせてあげましょう。例え失敗しても「見守る」姿勢を持つことが大切です。
お子さんの気持ちを尊重し、たくさんの失敗を経験させてあげてください。お子さんの行動につい口出ししたくなったり、ハラハラしたりすることもあるかもしれませんが、根気強く見守ります。ママやパパの温かな眼差しによって、子どもは前向きな挑戦を続けることができます。
6.子どもの失敗は「信じて見守る姿勢」を大切にしよう

この記事では、子どもにとって失敗経験が大切な理由、失敗を「次の挑戦」につなげていくための親の関わり、子どもが失敗したときの具体的な対応法をお伝えしました。
子どもが失敗を恐れずに「挑戦する力」を育むためには、小さいうちから「失敗しても大丈夫」と伝え続けることや、「どんな自分も受け入れてもらえる」という安心感をお子さんに与えることが大切です。
親が過度に先回りすることは避けて、お子さんが安心して失敗・挑戦ができる土台作りを意識してみましょう。
参考文献
※1:Holly H. Schiffrin,Miriam Liss,The Effects of Helicopter Parenting on Academic Motivation,2-6-2017
関連トピックをご紹介!
・親子で「レジリエンス」を鍛えよう!年齢別の伸ばし方や折れない心を育む方法
・「あきらめ癖」のある子どものチャレンジ精神を育む関わり方
・子どものやる気を引き出す!3つの性格タイプ別「やる気スイッチ」を押す声掛けとは?