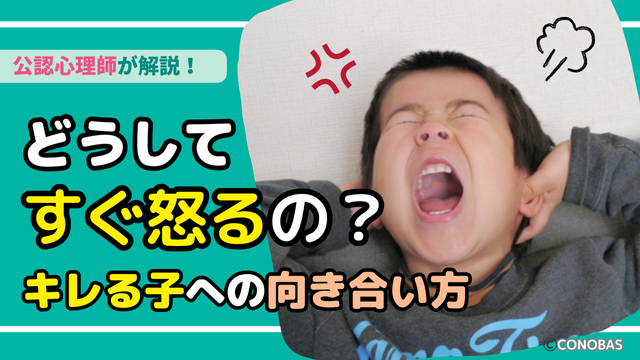
なぜすぐ怒るの?キレる子への向き合い方・押さえるべき大切なポイント
この記事を書いた人
狩野淳
- 公認心理師
- 臨床心理士
大学、大学院にて発達心理学と臨床心理学を専攻していました。
臨床心理士と公認心理師の資格を保有しております。
子ども達とその保護者の方の支援を仕事にしており、子ども達へは主に応用行動分析を認知行動療法用いて、保護者の方にはブリーフセラピーを使ったアプローチを行っています。
もうすぐで1歳になる男の子がいて、毎日癒されています!
「何かあるとすぐに怒りだすけど、どうして…?」
「育て方が悪いから怒る子になっちゃったのかな…?」そんな風に悩んでいませんか。
うちの子だけかなぁと思いがちですが、実はちょっとしたことで怒りだす子どもはたくさんいます。
「どうしてすぐに怒り出すのか」その背景に目を向ければ、子どもの言動にイライラしたり、育て方について後悔したりすることが少なくなるかもしれません。
今回は、子どもが怒ってしまう理由と家庭でもできる感情コントロールの練習法について紹介しています。ぜひ、日々の暮らしの参考にしてください。
目次
1.どうしてすぐ怒るの?主な原因を3つ紹介!

そもそも子どもはどうしてすぐ怒りだしてしまうのでしょうか。
怒っている子どもに適切なかかわりをするために、まずは子どもが怒ってしまう原因について確認していきましょう。
1-1.感情のコントロールが未熟だから
子どもは感情をコントロールすることができないので、大人のように「少し我慢しよう」「気にしないようにしよう」と考えることができず、些細なことでも大きく怒りの感情を表出してしまいます。
そのため、怒っていることを注意したり、大人がさらに大きな声を出して怒鳴ったとしても、怒りを止めることができません。
怒っている子どもを前にしたときは、「まだまだ感情を抑えられないんだな」「これは仕方のないことなんだな」と客観的な視点を持つことが大切です
★ こんな風に考えてみよう
子ども「えー、なんで!かってよ」
親「(買わない理由は何度も話したのに…腹が立つなぁ。でも欲しいって感情を我慢するのがまだ難しいのかぁ…。気持ちを玩具から反らすにはどうしようかなぁ)」
1-2.気持ちを適切に表現できないから
子どもは様々なことに興味をもったり、「これがしたい」「あれをやってみたい」と色々な欲求をもっているものです。
しかしそれらの感情をすべて言葉にすることができるわけではありません。そのため「あれをしたいのに伝わらない」「こう思っているのにわかってもらえない」とイライラしてしまい、怒りへとつながってしまうのです。
こちらも感情のコントロールと同様に、注意したから、躾をしたからといってすぐに改善するものではありません。子どもは成長とともに少しずつ自分の感情を言葉にできるようになります。
日ごろから子どもの様子をよく観察し、「こういうことかな?」「あれがしたいのかな?」と子どもの要求を読み取ってあげることで、気持ちを表現できないことで怒りだすことは回避できるようになります。
★ こんな風に考えてみよう
子ども「もー、やだ!やらない」
親「(またワガママが始まった。こういうときいつもそうだよな…。もしやこっちを先にやりたいのかな?)」
1-3.様々な要因に左右されやすいから
また、子どもは様々な刺激の影響を受けやすいです。音が大きすぎたり、寒すぎたり、暑すぎたり…様々な要因から不快感を持ちやすく、イライラしてしまいます。
一見何の問題もないように思えても、眠い、疲れた、お腹がすいたといった内面的な刺激によって怒りやすくなります。そのため、子どもが怒った時にはどんな刺激を受けているのかを観察して取り除いていく必要があります。
子どもが怒ったときの状況や時間帯を把握しておき、「この時間に怒ることが多いから眠いのかな」「この温度になると暑い/寒いと感じやすいのかな」など共通点を探してあげると怒りにくくなるかもしれません。
★ こんな風に考えてみよう
子ども「なんでだよ!ぜったいやだ!」
親「(こっちは優しく言ってるのに…すぐ大きい声出して。あぁ、でもこんな時間か。眠くなってるのね)」
2.怒りの我慢…感情のコントロールはいつからできるようになる?

さきほど子どもは「感情のコントロールができないため怒りやすい」と解説しました。
ではいつごろから感情のコントロールができるようになるのでしょうか。また、どのようにして感情をコントロールできるようになるのでしょうか。
2-1.一般的には3~4歳ごろ
一般的に感情をコントロールを学び始めるのは3~4歳頃からとされており、おおよそコントロール可能になるのは5~6歳頃といわれています。
もちろん状況や体調によってコントロールできるときとできないときがありますし、コントロール技術にも個人差があるため、もっと早くコントロールできるようになる子もいれば、7歳頃でもまだまだコントロールが苦手なお子さんもいらっしゃいます。
そのため5~6歳程度でしたら「我が子は全然できていない」と心配しすぎることはありません。
2-2.ポイントは脳機能の発達と経験値
では、なぜ3歳を超えると感情をコントロールできるようになり始めるのでしょうか。
3歳程度になると脳機能が発達し、言葉の理解が進み、相手が何を言っているのか、自分はどうしたいのかを少しずつ伝えることができるようになります。そこで「今は我慢しててね」「後でやろうね」といった大人の言葉を理解できるようになります。
もちろん最初のうちは理解はできても受け入れることができず、泣いたり暴れたりすることもあるでしょう。しかしそんな体験を積み重ねていくことで徐々にコントロールすることができるようになります。
逆に言えば、脳機能が発達しない、もしくは経験が不足している場合は感情のコントロールがいつまでもできないということになってしまいます。
普通に生活をしていれば脳機能は自然と発達していきますが、感情コントロールの経験は大人が作り出さなければ積み重ねることができません。子どもの主張をすべて受け入れ、「待つ」「我慢する」といった経験がないと感情コントロールへ至るのには時間がかかってしまうのです。
2-3.感情コントロールに関係する力「心の理論」とは?
また、感情をコントロールするためには相手の立場や自分の置かれている状況を客観的にみる力も必要とされます。
「これは怒っても仕方ないな」「意地悪をされているわけではないんだな」といったことが分かって初めて自分の気持ちをコントロールすることができるようになるのです。
心理学では、相手の立場に立って気持ちや考えを想像する能力を「心の理論」と呼びます。これは、他者の心を推測して理解する能力のことで、一般的に4歳から6歳頃に獲得されるとされています。
皆さんのお子さんは心の理論を獲得しているのでしょうか。もしサリーとアン課題で間違ってしまうようなら、まだまだ感情のコントロールは難しいかもしれません。
しかし心の理論を獲得していないからといって焦ることはありません。自然に身につけていきますので、それまでゆっくりと見守ってあげてください。
★ 心の理論の発達を見る方法「サリーとアン課題」
まず、サリーが持っているボールをかごの中にしまい、部屋から出ていきます。サリーがいない間に、アンがやってきて、そのボールをかごから箱の中へと移し替えます。しばらくしてサリーが部屋に戻ってきたとき、ボールはどこにあると思って探すでしょうか?
この質問に対する答えによって、心の理論の獲得状況を判断します。
- 「かご」と答える場合(心の理論が獲得されている)
「サリーは、アンがボールを箱に移したことを知らない」ということを理解し、サリーの視点に立って考えられるため、このように答えます。
- 「箱」と答える場合(心の理論が未発達)
自分だけが知っている「ボールは箱の中にある」という事実に基づいて判断してしまいます。他者であるサリーが自分とは違う情報を信じている、ということが理解できないため、このように答えます。
3.苛立ち・怒りのコントロールを強化しよう!家庭でできる練習法

ここまで様々な側面から子どもの感情コントロールの難しさについて解説してきました。
成長と共にコントロール力は向上していきますが、自分自身でコントロールする、そしてコントロールした結果上手くいったという「経験」も必要だとお伝えしましたね。
この経験を積ませるために親としてできることはどんなことがあるのでしょうか。ここでは家庭でもできる怒りのコントロールの練習法について紹介していきます。
3-1.「怒ることは悪いことではない」ことの確認
まず大前提として「怒る=悪いこと」ではないという認識を大人側がもつ必要があります。
怒りに任せて相手を否定する、物や人に暴力をふるうなどの行動は間違いですが、怒ることそれ自体が悪いことではありません。
「自分の思いを伝える」「おかしいことをしっかりと指摘する」という「自分を守る力」として怒りは重要な役割をもっています。そのため怒ること自体を否定してはいけません。
「こういうことで怒っているんだね」「こういう理由でカッとなっちゃったんだね」と怒るに至った経緯を言語化してあげることで「怒り」への理解を促してあげましょう。
3-2.怒ったときの解決方法を一緒に考える
怒っている子の行動で一番困るのが、暴れる、暴言を吐きまくる、動かなくなるといった行動ではないでしょうか。
おそらく過去に「暴れたらいうことを聞いてもらえた」「動かなくなったら大人が折れてくれた」といった「子どもが得をした場面」があったのだと思います。自宅ならまだしも外出先でこれをやられてはたまったものではないですよね。
そうならないように、落ち着いていたり、機嫌がいいときに「怒ったときにどうすればよいか」を話し合っておきましょう。
買ってもらいたいのに買ってもらえないとき、やりたいのにできないときに大声を出すのではなく、話を聞いてもらいたいこと、「我慢できたら買ってあげる」「別の方法でかなえてあげる」などの代替案を提示するから話し合いをしたいことなどを伝えておきましょう。
初めのうちはうまくいかないかもしれませんが、このような経験から子どもは怒りのコントロール力を培っていくのです。
3-3.些細なことでもフィードバックする
また、どんな小さなことでも、怒りを少し抑えることができた、話し合いの内容に沿った行動ができた場合は「約束守ってくれてうれしいな」「怒りたいときに我慢してくれたんだね。ありがとう」というようなことを伝えてあげてください。
感情のコントロールは自分ではなかなかできているのか判断が難しいです。そのため身近な大人が「きちんとできているよ」「その方法で間違っていないよ」とメッセージを送ってあげる必要があるのです。
このときに大切なのは「完璧にできていなくても褒めてあげる」ことです。最初から完全に感情をコントロールできる子なんていません。
「できて当然」「なんでできないの」という考えは捨てて、いつもより1秒我慢できた、100%ではないけど50%ぐらいはできた、その程度でも肯定的な部分を見つけて伝えてあげてください。
自分を認めてくれない人の話を子どもは聞きません。「私はあなたのことを見ているよ」「すごいね、えらいね」ということを子どもに感じてもらうことで初めて子どもは前向きに行動することができるのです。
4.怒りをコントロールして適切な自己主張性を身につけていきましょう

今回はすぐに怒り出してしまう子どもについて、怒ってしまう理由と怒りのコントロールができるようになる時期、そして家庭でもできる感情コントロールの練習法について解説しました。
子どもは感情のコントロール力が未熟であり、些細なことで怒りだしてしまいます。親御さんも余裕があるときには受け流せますが、忙しいとき、イライラしているときにはついつい感情的になってしまいますよね。
あまりに強く怒り出す我が子を見ると「育て方が悪かったのかな」「私がいけないのかな」と悩んでしまうこともあるかと思います。
しかし、子どもは心身ともに成長し、色々な経験を積み重ねていくなかで自然と感情のコントロールができるようになって行きます。
自分自身を責めることなく、「まだまだコントロールできていないんだ」「一緒にコントロールの練習をしよう」と考え、お子様の精神的成長を促してあげてください◎
癇癪、こだわり、学習の遅れ… 子どもの発達に悩んでいませんか?[PR]
お子さまの行動の背景には、その子特有の「感じ方」や「学び方」が隠れているかもしれません。
リタリコジュニアは、科学的根拠に基づいたアプローチで、お子さま一人ひとりの発達をサポートする専門機関です。
★リタリコジュニアの特徴
✓ 学習のつまずきを根本からサポート
「なぜ文字が読みにくいのか」「どうして集中できないのか」を専門家が分析。お子さまが夢中になれる教材や指導法で、「わかった!」という成功体験を積み重ね、学ぶ意欲を引き出します。
✓ 友達との関係を円滑にするスキルを育む
ルールを守ることや、自分の気持ちを上手に伝える練習を、ゲームなどを通して楽しく学びます。勝ち負けのある場面での感情コントロールなど、集団生活で必要なソーシャルスキルが身につきます。
✓ 保護者の不安も一緒に解決
宿題嫌いや登校しぶりなど、尽きない悩みをご相談ください。専門家との面談やペアレントトレーニングを通じて、家庭での効果的な関わり方を一緒に考え、親子のストレスを軽減します。
いつも本当に、お疲れさまです。
その頑張りを、専門家のサポートで「確かな成長」に繋げませんか?
<無料>個別相談・体験授業のお申し込みはこちら>>リタリコジュニア
関連トピックをご紹介!
・親子喧嘩は悪いこと?してはいけない行動と仲直りのコツを解説!
・【小1】子どものアンガーマネジメントのやり方とおすすめの絵本
・反抗期に負けない!親の子育てアンガーマネジメントのやり方





