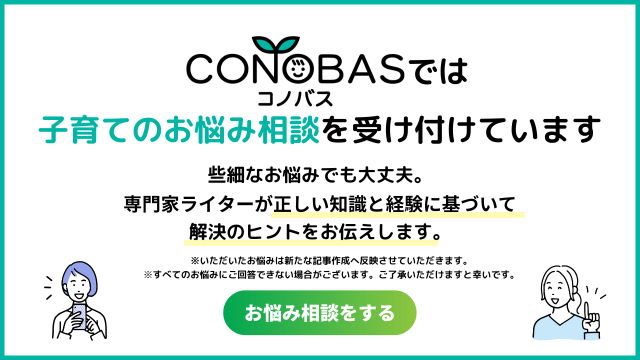5歳|怒ると物を投げる、何度言っても聞かない…理由と中間反抗期の対応ポイントを解説
この記事を書いた人


中川さくら
- 保育士
- 児童指導員
学生時代に障害児福祉を学び、小学校の特別支援教育支援員や療育施設の保育士、学童保育、小学校などで、子どもたちやそのご家族と関わる仕事を約10年ほど経験しました。
今は、保育園に通う1歳の息子がいます。
昔バックパッカーだったので、いつか家族で世界を旅することが夢です。
嫌なことがあるとすぐに物を投げる、何度注意しても聞いてくれない…
そんなお子さんの行動に困った経験はありませんか?
CONOBASの読者の方からも、5歳のお子さんのそんなお悩みをお寄せいただきました。
怒ると物を投げてしまう…
5歳男の子 ママからのご相談
出来なかったことや、嫌な事があった時物を投げてしまいます。物を投げると壊れるし、怪我をすると危ないから投げないでね。と何度も伝えますが、怒りの収まりが効かなくなった時には投げてしまい、どうしたら良いかわかりません。
また、ふざけて妹にわざとぶつかったり押したり軽く叩いたりします。痛いし嫌な気持ちになるからしないでと伝えますが、何度言っても同じです。何度も言い聞かせる以外の方法はないのでしょうか。
5歳頃といえば、2〜3歳の頃とは違い、やってはいけないことを理解できてきたり、言葉での意思疎通もスムーズになってきたりする子も多いでしょう。
だからこそ「何度も言っているのに」「ダメだってわかっているはずなのに」と、悩みや苛立ちを抱えているママやパパは、たくさんいるのではないでしょうか。

「怒ると物を投げる、何度言っても繰り返す。」
そんなお子さんの行動の背景を考え、対応のポイントをご紹介します。疲れた時は少し休憩して、できそうなことから取り入れてみてくださいね。
目次
1.5歳頃の子が怒ったときに物を投げる理由

「怒ったときに物を投げる」「思い通りにならないとすぐに怒る」というのは、5歳頃のお子さんをもつママパパにとって、非常に多い悩みの1つです。
一見困って見えるこれらの行為は、実はお子さんがすくすくと成長しているからこそ現れる行動、そして皆が通る道なのです。
とは言っても、毎日繰り返していては大変ですし、どう接したら良いのか悩んでしまいますよね。まずは、お子さんが物を投げる理由から考えてみましょう。
1-1.自己主張が強まる中間反抗期の時期
5歳前後のお子さんの成長として、以下のような特徴が挙げられます。もちろん成長のスピードには個人差があるので、以下のすべてに当てはまらなくても心配はありません。
- 自立心が育ち、自分でなんでもやりたがる
- 自我がはっきりして、「こうしたい」という自己主張が強くなる
- 自分の気持ちを言葉で伝えられるようになる
- 社会性が育ち、相手の気持ちを考えられるようになる
- 善悪の判断ができるようになり、やっていいことと悪いことの区別がつけられる
そしてこのような成長に伴い、次のような特徴も現れます。
- 言葉や思考力が成長したことで、口答えをしてくる
- 自己主張が強まり、自分の要求が通らないと反抗的になる
- 妹や弟に急にいじわるをする
- 親の話を無視する、反発する
お子さんに当てはまる部分はありませんか?ママやパパからすると、悩みの尽きないこの時期。
これらは「中間反抗期」の特徴で、心身ともに成長している証でもあります。親離れをして自立に向かう第一歩なのです。
1-2.感情のコントロールがうまくできない
5歳頃になると、大人と普通に会話ができるくらい言語力が発達していきます。
その一方で、自分の感情を詳細に伝えることはまだ難しく、うまく言葉にできなかったり、自分の欲望や気持ちを押さえて我慢するといった感情のコントロールができなかったりすることもたくさんあります。
その苛立ちやもどかしさ、「やりたいこと」と「できないこと」のギャップが、物を投げる、癇癪、暴言のような表現方法で出てしまいます。「ダメだとわかっているけど〜したい」といううまく処理できない感情を抱えているのです。
1-3. 衝動的に行動してしまう
お子さんの中には、衝動性が強く、思いついたことを頭で考える前に実行に移してしまう子もいます。
たとえば、ADHDのお子さんや衝動性のあるお子さんは、気に入らないことがあったり、注意散漫になったりすると、すぐに物を投げてしまうことがあります。
また、ASD(自閉スペクトラム症)のお子さんのように、感覚の処理がうまくできないことで物を投げてしまう場合もあります。感覚が人一倍過敏なお子さんには、苦手な環境や刺激があり、それらに対してどう対処したら良いかわからず、物を投げるという行動になってしまうのです。
このような特性のあるお子さんの場合は、その子に合った学びを重ねていくことで、好ましい行動を増やしていくことが可能です。ご家庭だけで悩まずに、発達支援センターなど地域の窓口で相談してみるのがおすすめです。
1-4. ママやパパに甘えたい
自立心が育っているとは言っても、まだまだ甘えたいお年頃。保育園などではお兄さんお姉さんの立場になり、小さい子たちのお世話をしています。役割や当番などもあるかもしれません。
社会性が育ち、お友だちや年下の子たちの気持ちを考えて我慢したり、マナーやルールを守ったり、幼いながらに気をつけて過ごしています。
ママやパパがいない場所でがんばっている分、家では安心して甘えたいからこそ、怒ったりわがままを言ったりしている部分もあるでしょう。反抗的な態度や、妹・弟を叩いたり意地悪したりしてしまうのは、もっと甘えたい気持ちの裏返しかもしれません。
お子さんの物投げや反抗的な態度は、保育園などでも起こっているでしょうか?家庭での困りごとと合わせて、先生に園での様子を聞いてみるのも良いですね。
大人でも、家族に見せる姿と外で振る舞う姿には、少なからず差があるものです。お子さんも「本当の自分」や「本音」を家族の前では表現できるのかもしれません。
2.物を投げてしまう子との接し方のポイント

厳しく叱ったり長々と注意したりすると、5歳頃のお子さんは反発しやすく、親子関係が悪くなってしまうかもしれません。
ここではお子さんへの接し方のポイントを、いくつかのケースに合わせてご紹介します。
お子さんの今の発達段階を理解し、少しポイントを意識してみるだけでママパパの気持ちが届きやすくなりますよ。
2-1. すべてのケースに共通のポイント
まず、どんな状況でも意識しておきたいポイントからご紹介します。
どうして投げたのか、何に怒っているのか、必ずお子さんなりの理由があります。その理由を聞く際に、以下の点を意識してみてください。
- 癇癪などで冷静に話ができない場合は、少し落ち着くまで待つ
- 話を途中でさえぎって親の意見を言わない
- 言い訳や口答えだと感じても最後までしっかり聞く
- うまく言葉にできない時は、「~だったの?」と言語化するのを手伝ってあげる
理由を聞くと言っても「なんで投げたの!?」など問い詰める聞き方では、本当の気持ちが言えなくなってしまったり、怒りが収まらなくなったりする可能性があるので、冷静に穏やかな口調を心がけてみてください。
お子さんの気持ちを最後まで聞いたら、「~したかったね」「〜が嫌だったんだね」と共感すると、理解してもらえたと感じて徐々に落ち着いていきます。
お子さんの希望や主張が叶えられない理由は、お子さんの気持ちを受け止めた後に伝えた方が心に届きやすいでしょう。
2-2.感情のコントロールがうまくできない場合
「物を投げるのがダメなこと」だと理解しているけど、怒ると我慢できなくなってしまう場合は、怒りの感情のコントロールがうまくできないことが考えられます。
5歳で感情をうまくコントロールするのは難しいことですが、以下の接し方を参考にしてみてください。
・怒りが抑えられないときに、親子で一緒に深呼吸をする
これはアンガーマネジメントの一部でもあります。日本アンガーマネジメント協会の小尻先生は深呼吸について、以下のように勧めています。
『風船を用意して、「怒っている気持ちを風船に吹き込むつもりでふくらましてごらん」というのも効果的です。とくに幼児の場合は、息を吸ったり吐いたりする行為を視覚的に体感できるからおすすめです。』
・「自分はどうしたいのか、どうしてほしいのか」怒りの正体を言葉にする練習をする
この方法もアンガーマネジメントの一部です。「何が嫌だったから怒っているのか?」「本当はどうしたかったのか?」など1つずつ怒りの正体を捉え、言葉にしていく方法です。
このような関わりを通して、少しでも感情のコントロールができたときは思いきり褒めてあげてくださいね。「物を投げずに気持ちを表現できた」という成功体験となって積み重なっていきます。
アンガーマネジメントについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
・反抗期に負けない!子育てアンガーマネジメントのやり方
・【小1】子どものアンガーマネジメントのやり方とおすすめの絵本
2-3.甘えたい場合
物を投げる理由が「親に甘えたい」という気持ちの場合、日常から心がけられるポイントもあります。
それは、ママやパパに甘えられる時間を意識的に作ってみるということです。妹や弟に意地悪をしてしまうお子さんにとっても、ママパパを独占できる、愛されていると実感できる時間は、心を満たして発達を促してくれます。
家族や周囲の協力が必要ですが、具体的には、ママと2人きりでお子さんの食べたかった物を食べに行く、パパと2人きりでお子さんの好きなことに没頭する、など、お子さんの普段からの要求を叶えてあげるのがおすすめです。
自立したい、背伸びしたい気持ちと、まだ甘えたい気持ちの狭間で、葛藤したり心が揺れたりしている時期かもしれません。その揺らぎも「今しかない、二度と戻ってこない」のだと、少しだけ意識して過ごせると良いのではないでしょうか。
3.子どもが物を投げたときになるべく避けたい対応

次に、お子さんが物を投げたときになるべく避けた方が良い対応についてもご紹介します。
「これ、今までやっていたな」というものがあっても、これから少しずつ気をつけていけば大丈夫なので、今後の対応の参考にしてみてくださいね。
3-1.子ども自身を否定する
「勝手にしなさい!」と突き放す言い方や「本当にダメな子ね」など、お子さん自身を否定する言葉は使わないようにしましょう。「自分はダメなんだ」と自分の存在に価値を感じられなくなったり、自信を無くしてしまったりするからです。
お子さん自身ではなく「投げることや周囲を傷つける言動や行動」を、やってはいけないと伝えることが必要です。
逆に、普段から小さなことでも良いところを褒めていると、「自分は認められている。受け止めてもらえている。」と自信を持つことができ、だんだんと人を困らせる行動はしないようにしようと、考えられるようになっていきます。
大人も感情的になってしまうことはありますが、「口答えが多い時期」「自分の気持ちを表現できるようになった」と割り切って、お子さんの言葉に反応しすぎない方が良いでしょう。
3-2. 命令形で指示する
自立心が育つ時期なので、理由もわからずに「~しなさい」と命令されると、自分の意思が無視されていると感じて反発しやすくなります。
代わりに、「~しようか」と提案する言い方や「~してくれる?」「してくれたら助かるな」とお願いする言い方で伝えるのがおすすめです。
自分でやりたい、認められたい!という時期だからこそ、お願いすることでやる気を出してくれますよ。一方的な指示と違い、自分でするかしないか判断ができる余地があるのもポイントです。
3-3.無視をする
人を傷つける言葉を使う、叩く、物を壊す、迷惑をかけるといった行動の場合は、無視をしないようにしましょう。
叱っても繰り返す行動に、うんざりしてしまうこともありますよね。ですが、根気強く何度でも「やってはいけないこと」や「どうしてやってはいけないのか」を伝えることが大切です。
それでも繰り返してしまうこともありますが、5歳頃のお子さんの言語力・理解力なら、大人が伝えたいことは理解できます。
注意や正論を素直に受け取れない成長過程なだけで、ママやパパのまっすぐな言葉は、お子さんにきちんと蓄積していきます。
3-3.妹や弟ばかりをかばう
弟や妹がいるお子さんの場合は「お兄ちゃん(お姉ちゃん)なんだから」と言うのはなるべく避けた方が良いでしょう。
大きな怪我に発展しそうな喧嘩や、明らかに上のお子さんが悪い場合は、もちろん注意したり止めたりしなければなりません。
ですが、それ以外の場面でも「お兄ちゃんなんだから優しくしなきゃダメでしょう」と言うなど、普段から親が下の子ばかりをかばっていると、自分は愛されていないと感じたり、余計に意地悪したくなったりしてしまう可能性があります。
「妹(弟)はまだ幼いから、わからないことやできないことも多いよね。いつも我慢してくれているのわかっているよ。」など、上のお子さんが頑張っていることをママやパパはちゃんと知っている、と伝えてあげましょう。
どちらの子も同じように大切で大好きだよと、普段から伝える関わりができたら良いですね。
4.5歳の発達の特徴を知り、自立へのステップに寄り添おう

5歳前後のお子さんの「怒るとすぐに物を投げる」行動について、その理由と対応ポイントを解説しました。
すぐに怒り出したり反抗的になったりするお子さんの姿に「育て方が悪かったのかな…」「うちの子は短気なんだろうか…」と悩んだり、言い聞かせても聞いてくれず、感情的に怒鳴ってしまって自己嫌悪に陥るときもあるかもしれません。
ですが、ママやパパがこれまで懸命にお子さんを育ててきたからこその、立派に成長した姿であり、少しずつ親から離れて自立しようする、次のステップに立つことができたのです。
「こんな時期もいっときのこと」「この子だけじゃない、みんなが通る道」ととらえて、少し前まで「ママじゃなきゃ」と泣いてばかりいた赤ちゃんの誇らしい成長を、見守ってあげたいですね。
・わがまますぎる!言うことを聞かない!5歳児「反抗期」への対応のコツ
・小1反抗期ってなに!?小1の”なまいき”な言動を認知心理学の視点から読み解く
・無視、口答え…5歳・6歳、小学生頃の「中間反抗期」の特徴と対応のコツ