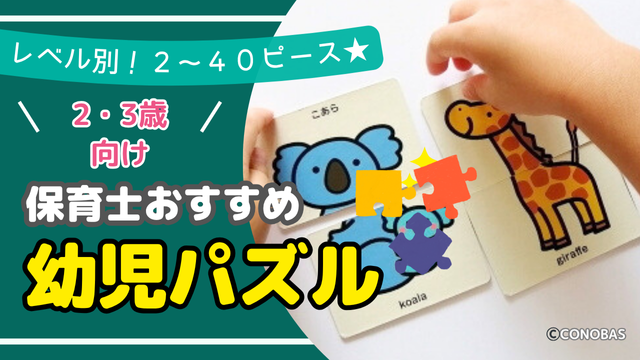
2,3歳児のパズルは何ピース?幼児パズルの選び方とレベル別のおすすめ
この記事を書いた人
梶谷なつみ
- 保育士
保育士として13年間、公立保育園に勤務していました。0歳児から年長まで全ての学年の担任経験があります。
現在は保育の経験をいかしてライターとして活動中。
7歳と4歳の子どもがおり、保育とは違う子育てに試行錯誤の日々です。
保育や育児の経験から、育児の不安や悩みのヒントになるような記事を執筆していきます。
2~3歳頃になると、少しずつ手先が器用になってきて、細かい動きや道具を使う遊びにも興味を示すようになります。
このタイミングで、「そろそろパズルにチャレンジさせてみようかな」と考える親御さんも多いのではないでしょうか。
とはいえ、いざ買ってみようと思っても「どんなパズルを選べばいいのか分からない」「せっかく買ったのに、あまり興味を示してくれない」といった悩みにぶつかることもあるかもしれません。
また、種類が多いので何を基準に選べばよいのか迷いますよね。
パズルは子どもの年齢や発達に合わせて選ぶことがとても大切です。
今回は、元保育士で2児の母でもある筆者が、2,3歳の子どもに向けたパズルの選び方や、遊ぶときの注意点、レベル別のおすすめパズルについて紹介します。
子どもの発達や興味にぴったりなパズルを見つけて、遊びに取り入れてみてくださいね。
目次
1.2,3歳でまだパズルができない…大丈夫?

「うちの子、2,3歳になってもパズルができないな」と心配になる親御さんもいるかもしれません。
しかし、パズルができなくても問題はありません。
同じ2,3歳といっても、手先の器用さや興味関心などは、その子の特性によってさまざまです。今できないからといって焦る必要はありませんので、安心してください。
また、この時期の子どもさんは、パズルが「できない」というより、「やらない」「やりたくない」ということの方が多い印象です。
パズルに興味をもってもらうためには、まず「パズルって楽しいんだ」と感じてもらうことを大切にしましょう。
2.パズルの知育効果を最大化する5つのコツ|選び方から関わり方まで解説

パズルは手先の器用さを伸ばすことはもちろん、集中力や記憶力、空間認知能力といった、さまざまな力が育める遊びです。
ただパズルをやってもらうというのも良いですが、少し工夫してみると知育効果をより高めることができます。
ここでは、パズル遊びで知育効果を高める5つのポイントを見ていきましょう。
①子どもの発達や興味に合わせたパズルを選ぶ
子どもの発達や興味に合わせたパズルを選ぶことは、とても大切です。
「〇歳向け」とかかれた目安を重視するよりも、まずは簡単なものを選ぶようにしましょう。
できた経験を積み重ねていくことで、自信や意欲につながりますよ。
②成長に合わせて少しずつステップアップする
繰り返しやりこんだら、段階的にレベルアップしていきましょう。
新しいパズルを選ぶときは、レベルを上げすぎないように注意しましょう。
もしも子どもが「かんたんだった!」などと言っても、4ピースから20ピースのパズルに急にレベルアップすると、今度は難しすぎて子どもの意欲が低下する可能性があります。
子どもが余裕をもって楽しめるぐらいがベストです。4ピースの次は8ピースなど、子どもに合わせて少しずつステップアップしていくのがおすすめです。
③集中できる環境を整える
パズルをするときは、見えるところに気になるものは置かず、テレビやYouTubeは消して集中できる環境をつくりましょう。
子ども用の机を壁に付け、壁を向いてパズルをおこなうのもおすすめです。
気になるものが見えないことで、パズルに集中でき、集中力が養われます。
④子どもの意欲を尊重し、見守る
子どもがパズルをしていると声をかけたくなりますが、集中しているときはグッと我慢して見守るようにしましょう。
途切れずに集中する経験は、記憶力や観察力を育みます。
少しくらい分からなそうでも、子どもを信じて待ってみましょう。以外と次の瞬間には、「あ、ここだ」と閃いていたりします。
完成したり、一息ついたタイミングで声をかけてみてくださいね。
⑤やれるところまででOK!途中でやめても気にしない
集中力が切れたら、途中でやめても問題ありません。
幼児の集中力が持続する時間は「年齢+1分」とされており、2,3歳は3〜4分程度が一般的です。
2,3歳は、パズルが完成する前に集中力が切れるのはよくあることで、経験を積み重ねていく中で、集中する時間が少しずつ伸びていきます。
最後までやりきることよりも、まずは楽しく取り組むことを大切にしていきたいですね。
3.パズルに興味がない・苦手な子のやる気を引き出す3つのコツ

ここからは、パズル遊びをやりたがらない子どもを「パズルに興味がない子」「パズルに苦手意識がある子」の2つのタイプに分けて対処法をご紹介します。
無理にやらせる必要はありませんが、いろいろなことへ挑戦してもらうことが子ども自身の成長や学びにつながります。
遊びのバリエーションとして楽しめるようになれると良いですね。
3-1.パズルに興味がない子への対処法
パズルに興味がなかったり、ほかに遊びたいものがあったりする子には、やり方を見せながら一緒に楽しめるようにしていきましょう。
対処法①好きなキャラクターや動物の絵柄を選ぶ
好きな絵柄のパズルを用意しておくと、興味をもつきっかけになります。
「〇〇の顔のピースはどこにあるかな?」と、子どもが探しやすいように声をかけていきましょう。
好きなキャラクターを完成させながら、パズルの楽しさを感じられるようになります。
対処法②親が遊び方をみせる
やり方がわからない点も、やりたがらない理由のひとつです。
親が遊び方をみせることで「何やってるんだろう」と興味をもち、やってみたい気持ちになるかもしれません。
まずは親子で会話をしながら、パズルを楽しんでみてくださいね。
対処法③無理にやらせない
パズルを用意しても興味がない場合は、無理にやらなくても問題ありません。興味が出てきたら自然とやるようになるので、ゆっくり待ちましょう。
「待っているだけでパズルをやるようになるのかな?」と不安な方もいますよね。
少しでも興味をもってほしい場合、子どもが見える位置にパズルをおいておくのがおすすめです。
目に見える場所にあることで自然と目にはいり、興味をもちやすくなります。
あと少しで完成するパズルをおいておくと、はめてくれることもあるかもしれません。子どもの気持ち第一で進めていきましょう。
3-2.パズルに苦手意識がある子への対処法
パズルのピースがうまくはまらずに諦めてしまう子には、達成感をたくさん感じられるようにしていきましょう。
対処法①パズルを簡単なものにする
パズルに苦手意識がある理由は、発達にあっていないパズルに挑戦しているからかもしれません。
「少し簡単かな?」と思うくらいのパズルから始めていき、完成する楽しさを感じられることで、次への意欲に繋がります。
簡単なパズルを十分楽しんだら、少しずつステップアップしてみてくださいね。
対処法②さり気なくヒントを教える
「自分でやりたい。でも難しくてできない」子には、さり気なくヒントを教えるのがおすすめです。
筆者はよく「誰かの耳かな」「まだ耳が完成していない子いるかな〜」と、ひとり言のように呟いてヒントをだしています。
つぶやきを聞いて子どもが自分ではめるところを見つけるので、達成感に繋がります。
困っているとすぐにヒントを伝えたくなりますが、伝え方に気をつけて、子どもが自分でできるようにサポートしていきましょう。
対処法③完成したときはたくさん褒める
パズルが完成したときは「全部自分でできたね」「最後まで完成したね」と、たくさん褒めて達成感を感じられるようにしましょう。
できた経験をたくさんして達成感を感じることで、苦手意識も少しずつなくなってきますよ。
4.2,3歳におすすめパズル2~10ピース:レベル★

ここからは2,3歳におすすめのパズルをレベル別にご紹介していきます。
2,3歳でパズルの経験がない場合、パズルのやり方を知り、パズルに慣れていくことを重視して選びましょう。
持ちやすくてすぐに完成するパズルがおすすめです。
4-1.おすすめパズル①エド・インター木製パズル 木のパズル なかよしどうぶつ
パズルが初めての子は「型はめパズル」から始めてみましょう。
型はめパズルでは、パズルをするのに大切な図形認知能力が養われます。
ひとつひとつ型枠があるため、パズルが初めての子でもスムーズに完成させることができます。木製でつまみが付いているので、小さな子どもも扱いやすいパズルです。
★使用した感想
(遊んだ年齢:1歳10ヶ月〜)
筆者が自分の子どもに初めて購入したパズルです。可愛いイラストで動物たちが描かれていて、子どもも興味津々でした。
型枠に余裕があるので、パズルが初めてでもはめ込みやすいです。
動物を動かして遊んだり、「おうちかえろうね」と言いながらパズルを完成させたりして、繰り返し楽しんでいました!
保育園でも1,2歳に大人気のパズルです!
4-2.おすすめパズル②MUJOY モンテッソーリ 木製パズル
3〜6ピースの木製パズルが6種類入った商品です。ピースの数が少なめなので、パズルの経験が浅い子にぴったりです。
カラフルな色合いなので、遊びながら子どもの脳の発達を促し、色彩感覚が育ちますよ。
★使用した感想
(遊んだ年齢:2歳〜)
木製なので、子どもの小さな手でも持ちやすく、少し雑に扱っても壊れにくそうです。
初めてやるときは少し苦戦していましたが、すぐにやり方を覚えてできるようになりました。
ピースが少ないため、子どもも自分で完成できて嬉しそうです。毎日、好きな動物を選んで何度も遊んでいました。
★注意ポイント
少し小さいパーツもあるため、保護者が見守りながらおこないましょう。
4-3.おすすめパズル③サンスター文具 それいけ!アンパンマン はじめてのジグソーパズル Step1
ジクソーパズルは、パズルを上からはめ込むので、やり方に慣れるまでは少し難しいですよね。
このパズルは2〜4ピースと少ないので、ジクソーパズルに慣れるのに最適です。普通のジグソーパズルより大きめで、2,3歳の子どもの手でも扱いやすいようになっています。
アンパンマンは子どもたちが大好きなキャラクターなので、楽しみながら遊べますよ。
★使用した感想
(遊んだ年齢:2歳〜)
アンパンマンが大好きな子どものために、初めてのジクソーパズルとして購入しました。
普通のパズルとははめ込み方が違うので最初は難しいですが、親が見本を見せながら何度か挑戦してできるようになりました!
2ピースのパズルは、ひとつはめたら完成するので、子どものやる気がアップしてとても良かったです!
5.2,3歳におすすめパズル10~20ピース:レベル★★

2〜10ピースのパズルがスムーズにでき、集中して取り組めるようになってきたら、少しずつレベルをあげていきましょう。
5-1.おすすめパズル①くもん出版 くもんのジグソーパズル STEP2 なかよし どうぶつファミリー
くもんのジグソーパズルは、ジグソーパズルで本格的に遊びたい子にぴったりです。
STEP2では、9ピース・12ピース・16ピース・20ピースの4セットのパズルが入っており、子どもに合わせて少しずつレベルをあげていくことができます。
ジグソーパズルは、集中力や思考力が養われるためとてもおすすめですよ。
★使用した感想
(遊んだ年齢:2歳6ヶ月〜)
アンパンマンのジグソーパズルが1人でスムーズにできるようになったので購入しました。
9ピースは、子どもが諦めずに集中してできるレベルで、ちょうどよかったです。パズルで遊ぶようになってから、机で集中して遊ぶ時間が増えました。
9ピースからゆっくり進めることができたので、3歳半には16・20ピースも1人でできるようになりました。
5-2.おすすめパズル②くもん出版 NEW さんかくたんぐらむ
たんぐらむとは、いろいろな形のピースを組み合わせながら図形をつくるパズルです。
普通のパズルと違い、正解が何通りもあり、自分で組み合わせを考えて完成させていくのが特徴です。
今回紹介する「NEW さんかくたんぐらむ」のピースは、さんかく1種類で、通常の「NEWたんぐらむ」より優しいパズルになっています。
タングラムをすることで空間認知能力はもちろん、創造力や思考力、集中力が養われます。
★使用した感想
(遊んだ年齢:2歳8ヶ月〜)
初めてのたんぐらむでしたが、1ピースから始められて子どもも「できた!」と嬉しそうでした!
段階的にレベルアップができるので「難しい」と感じず、気づいたら難しい問題もできるようになっていました。
現在は4歳なり「NEWたんぐらむ」で遊ぶようになりましたが、事前に「NEWさんかくたんぐらむ」をやっていたことで、試行錯誤しながら諦めずに遊んでいます!
5-3.おすすめパズル③ポエック社 【キューブパズル】
キューブパズルは立方体6面にイラストが描かれたパズルです。
6面をみながらパズルを完成させていくので、空間認知能力が向上します。
エポック社のキューブパズルは、面ごとにレベルがあり、初めてキューブブロックをする子でも遊びやすいのが特徴です。
★使用した感想
(遊んだ年齢:3歳0ヶ月〜)
キューブパズルは難しいイメージがありましたが、STEP1とSTEP2は形や数字をそろえればいいので、3歳になったばかりの子どもでもできました!
慣れてくると「次はここの面を完成させよう!」と何度も繰り返し楽しんでいます。
他のパズルと違い、いろいろな面をみなくてはいけないので、判断力も必要なパズルだと感じました。
6.2,3歳におすすめパズル20~40ピース:レベル★★★

20〜40ピースになってくると難しいパズルが増えてきます。
パズルは、板パズル、ジグソーパズル、図形パズルといった種類があるため、今までやってきた中で、子どもが一番楽しめているものから選んでみましょう!
6-1.おすすめパズル①エポック社 【アポロのステップパノラマパズル】 ジュラシック・ワールド/新たなる支配者
18・24・32ピースの3種類がセットになった板パズルです。
1種類ずつ遊ぶことはもちろん、3種類をつなげて大きなパズルのように遊ぶことができます。
まずは18ピースから始めて、32ピースまでできるようになったら、つなげてやってみるのも面白いですよ。
全てつなげたときのピース数は74ピースもあるため、何度も長く遊ぶことができます。
★使用した感想
(遊んだ年齢:3歳2ヶ月〜)
恐竜が大好きなので出した瞬間から目を輝かせて遊んでいました!
18ピースは3歳の子、24・32ピースは姉と母でつくり、1つにつなげるととても嬉しそうでした。他のパズルではできない遊び方で、親子で遊べてとても良かったです!
大好きな恐竜なのですぐに32ピースまでできるようになり、1人で集中して完成させていました。
6-2.おすすめパズル②・Bajoy 4in1 教育玩具 木製パズル テトリス
長方形の木枠の中にピースを組み合わせてはめこんでいくパズルです。
ピースをはめる位置に正解はありませんが、適当にいれると上手くはまらないことがあり、思考力や空間認知能力が必要なパズルになっています。
平面だけでなく、立体図形も作ることができ、子どものアイデア次第で遊び方は無限大です。
★使用した感想
(遊んだ年齢:3歳6ヶ月〜)
可愛い動物たちがカラフルに描かれていて、見るだけで楽しいパズルです。
最初は木枠の中にピースを自由に入れて「あれ?なんではいらないの?」と不思議そうにしていましたが、ピースの向きや形を変えて「この形ならここにはいる!」と気づいたときの表情はとても嬉しそうでした。
積み木のように積み重ねてみたり、立体的なものを作ろうとしたり、遊び方がどんどん広がっています。
木製パズルテトリスのおかげで、子どもが自分で考える力がとても伸びました。
6-3.おすすめパズル③学研 はっけんパズル ジグソーパズル 3枚入り どうぶつ
15・20・35ピースの3種類のジグソーパズルのセットになっています。
はっけんぱずるは、図鑑のように楽しめるパズルになっているのが特徴です。
パズルを完成させたあとにピースをめくると、動物に関することを知ることができ、パズルだけでなく、動物の知識も身につきます。
リアルなイラストで少し難しいため、いろいろなパズルを経験した子におすすめです。
★使用した感想
(遊んだ年齢:3歳8ヶ月〜)
リアルなイラストで背景が似たようなものが多く、可愛い絵柄のジグソーパズルより難しいようで、最初の頃は親が一緒に手伝いながら完成させていました。
4歳1ヶ月の今は20ピースまでは自分でできるようになり、35ピースもまずは自分でやろうと頑張っています!
パズルを完成させたあとにピースをめくると、動物に関することが書いてあり、親子で図鑑のように楽しみました!4歳以降も長い期間遊べるパズルです。
7.子どもの発達に合ったパズルで「できた!」の経験を増やそう
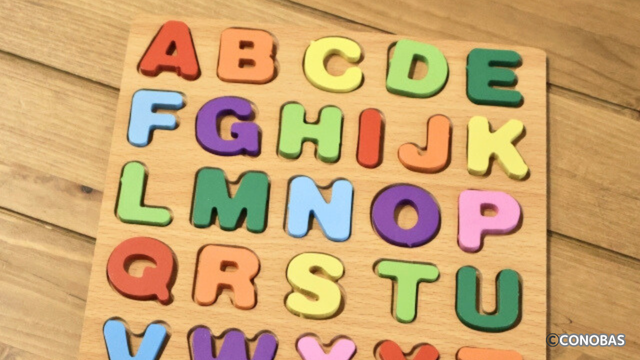
2,3歳は、パズルに興味がなかったり、うまくできなかったりするのが当然の時期です。
子どもの成長や興味にあったパズルを選ぶことで、「楽しそう!」「自分でできた」と意欲や自信に繋がります。
子どもの姿に合わせたパズルを選択して、ぜひ親子で楽しんでくださいね。
利用者No.1「トイサブ!」積み木、ごっこ遊び、音が出るおもちゃ、パズル…多様な玩具が選べる[PR]
おもちゃを買うのも選ぶのも、子どもがいるご家庭ならではの楽しみですね。
一方で、どんなおもちゃがいいか分からないといったお悩みや、高くて何個も買ってあげられないといった声も聞きます。
色々なおもちゃで遊ばせてあげられればいいな…と思ったら、トイサブ!を活用してみてはいかがでしょう?
トイサブ!は、国内・海外メーカー約250社から選定した1800種類以上の玩具の中から、一人ひとりに合った知育玩具をお届けするレンタルサービスです。
★トイサブ!の魅力
- 2か月ごとに、定価合計17,000円以上の知育玩具を5~6点お届け
- おもちゃ評価データ100万件以上を活用し、個別プランを作成
- 気に入った玩具は、レンタル継続やお得な価格での買取も可能
- 遊び方や子どもが興味を持たない場合など、メール・チャットで相談できる
- 破損しても原則弁償不要で、安心して自由に遊ばせられる
- 返却期限なし、延滞料金なしなど、子育て世帯の声をもとに柔軟な仕組みを採用
「買ったおもちゃもすぐに飽きてしまう」
「おもちゃが部屋に溢れている…」
「買うと高価な知育玩具を購入前に試してみたい」
そんな親御さんにもおすすめです◎
▶▶詳しくはトイサブ!の公式サイトをチェックしてみてください!
関連トピックをご紹介!
・1・2・3歳おすすめシールブック!選び方&遊びの工夫も紹介
・【0~3歳】手遊び・リズム遊びで運動能力を育もう!
・保育士おすすめ「しかけ絵本」ではじめる幼児教育!│1歳2歳3歳向け






