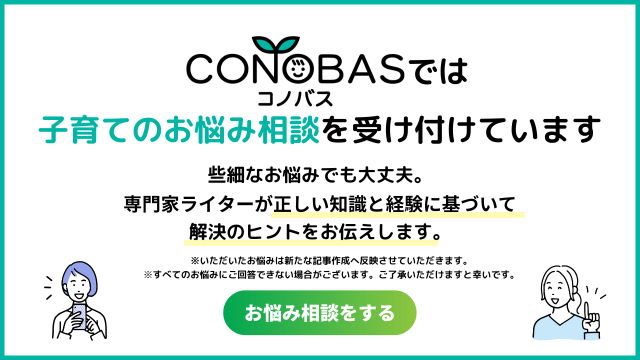5・6歳|不安が強い・心配しすぎる子【関わり方のポイントを解説】
この記事を書いた人


中川さくら
- 保育士
- 児童指導員
学生時代に障害児福祉を学び、小学校の特別支援教育支援員や療育施設の保育士、学童保育、小学校などで、子どもたちやそのご家族と関わる仕事を約10年ほど経験しました。
今は、保育園に通う1歳の息子がいます。
昔バックパッカーだったので、いつか家族で世界を旅することが夢です。
5歳のお子さんのママからCONOBASへ「子どもの不安が強すぎたり、心配しすぎたりして困っている」というお悩みをお寄せいただきました。
「人の足を踏んだかもしれない」と不安になりすぎてしまう…
5歳女の子 ママからのご相談
『最近幼稚園にお迎えに行くと「誰かの足を踏んだかもしれないし、踏んでないかもしれない、どうしよう」と質問されます。「踏んでしまったら相手が痛いって言うんじゃないかな?そういう反応があったら謝ればいいよ。」と伝えました。
また、買い物へ行く途中ですれ違った人がいると「今ぶつかったか、ぶつかってないか分からない」と言ったり、近くに人がいないのに人を見つけると「足踏んだかな?」と絶対ありえない状況でも聞いたりしてきます。
人を見つける度に繰り返されて、その度に「踏んでないよ、あたってないよ」と答えているのですが、質問回数が多すぎてイライラしてしまいます。
さらに同じ頃から「自分いらない、自分嫌い」と言い始めて自分を叩いたりもします。
幼稚園の先生からも「人の足を踏んだか踏んでないかで泣いちゃった事がある」と聞いたので、きっかけがあったのかなと思うのですが、どのように対応したら良いのか悩んでます。』

今回は、不安が強い・心配しすぎるお子さんについて、その背景にある要因や対応方法をご紹介します。具体的な対応例もご紹介しますので、お子さんの不安に寄り添う関わりを一緒に考えていきましょう。
目次
1.不安が強い子の特徴と要因

不安を感じることは、大人にとっても子どもにとっても自然なことであり、危険から身を守るために必要な感情でもあります。
しかし、日常生活に支障をきたしてしまうほど、強い不安を抱きやすい人もいます。特に子どもの場合は、その不安を言葉にできず溜め込んでしまったり、心身の不調となって表れてしまったりすることがあります。
まずは、その特徴と背景にある要因について考えていきましょう。
1-1. 過去の経験が影響している
過去に経験したことが原因で、不安が強くなってしまう可能性があります。
国立成育医療研究センターの「子どものトラウマ診療ガイドライン」には、
「著しい恐怖や不安を感じた子どもは、トラウマの原因となったできごとが起こらないような状況においても、過剰に警戒的となり、周囲の人の些細なしぐさや行為に敏感に反応するようになります。」
と書かれています。
たとえば、相談者様のお子さんのように「人の足を踏んでしまったかもしれない」という不安は、過去に人の足を踏んでしまったことで、相手にひどく怒られてしまったり、悲しい思いや怖い思いをしたりしてしまった可能性があります。
1-2.持っている気質や性格
お子さんの中には、もともと繊細な気質を持っている子もいます。
・人一倍感受性が高い
・その場の空気や人間関係に敏感
・環境の変化が苦手
・失敗や怒られることが怖い
上記のような繊細な気質があると、不安をより強く感じやすい傾向があります。
その場合、以下のような行動や特徴として現れることがあります。
・他人が怒られているのを見ると辛くなる
・「自分も怒られるのではないか」と想像して、幼稚園や学校に行きがらない
・「失敗してしまったらどうしよう」という不安から完璧主義になる
また、このような繊細なお子さんは、周囲に気持ちを打ち明けることができず抱え込みやすい傾向もあります。
1-3. 相手の気持ちを想像するのが苦手
お子さんの中には、相手の立場に立って気持ちを想像したり、その場の状況を読み取ったりすることが苦手な子もいます。
特に、ASDの特性のあるお子さんやグレーゾーンのお子さんには、そのような傾向があり、個人差はありますが以下のような特徴があることが多いです。
・わかりにくい状況や見通しの立たない状況、イレギュラーな事態が苦手
・人から言われたこと言葉を本意とは違うように受け取りやすい
・柔軟に考えることが苦手
このように、いつもと違う状況になると過度に心配になってしまったり、感じ方や認識の仕方に偏りがあることで、相手の言動を本意とは違う意味に捉えてしまったりし、不安に陥りやすい場合があります。
1-4. 不安症の可能性
子どもは大人よりも感情をコントロールする脳の「前頭前野」が未熟なため、より不安を感じやすい傾向があります。
しかし、その不安が心身に悪影響を及ぼすほど過度な場合は、不安症(不安障害)の可能性があります。
MDSマニュアルの「小児と青年における不安症の概要」によると、
「不安症(不安障害とも呼ばれます)は、実際の状況と釣り合わない強い恐怖、心配、脅威によって日常生活に大きな支障をきたすことを特徴とする病気です。」
と記載されています。
幼いうちは特に、不安な気持ちをうまく伝えることも難しいため、「お腹や頭が痛くなる・眠れなくなる」といった身体症状として出ることがあります。
不安症の場合は医師または専門家による診断、行動療法、症状によっては薬による治療が必要となるため、早期に受診や相談をすることが大切です。
2.不安が強い子への関わり方ポイント

2-1.不安な気持ちを否定しない
お子さんの不安な気持ちの要因が何であっても、共通して大切なことは「不安な気持ちを頭から否定しないこと」です。否定されると子どもは余計に不安になってしまいます。
たとえば「気にしすぎだよ」などの言葉は、「気にしなくて大丈夫だよ」というつもりであっても、不安で困っているお子さんにとっては責められているように感じてしまうかもしれません。
・不安なんだね、悲しかったね。ネガティブな気持ちのあなたもそのままで大丈夫だよ
・不安なことがあっても、ママやパパはあなたの味方だよ
・ママたちも不安になることがたくさんあるよ
など、お子さんの気持ちをそのまま受け止めたうえで、安心させてあげるような言葉かけがおすすめです。
2-2.背景にある本当の気持ちに寄り添う
お子さんが不安な気持ちになる時には、その背景に本当の気持ちが隠れていることがあります。
目の前の姿だけではなく「本当はどんな気持ちが隠れているのかな」と、その原因や背景に寄り添ってあげるのも良いでしょう。
大人からすると、子どもの話は支離滅裂に思えたり、本当なのかわからないような話だったりするかもしれません。それでも子どもの話にじっくり耳を傾けたり、他愛のない話を一緒にしたり、そんな関わりの中から、子どもの本当の気持ちが見えてくることがあります。
「本当に伝えたいことがうまく表現できていないのでは」と捉えてみると、大人の心の持ち方も変わるかもしれません。
2-3.思考の癖を変えていく
不安が強いお子さんの中には、人の言葉や状況を否定的に捉えやすい、というような思考の癖があることがあります。
不安な場面があった時に、お子さんがさまざまな角度から考えられるよう、幼いうちから一緒に練習していくと良いでしょう。
・「例えばこうかもしれないし、こっちかもしれない」と普段からいろんな可能性を考える
・相手が何を考えているかは、どれほど考えても分からない(考えすぎない)
2-4.専門機関へ相談する
不安障の心配がある場合は、家族だけで抱え込まずに身近な相談機関に頼りましょう。
専門的なアプローチは、お子さんの不安を減らす助けになってくれるでしょう。
住んでいる地域の市区町村役場や保健センター、精神保健福祉センターなどに問い合わせると、専門の機関へつないでくれます。

そのほかにも保育園の先生と共有したり、子どもの精神面を診察できる医療機関に行ったり、周囲の大人と連携してお子さんの心の健康を支えられたら良いですね。
3.【場面別】不安が強い子への対応例

ここでは、3つの場面の例を挙げて具体的な対応方法をご紹介します。
3-1. ケース①人が近くにいない状況でも「人の足を踏んだかもしれない」と不安になる
今回の相談者様のお子さんのように、現実的には「ありえない状況」でも「〇〇してしまったかもしれない」と繰り返し不安になってしまうお子さんへの対応方法からご紹介します。
「もし踏んでしまっても、謝れば大丈夫だよ」と伝えても不安が消えないという状況なので、対応の仕方を変える方が良いかもしれません。
①共感し、切り替える
「そっか、踏んでいないかすごく心配なんだね」と不安な気持ちを受け止めてあげましょう。しかし「踏んだかな?」と聞かれるたびに「大丈夫、踏んでないよ」と答えると、お子さんが不安を「一時的に和らげるため」に、何度も確認する行為が強くなってしまう可能性があります。
「ママは、〇〇ちゃんが踏んでいないって知っているよ。だから、この話は終わりにして一緒にこれ(別の遊び)をしよう。」など、お子さんの不安への確認行為には何度も応じず、切り替える練習をしてみましょう。「不安な気持ちを抱えたままでも、次の行動に移る」という練習になり、「不安はあっても大丈夫」「不安に負けない心」を育むことにつながっていきます。
②スイッチを押すイメージを作る
切り替え方の練習として、自分の中にある「スイッチ」を押すようなイメージを作ります。
「不安になっても大丈夫。〇〇ちゃんには『切り替えスイッチ』があるよ!スイッチを押したら『不安なことはおしまい!楽しい遊びをする!』って決めよう。」という感じで、はじめは難しいかもしれませんが繰り返していきましょう。
③「できたこと」を褒める
「踏んだかもって不安になりそうだったけど、この遊びに集中できたね!スイッチ押せたよ!」「今日は『足踏んだかも』って言うのが昨日より1回少なかった!〇〇ちゃんの心が強くなっているんだよ」と、頑張ったこと、できたことを言葉にしてあげましょう。
不安が消えたかどうかよりも、不安がある中で別の行動ができたこと、乗り越えられたことがお子さんの自信となっていきます。
3-2. ケース②怒られるのが不安で保育園に行けない
2つめは、「怒られるのが不安」「人が怒られているのも苦手」という理由から、保育園や幼稚園への行きしぶりのある繊細なお子さんへの対応方法のご紹介です。
「不安な気持ちを軽くする」ことと「保育園への安心感」がもてるようアプローチしてみましょう。
①「共感」と「言語化」
まだ言葉でうまく表現できないので、「先生の大きな声を聞くとすごくドキドキして、怖いんだね」など、代弁してあげましょう。「ママはつらい気持ちをわかってくれた!」という安心感で不安が和らぐことがあります。
また「誰かが怒られているのを見ると、つらい気持ちになるんだね。そう感じてもいいんだよ。」と、お子さんの繊細さもそのまま肯定することで、「自分って変なのかな…」という二次的な不安を和らげます。
②怒っているのはその子を否定しているわけではない
「先生がもし怒っても、その子や〇〇ちゃんの良いところもたくさん見てくれているよ。大きな声を出したとしても、危ないことを教えてくれているだけだから大丈夫なんだよ」と、先生の行動の意味を伝えます。
③先生と連携して「避難場所」を作る
保育園の先生に、お子さんの特性を踏まえて対応してもらえるよう相談してみるのはいかがでしょうか。
「娘は先生が他の子を叱る姿を見ただけで、不安でいっぱいになってしまう」という気質を伝え、「もし不安が強くなりすぎた時、静かに落ち着ける場所(職員室の隅、本のコーナーなど)を使わせてもらうことはできますか?」と相談してみる方法もあります。
「不安な時に一時的に離れる」という選択肢があるだけで、お子さんは大きな安心感を得られます。
無理に登園させることよりも「不安な気持ちになっても大丈夫」「不安になったら安心できる場所がある」と感じることが、登園しぶりを乗り越える力になるでしょう。
3-3. ケース③自分のことを叩く、ダメな存在、嫌われているなどと自己否定する
3つめは、自分のことを叩いたり、ダメな存在だと自己否定したりするケースへの対応です。
幼稚園などの集団生活の中で、人との関係がうまくいかず孤立を感じて「みんな私を嫌っている」と思ったり、遊びや役割の中で失敗すると「もうやだ!」「ぼくってダメなんだ」と自分を叩いたり、感情の葛藤が「自己否定」という形で現れることがあります。
自己否定が強い時期には、「大好きだよ」などの言葉に加えて、自己肯定感や安心感を育むアプローチが良いでしょう。
①抱きしめる等、体全体での愛情表現を習慣にする
自己否定や「嫌われている」という不安は、心の奥に「基本的な安心感」が不足している可能性があります。毎日5分でも良いので、抱きしめたり背中をさすったり、肌と肌で安心を感じられるスキンシップを続けてみてください。
②失敗をポジティブに変換する練習をする
自分を叩く行為は、「失敗すると自分には価値がない」と感じているからかもしれません。お子さんが何かを失敗した時に「次はこうしたらいいよって、失敗の先生が教えてくれたんだね」と、失敗を「先生」としてポジティブに変換してみましょう。
逆に、何かがうまくできた時にも「上手だね」と結果を褒めるのではなく、「どうやったらできるか一生懸命考えているの、ママ見てたよ」など、努力や粘り強さを褒めるのもおすすめです。
「結果ではなく過程に価値がある」ということが、徐々に伝わっていくと良いですね。
③「叩く行動」を止めて「気持ち」に共感する
自分を傷つける行為は、本人にとっても家族にとっても悲しいものです。しかし、「叩いちゃダメ」「自分はダメなんて言わないで」など、今のお子さんの姿を否定しても解決には向かいません。
自分のことを叩いていたら、その手を優しく止めて、落ち着くように抱きしめたり手を握ったり、「〜〜が悲しかったんだね」など受け止めてあげましょう。
もちろん「愛しているよ。宝物だよ。」という言葉は、お子さんにとっては何にも代えがたい心の安心材料になりますので、惜しみなく伝えてあげてくださいね。
4.不安があっても大丈夫!と思える心を育もう

今回の記事では、不安が強い・心配しすぎてしまうお子さんについて、その要因と具体的な対応例についてご紹介しました。
5歳頃のお子さんは、まだ状況を客観的に理解することが難しい段階でもあるため、必要以上に不安になってしまうこともあります。
関わりには根気が必要ですが、その積み重ねが、お子さんの心にある不安を少しずつ溶かしていく力になっていくでしょう。
お子さんの不安を和らげ、また不安があっても乗り越えていけるよう、周囲の協力や専門家からのサポートにも頼ってみてくださいね。
偏食・野菜嫌いさんにもおすすめ!無添加・手作り冷凍幼児食「mogumo(モグモ)」
[PR]
当たり前のように思われがちですが、毎日食事を作るのは、とても大変ですよね。
「今日はゆっくりしたい」
「手を抜きたくないけれど、時間がない」
「市販の総菜や幼児食を取り入れるのは抵抗がある」
「家事や育児でぐったり…」
「何を作ればいいだろう?料理は苦手だなぁ」
悩みはそれぞれですが、毎日の食事作りのお供に、冷凍宅配幼児食「mogumo(モグモ)」を活用してみるのもおすすめです。
モグモの幼児食は、全て手作りの無添加。管理栄養士が監修しているため、栄養バランスはもちろん、美味しさにもこだわっています。
mogumo(モグモ)の特徴
✓冷凍だから、レンジで温めるだけで簡単に食べられる
✓かわいいパッケージで、子どもの興味もそそられる
✓何食、どれくらいの期間利用するかは、家庭に合わせて自由に選べる
✓予定に合わせて、お届けスキップやプラン変更が可能
独自の冷凍技術で、長期間保存ができるので、冷蔵庫にストックがあるだけで安心です。
幼児食ってどうすればいいの?とお悩みの方には、管理栄養士の無料相談サポートもあります。
利用できるサービスは、上手に活用しながら、無理せず親子で楽しい時間が過ごせると良いですね。
詳細はこちらから>>冷凍宅配幼児食「mogumo(モグモ)」
・育て方で変わる!ひといちばい敏感で繊細な子ども「HSC」の特徴といいところを伸ばす言葉がけをご紹介
・3.4.5歳「他人が怒られているのを怖がる子」〜理由と寄り添い方を解説
参考文献
・子どものトラウマ診療ガイドライン/国立成育医療研究センター
・小児と青年における不安症の概要/MSDマニュアル