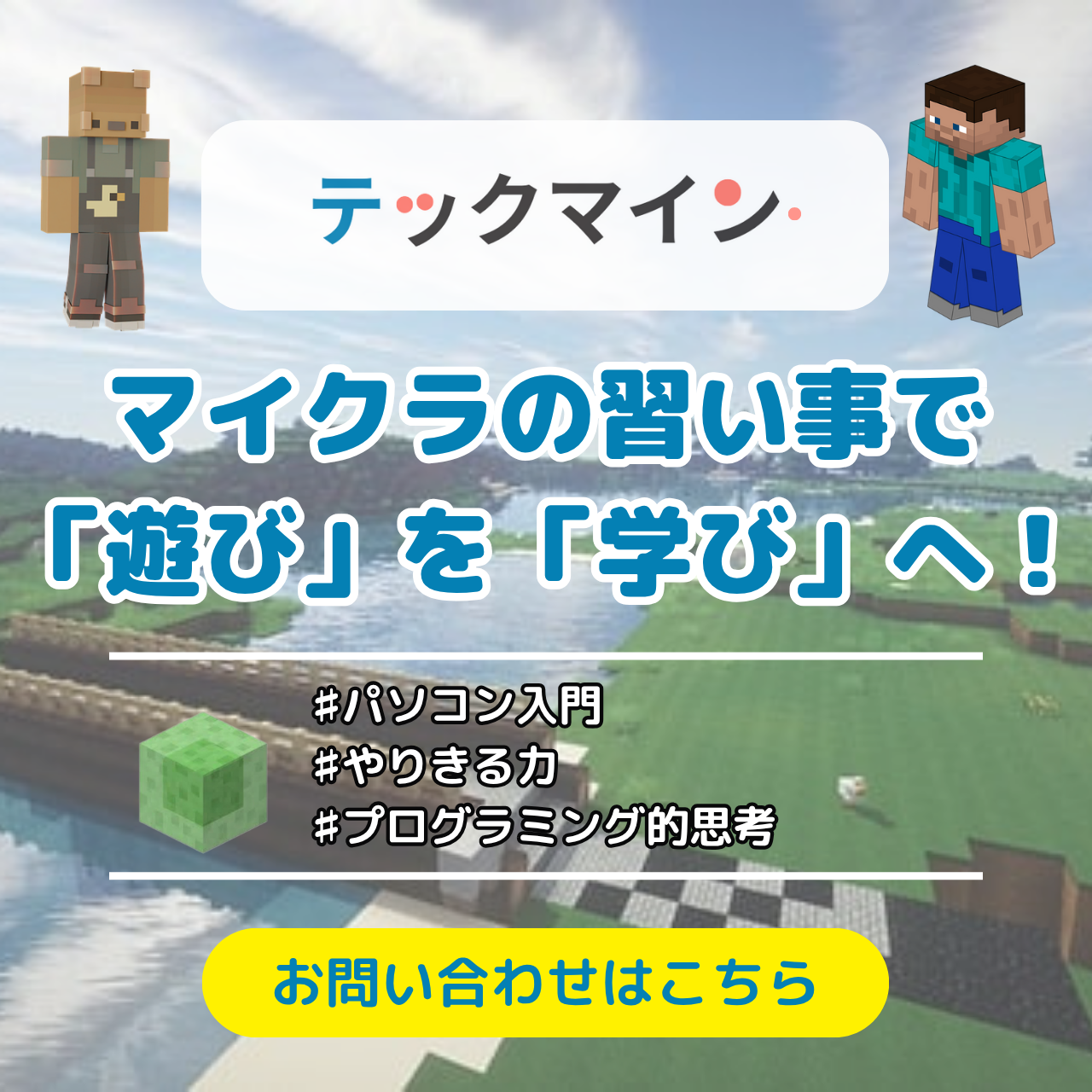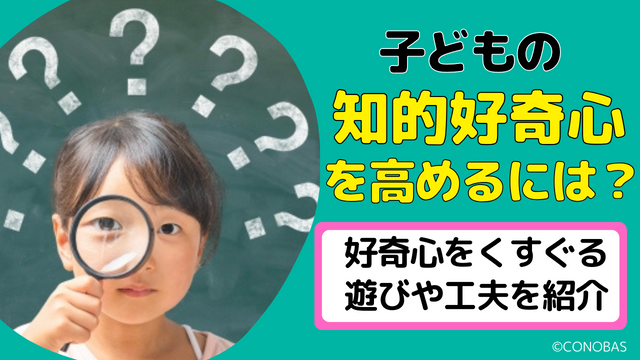
子どもの知的好奇心を高めるには?好奇心をくすぐる遊びや工夫を紹介
この記事を書いた人
多村美穂
- 保育士
元保育士のWEBライターです。
保育園勤務時は、主に0~2歳児を担当していました。
現在は、大きくなってきた子どもを見守りながら、育児・教育を中心に様々なジャンルの記事を執筆しています。
保育園にて勤務した経験や、自らの子育てを通して得た知識を、分かりやすくお伝えしていきたいです!
「新しいことをどんどん知りたい」「なんでこうなるのか理由を知りたい」などのように、「知る」ことに対してワクワクする気持ちが知的好奇心です。
「子どもの好奇心を伸ばしてあげたいけど、どんなことをすればいいか分からない」 「子どもの知的好奇心を高める遊びが知りたい」
知的好奇心が大切だと聞いたことはあるけれど、子どもの知的好奇心を伸ばす具体的な方法が分からず困ってしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、知的好奇心を刺激するための「室内遊び」「外遊び」「部屋作り」に関する具体的なアイデアや、親ができる工夫を紹介します。
3〜6歳頃は知的好奇心を伸ばすのに最適な時期です。この大切な時期に子どもの知的好奇心を刺激して、将来に役立つ力を育んでいきましょう。
目次
1.知的好奇心を高める4つのメリット

「これはなんだろう」と興味をもって物事に没頭していく力である知的好奇心。
子どもの知的好奇心を伸ばすことには、以下のメリットがあります。
1-1. 学習意欲が向上する
知的好奇心が旺盛な子どもは、学習意欲も高くなると言われています。なぜなら、知的好奇心が高くなると、「なんで?」「どうして?」という気持ちが高まり、「知る」ということに喜びを覚えるようになるからです。
知らないことを自ら学び、分からない問題を調べながら解決していく勉強は、押しつけられた勉強以上に、自分の糧になっていくでしょう。
1-2.学びのサイクルが作られる
知的好奇心が高いと、「知りたい」「調べたい」という気持ちが生じます。すると、子どもは知りたいことが分かるまでとことん調べ、疑問や問題を解決することもあるでしょう。
「疑問を解消できた」という達成感は、次の「知りたい」という意欲を高め、子どもは自ら積極的に情報を集めるようになっていきます。
積極的に行動を起こすことで、新たな発見や疑問と出会い、さらなる好奇心を育てていくという好循環を作ることにつながりますよ。
1-3.集中して物事に取り組めるようになる
知的好奇心が高い子どもは、「自分が納得するまで調べたい」気持ちが強いため、興味の対象に没頭する傾向があります。
小さな子どもが山手線沿線の駅名をすべて覚えていたり、大人顔負けの恐竜の知識をもっていたりする場面を見たことはありませんか?
これは、知的好奇心が働き、物事に集中した結果でしょう。
何かに「没頭する」体験は、成長していく中で訪れるトラブルや困難にも集中して取り組む力を育ててくれますよ。
1-4.ストレスに強くなる
知的好奇心が高い子どもは新しい環境に飛び込んだときにも、「いろいろなことが知りたい」「新しいことに出会える」という気持ちが強いため、気後れしにくいという傾向があります。
入園・入学や新しい習い事など、慣れないことが多い場合でも、ストレスにつぶされることなくその状況を楽しんでいけるでしょう。
また、トラブルがあった場合でも「どうしてこうなったんだろう」と問題を発見・解決していこうとする姿勢が見られます。
そのため、トラブルに直面した場合でもストレスに負けることなく立ち向かおうとするでしょう。
2.【室内】知的好奇心を高める遊び

ここからは、子どもの知的好奇心を高める遊びを紹介します。
まずは、室内遊びから見ていきましょう。
2-1.図鑑、辞書・地図を一緒に読む
「なんで?」「どうして?」を引き出し、深めてくれる図鑑・辞書・地図は、知的好奇心を高めるための必須アイテムと言っても過言ではありません。
しかし、ただ置いてあるだけでは子どもの好奇心を高めることはできません。
絵本の読み聞かせのように、子どもと一緒に図鑑や地図を楽しむことが大切です。
その際は、子どもの疑問を引き出す読み方を意識してみましょう。
【子どもの疑問を引き出す読み方のヒント】
- 親が疑問に思ったことを、「どうしてこうなったんだろうね?」と子どもに聞く
- 子どもが「なぜ?」と聞いてきたら、一度「なんでだろうね?」と聞き返す
- 一緒に調べ、情報が載っている本やページを探す
もし恐竜に興味をもっている場合、
- 「なんで現在は恐竜がいないのだろう」
- 「隕石が原因なんだ!」
- 「隕石って何だろう」
- 「隕石はどこに落ちたのだろう」
と、どんどん疑問を引き出していけるでしょう。
また、疑問が出るたびに図鑑・地図・辞書を使って調べることで、調べる習慣や方法が身につき、学力の向上も期待できますよ。
2-2.一緒に料理を楽しむ
料理は毎日行うものである上に、親子で一緒に行いやすいことから、好奇心を伸ばす室内遊びとして取り入れやすいのではないでしょうか。
知的好奇心が伸びる3〜6歳頃は手先が器用になってくる時期でもあり、多くの作業が一緒に行えるようになってきている点でも、一緒に料理をすることはおすすめです。
【料理を通して知的好奇心を刺激する方法の主な具体例】
- ゆで卵の殻を上手に剥くにはどうしたらいいのか考えたり調べたりしてから、実践する
- 自分の好きな味付けにするには、何をどのくらい入れたらいいのか試す
- 火の色と温度の関係を調べてから強火と弱火を使ってみる
- 野菜の産地を見て、地図で調べる
「どうしたらうまくいくのかな?」「図鑑で調べた通りだね」など、子どもの好奇心や達成感を引き出せる言葉かけをしながら、一緒に料理を楽しんでくださいね。
2-3.実験遊びをする
磁石での砂鉄集めやスライム作りなど、身近な道具を使って科学現象を楽しむ実験遊びは、子どもの好奇心を育むのにぴったりの遊びです。
実験と言っても、大がかりなものをする必要はありません。
下記の例のように、家にあるものを使って科学を楽しむことが可能です。
【具体例】
- かたくり粉を使ったスライム作り
- 針金・刺繡糸・毛糸など、さまざまな素材を使った糸電話作り
- 下敷きを使って静電気を起こし、ティッシュや風船を集めるくっつき遊び
実験を行う前後に、図鑑や本で仕組みを調べると、より深い学びになりますよ。
3.【屋外】知的好奇心を高める遊び

知的好奇心を伸ばすためには、実際に体験することがとても大切です。
テレビや図鑑で知ったことを実際に目にして体験することで「テレビで見たことは本当だった!」と知的好奇心を刺激し、次の知的好奇心を育てるからです。
ここでは、学習したことと実体験を紐づけやすい外遊びのアイデアを3点紹介します。
3-1. 子どもの興味のある場所へ行く
興味は知的好奇心のはじまりです。子どもが何かに興味をもっていることが分かったら、実際に体験できる場に連れていってあげましょう。
【具体例】
- 昆虫に興味をもっていたら、蝶やセミを捕まえて観察する
- 動物や魚の絵本を好んで見ていたら、動物園や水族館に連れていく
- カップラーメンが好きだったら、工場見学に一緒に行く
子どもの興味の内容によっては、家の庭やベランダが「興味のある場所」になることもあります
【具体例】
- 食べ物に興味をもっていたら、プチトマトなど手入れが簡単な植物を育てる
- 星座や神話が好きだったら、一緒に夜空を見上げてみる
子どもの様子をじっくりみながら、興味の対象を見つけてあげてくださいね。
3-2.自然体験をたくさんする
自然と触れ合うことも、知的好奇心を大きく伸ばしてくれます。
魚・植物・空・風など、自然の中には、家では体験できない子どもの知的好奇心や五感を刺激する要素がたくさんあります。
子どもが外遊びに興味がない場合は、時間のある日のお迎えの帰り道などに、ちょっと近所を散歩することから始めてみてはいかがでしょうか。
その際にミニ図鑑を渡して花の名前を調べたり、携帯電話のカメラのズーム機能を使って虫を観察したりすることで、好奇心の発芽を後押しできますよ。
3-3.実験教室に参加する
実験遊びの項目で触れたように、実験は知的好奇心を伸ばすのにうってつけです。
そのため、家で実験遊びをするだけではなく、さまざまな場所で開催されている実験教室に積極的に参加するのもおすすめです。
実験教室では、自宅では準備することが難しい材料や道具がそろっているため、本格的な実験を体験できます。
科学が好きな子どもはもちろん、興味のない子どもでも、夢中になる仕掛けがありますよ。
実験教室は科学館や博物館の他、地域の児童館やお祭り・ショッピングモール・塾の無料体験など、身近な場所で行われている場合もあります。
まずは、ご近所で開催されている実験教室に気軽に参加してみるのもいいですね。
4.【部屋作り】知的好奇心を高めるアイデア

ここでは、知的好奇心を伸ばす部屋作りのための4つのアイデアを紹介します。
4-1.子どもの興味のあるものをそろえる
「もっと知りたい」「どうしてこうなるのか知りたい」と思うのは、好きなもの、興味をもっているものに触れているときです。
子どもの好奇心の芽を育てるために、子どもの好きなもの・興味をもっているものをどんどんそろえてあげましょう。
【具体例】
- 宇宙が好きだったら、宇宙の絵本や図鑑・天体望遠鏡をそろえる
- レゴが好きだったら、パーツを買い足す
- お絵描きが好きだったら、好きな画集や絵の具などの画材を集める
できる範囲で構わないので、興味の対象に没頭できる材料を準備してあげてくださいね。
4-2.図鑑や辞書はリビングに置く
子どもの知的好奇心を伸ばすために欠かせない図鑑や辞書は、リビングに置きましょう。
子どもが何かを調べたいと思ったとき、他の部屋に取りにいくという手間があることで、好奇心の芽を摘んでしまう恐れがあるからです。
興味をもったらすぐに手を伸ばせる、という環境を作ってあげてください。目立つ場所に置いておくことで、手にする機会もぐんと増やせますよ。
4-3.地図は子どもの目につく場所に貼る
インテリアとしても優秀な地図は、高い場所ではなく子どもが見やすい場所に貼るのがおすすめです。
絵本やテレビで知った国や都市の名前をすぐに確認できるからです。
【具体例】
おやつのりんごを食べながら「このリンゴは青森県でとれたんだよ。青森県はどこでしょう?」と聞いて一緒に探す
身近に地図があれば、地図を見る機会を簡単に増やせますよ。
4-4.親が選んだ本を子どもの本棚に飾る
子どもの興味・関心を広げて好奇心の芽を育てるために、親が選んだ本を子どもの目につく場所に飾るのもおすすめです。
「これを読みなさい」と子どもに強制すると、子どもの興味はかえって失われてしまう恐れがあります。しかし、本を飾る方法であれば、「押しつけられた」と子どもが感じることなく自然に手に取るきっかけを作れます。
本を飾る際は、子どもの興味をひきやすいように、本の表紙が見えるように飾るのがポイントです。
本の内容は、どのようなものでも構いません。例えば季節の絵本は、季節や行事を楽しめたり、ためになる知識が詰まっていたりすることが多い傾向があります。
新しい絵本の選択に迷ったときは、季節の絵本を選んでみてはいかがでしょうか。
5.子どもの知的好奇心を高めるために親ができる工夫

ここからは、子どもの知的好奇心を高めるために親ができる工夫を紹介します。
5-1.学習と実体験をリンクさせる
子どもの知的好奇心を高めるためには、学習と実体験をリンクさせることが重要です。
図鑑を眺めたり、テレビで見たことを実際に体験することで、
- 「知っている」
- 「調べたことは本当だった」
- 「楽しい」
- 「もっと知りたい」
と気持ちが変化していき、知的好奇心をぐんぐん育てます。
学習と実体験をリンクさせる主な具体例は、以下の通りです。
【具体例】
- 季節の星座を星座早見盤で見た夜、空を眺める
- 動物に関するテレビを見たあとに、動物園に行く
- 寒い時期、水の性質に関する本を読んだあとに、水を張ったバケツを外に置いて、氷を作る
- 食べ物の図鑑で断面図を見てから、実際に野菜や果物を切ってみる
子どもの興味の対象に敏感になり、学習と実体験をリンクさせる機会を増やしてあげてくださいね。
5-2.知的好奇心を刺激するきっかけを作る
何もないところからは、知的好奇心は生まれにくいものです。
図鑑・本・ドキュメンタリー番組・楽器など、子どもの知的好奇心を刺激するアイテムを、子どもの手の届く場所にそろえてあげましょう。
特に図鑑は知的好奇心を育てるためにうってつけのアイテムです。親と一緒に眺めるだけでも、知的好奇心は大いに刺激されるでしょう。
読み聞かせの際に、絵本の代わりに読んであげるのもおすすめです。
興味のある分野の図鑑は、「ドクターイエロー」「トリケラトプス」などのように名前を読みあげるだけでも子どもは夢中になりますよ。
5-3.親も知的好奇心をもち一緒に考えて応援する
子どもの知的好奇心を育てる上で欠かせないのは、親も知的好奇心をもつことです。
親がさまざまな物事に興味をもち、楽しそうに熱中している姿を見せることで、子どもも自然に興味をもっていくからです。
親に共感してもらえる・親と一緒に何かをするということは、子どもにとって嬉しいことです。その喜びが、次の好奇心やチャレンジ精神を育てていきます。
また、親に応援してもらっているという感覚は、自己肯定感を育てることにもつながりますよ。
「長い間、集中して考えていたね」「おもしろいことに気がついたね」など、プラスの言葉をたくさんかけてあげましょう。
一方「同じことを何回も聞かないで」「そんなことしてないで、早く寝なさい」などのように、子どもの興味を遮ってしまったり、子どもの質問を拒絶してしまったりすると、好奇心の芽を摘んでしまいます。
忙しい中でもほんの少し立ち止まって、子どもの言葉に耳をかたむけてあげてください。
5-4.子どものやりたいことを制限しない
子どもが何かに熱中しているときは、危険がない限り自由にさせてあげましょう。
子どもの行動を制限し、親の意見を押しつけることで、子どもの好奇心がそがれてしまう可能性があります。
また、知的好奇心が伸びる時期である3~6歳頃は、「自分でやってみたい」という気持ちが育つ時期でもあります。
自分の力でやり遂げる経験を通して達成感を味わうことで、自主性も伸ばしてあげましょう。
5-5.答えを教えない
子どもが何かに興味をもち、疑問に思ったとしても、すぐに正解を教えないことも大切です。
答えが簡単に与えられてしまうと、その場で満足して終わってしまい、興味を失ったり忘れてしまったりすることがあります。
親は答えを教えるのではなく、調べる場所や方法を教え、疑問は子ども自身で解決できるようサポートすることを心掛けましょう。
5-6.リラックスできる環境をつくる
時間がないと焦ったり、空気がピリピリしていたりする環境にあっては、好きなものが目の前にあっても楽しめません。
子どもがリラックスできる環境を作るために、次のことを意識してみましょう。
- 子どもを一人にしない
- 一緒にいる人もリラックスする
- 暑すぎず、寒すぎない温度を保つ
- 余裕のある時間を作る
1日のうち少しの間だけでも、子どもがじっくり物事に没頭できるような時間を作ってあげてくださいね。
6.子どもの知的好奇心を育てる時間は人生の宝物

家事や育児・仕事に追われる中、子どもに向き合う時間を作るのが難しいこともあるでしょう。
この記事のアイデアをすべて行おうと無理をする必要はありません。
ご家庭に合ったものや、できることを少し取り入れてみることから始めてみてはいかがでしょうか。
親と一緒に楽しんだ経験は、子どもの知的好奇心を伸ばすだけではなく、子どもの一生を支えるすてきな思い出にもなりますよ。
子どもの好奇心の芽を伸ばすヒントが見つかる!
・【3~8歳】子どもを褒めて伸ばす!「褒め方」のコツと年齢別の実践方法を紹介
・「ダメ」と言わない子育てをするには?「ダメ」に代わる声掛けや対応のヒントをご紹介
・3歳・4歳頃のなぜなぜ期とは?大人が質問に答えるときの4つのヒント