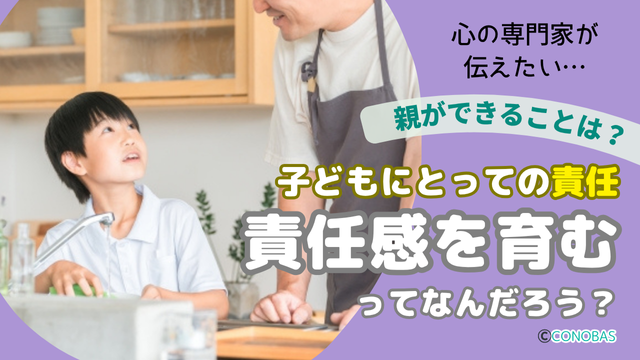
子どもの責任って?責任感を育むためにできること、強すぎる子も注意
この記事を書いた人
狩野淳
- 公認心理師
- 臨床心理士
大学、大学院にて発達心理学と臨床心理学を専攻していました。
臨床心理士と公認心理師の資格を保有しております。
子ども達とその保護者の方の支援を仕事にしており、子ども達へは主に応用行動分析を認知行動療法用いて、保護者の方にはブリーフセラピーを使ったアプローチを行っています。
もうすぐで1歳になる男の子がいて、毎日癒されています!
「うちの子、責任感がないな…」「どうしたら責任感って育つの?」
子どもらしいといえばそうだけど、責任感が育っていないだけなのかも…このまま大きくなったらどうしよう…。
そんな風に悩んでいませんか?
今回は、「子どもの責任感が育つプロセス」に注目しながら、責任感を育てる親のかかわり方について解説していきます。
反対に責任感が強すぎる子への対応についても触れていきますので、ぜひ参考にしてください。
目次
1.子どもの責任感はどう育つ?育ちのプロセスを解説!

子どもに対して「しっかりした人に育ってほしい」「物事を最後までやり遂げられる人になってほしい」と願うのは親として自然なことです。
しかし家での様子を見ていると「だらしがない」「自分で言ったことも守れない」など、責任感がない部分ばかりが目につき、将来が不安になることもあるでしょう。
お子さんの責任感を育てていくためにはどうすればよいのでしょうか。まずは責任感とは何なのか、そして責任感はどのような過程を経て育っていくのかについて紹介していきます。
1-1.そもそも責任感とは?子どもにとってはピンとこない?
はじめに責任感という言葉の意味について確認していきましょう。
責任とは「立場上当然負わなければならない任務や義務」と指し、責任感とは「自分の責任を重んじる感情」のことをいいます。
普段私たちは「責任」という言葉をなんとなく使っていますが、改めて言葉の定義を確認して皆さんはどう思われたでしょうか。
筆者は「年長や小学校低学年の子どもが抱える『立場上当然負わなければならない任務や義務』とはいったいなんだろう?」と考えてしまいました。
私たち大人は生活のためや自己実現のため、家族のために労働をし、お金を稼ぎ、生きています。責任感がなければ仕事がなくなってしまうかもしれないので、否が応でも責任感を持たざるを得ません。
しかし子どもはどうでしょうか。子どもの生活の中に「責任感」をもたなければいけない場面はどれほどあるのでしょうか。そう考えると子どもに「責任感をもちなさい」といくら言ってもいまいちわかってもらえないかもしれませんね。
1-2.「任される」→「できた!」の過程から責任感は育つ
子どもにとってとらえにくい責任感ですが、成長するにつれて必要になる力であることは間違いありません。では、どのように責任感は育っていくのでしょうか。
結論から言えば責任感は「役割をもらい評価される」ことで養われていきます。
まずは、どんな小さなことでも「お願いね」「よろしく頼むね」と子どもにお任せします。そこで任せられた行動に「ありがとうね」「助かったよ」と言ってもらえることで「やってよかった」「また任せてもらいたい」という気持ちが芽生えます。
そしてその気持ちから「きちんとやろう」「最後までやろう」という思い、つまり責任感が育まれていくのです。
この記事の後半で責任感を育てるために家庭でできることについて具体的に紹介していますので、そちらもぜひ参考にしてください。
2.責任感が乏しいまま育つとどうなる?

責任感についてと責任感が育つプロセスについて紹介してきました。責任感をもつことはとても大切なことですが、では責任感が育たないまま成長するとどうなってしまうのでしょうか。
ここからは責任感が乏しいことで生じる主な問題を3つ紹介していきます。
2-1.周囲からの信頼をなくしてしまうかも…
私たちは、一人では生きていけません。学校や職場、近所のお店など、暮らしのさまざまな場面で、誰かとつながり、支え合いながら生きています。
人との関わりは、時には少し面倒に感じることもあるかもしれません。でも、周りの人たちと良い関係を築いていくことは、とても大切なことです。そして、そのために欠かせないものの一つが「責任感」なのです。
もし責任感がなく、任されたことや自分のやるべきことを大切にしないと、周りの人はがっかりしてしまいます。「この人にはもう頼めないな」と思われ、少しずつ信頼を失っていくでしょう。
その結果、気づいたときには周りから孤立してしまう…そんな悲しいことにもなりかねません。
2-2.自分に自信が持ちにくくなるかも…
責任感は「任され評価されることで培われる」と紹介しましたね。こうした体験が少ないと、「自分ならできる」という感覚(自己効力感)を得られず、自分に自信が持ちにくくなってしまうのです。
そして、自信がないままだと、何かを決めるときに「誰かに指示してもらおう」と考えたり、責任のある役割から「自分には無理だ」と逃げてしまったりするようになります。
これでは、ますます自信をつけるチャンスが遠ざかってしまう…という悪循環に陥ってしまいます。
2-3.決断ができなくなるかも…
責任感や自信がないと、物事を「自分で決める」ことが難しくなります。
子どもの成長に合わせて任されることも大きくなりますが、ここで親が手を貸しすぎてしまうのは考えものです。子どもから「責任を持ってやり遂げる」という大切な経験を奪ってしまうからです。
その結果、「僕は考えなくていいんだ」「ママが決めてくれるから楽だな」といった、受け身の姿勢が身についてしまう恐れがあります。
親は、一生子どもの面倒を見られるわけではありません。将来子どもが自分の力で考え、自立していくために、責任感は今のうちから少しずつ育んでいく必要があるのです。
3.責任感を養うために親にできることとは?

責任感が育たないまま成長してしまうことで、子どもにどのようなデメリットが生じるのかお分かりいただけたかと思います。
では、子どもの責任感を育てるには、具体的にどのようなかかわりをしていけばよいのでしょうか。次に家庭内でできる責任感の育て方について解説していきます。
3-1.家庭内で「役割」をつくろう!
責任感を育てるにはまずは小さなことを任せていくことから始めましょう。
どんなことでも構いません。その子に合ったできるだけハードルの低いもの、単発ではなく日々の暮らしの中で何回か生じるものをお願いしてみてください。
例えば「箸を運ぶ/並べる」「洗濯物を運ぶ」などが挙げられるでしょう。そして子どもが役割を全うしたら必ず「ありがとう」「助かったよ」などの感謝の言葉を伝えてあげましょう。
それだけで子どもは役割を意識し、「これは自分のやることなんだ」と意識をもって行動することができ、責任感へと繋がっていきます。
また、お願いは具体的に伝えてあげてください。「箸をあっちにもっていって」「洗濯物をいい感じにしまっておいて」など抽象的な指示は避けるようにしてください。
年齢的にあいまいな言葉が理解できない可能性があります。ここでつまずいてしまうと「自分にはできないんだ」と感じてしまったり、親としても「なんでこんなこともできないの」「考えればわかるはずでしょ」とついつい文句を言いたくなったりしてしまいます。
そのようなトラブルを避けていくことも意識してください。
3-2.「手出し」や「口出し」は封印!
日常生活の中で子どもの行動に手出しや口出しをしすぎないことが大切です。
子どものやることは効率が悪く、そのままほっておくとマイナスなことになるのではと思い、ついつい軌道修正したくなってしまいますよね。
しかし先ほども紹介した通り、何でもかんでも親が介入してしまうと、子どもは考えることをやめてしまい、役割の重要性を感じることができなくなってしまいます。
多少の失敗には目をつむり、むしろ失敗することで学びとなり、今後の人生においてプラスになると前向きに考え、見守る姿勢をとっていきましょう。
3-3.「できていない部分」だけの指摘はNG
子どものことを思うからこそ、ダメ出しをしてしまう親は少なくありません。
「次に生かしてほしい」、「もっと効率的にやってほしい」という思いから失敗点や改善案を伝えてしまいがちですが、素直に受け止められる子ばかりとは限りません。なかには「文句言うなら自分でやってよ」とへそを曲げてしまう子もいます。
そのため、まずはできている部分、よかった部分を伝えてあげてください。自分の行動を前向きにとらえることができ、自信に繋げてあげることで責任感は成長していきます。
出来なかった部分や改善すべき部分は最初のうちは伝えなくて大丈夫です。回数を重ねていくにつれて自分で気づいてくれる場合もあります。
もしお子さんが自分で改善点に気づけず、どうしても伝えたい場合は、言葉でストレートに伝える前に、保護者様がやって見せてあげてください。これなら親としては伝えたいという気持ちを、子どもは「自分で気づけた」という自信を満たすことができます。
4.逆に責任感が強すぎる子へはどう対応すればいい?

ここまで責任感がない子どもについて触れてきましたが、次に責任感が強すぎる場合について解説していきます。
責任感があることは喜ばしいことですが、あまりに強すぎる責任感は子ども自身への負担となってしまいます。責任感が強すぎる子に対してはどのように接していけばよいのでしょうか。
4-1.適度に力を抜くことを教えてあげよう
責任感が強すぎる子は「○○しなければならない」「××すべきだ」という思考に囚われている場合があります。心理学ではこれを「全か無かの思考」といい、修正していく必要があります。
大人の場合は自分の全か無かの考え方に気づき、直していきますが、子どもの場合はそこまで至ることは難しいでしょう。そのため周囲の大人がその都度気づくきっかけを用意していく必要があります。
例えば、子どもが「絶対しなきゃいけないんだよ!」と言ったら、「本当に絶対なのかな?もしかしたらそうじゃないかもしれないよ」と視点を変える声を掛けてあげるのもおすすめです。
また、責任感の強さから「完璧にできなかった…」と落ち込んでいるような場合は、「でもここは十分にできたね」と部分的に評価することを伝えることで、次第に思考が柔らかくなり、適度に力を抜くことを身につけていけます。
4-2.「正しさ」と「優先順位」のあり方を話し合おう
責任感が強い子が引き起こしてしまうトラブルとして「周りの子にも責任感を強要する」ことがしばしばあります。
「みんなやっているのに何で君だけやらないんだ」「自分の仕事なんだからしっかりやれよ」といった強すぎる正論は、いくら正しくても言われた側の逃げ道をなくしてしまい、強い反感を買ってしまいかねません。
責任感をもつことの正しさに寄り添いながらも、「先生の力が必要かもしれないな」「〇〇くんだけだと、喧嘩になったときに大変だから先生に注意してもらおうか」など、トラブルを回避する方法を伝えてあげましょう。
最も大切なのは「自分を大切にすることが優先」であることを分かってもらうことです。隣の子が騒いでいるから、それを注意していたらやることができなかった…。そんな状況にならないように、ある程度、「他人は他人、自分は自分」と区別して集中することを身につけてもらいましょう。
★コラム.親の責任感が強いことは子どもに影響する?
親の価値観は子どもに大きな影響を与えます。そのため親の責任感が強いと子の責任感も強くなる傾向があります。
子どもは多くの時間を家族というコミュニティで過ごすため、「親の価値観=絶対的な価値観」としてとらえてしまいます。そうすると「家ではこうだから幼稚園や保育園、学校でもそうすべきだ」と考えてしまい、トラブルに発展しかねません。
子どもの責任感が強すぎると感じたときには、はじめに自分たちの言動から振り返りましょう。
子どもは親の背中を見て育ちます。親のよい手本が子どもにとっての最高の教材です。
みなさんの責任感は強すぎていませんか?全か無かの思考になっていませんか?相手にも自分の価値観を押し付けていることはありませんか?
5.程よい責任感で環境に適応できる力を育てましょう

今回は子どもの責任感についての概要と成長のプロセス、家庭でもできる取り組み、そして強すぎる責任感をもつ子に対しての関わり方について解説してきました。
責任感をもつことはよいことですが、何事もほどほどが大切です。適度な責任感をもつためには、家庭の中で役割を与え、評価していくことが重要です。そうすることで責任感以外にも、自信や他者との関係を構築する力を身につけることができます。
なかには難しく思ってしまう親御さんもいるかもしれませんが、子どもを信じ、任せ、褒めてあげるだけで子どもは成長していきます。
「子どもには立派な人になってほしい」という気持ちは必ず子どもに伝わります。親子で楽しみながら、是非子どもの力を伸ばしてあげてください。
買い切りキットでいつでも自由に!自宅で質の高いロボット・プログラミング学習![PR]
「ロボット教室やプログラミング教室、興味はあるけど…どこがいいか分からない」
「近くに良い教室がない」 「仕事が忙しくて、毎週の送迎はむずかしい」
子どもの習い事を考えた時、そんな風に悩んだことはありませんか?
ソニーグループが開発した「KOOV®(クーブ)」は、教室に通わずに、自宅で質の高いロボット・プログラミング学習ができるオールインワン・キットです。
必要なのはキットとご家庭のタブレットやPCだけ。お子さまの好きな時間に、好きなだけ夢中になれます。
★自宅が最高の教室になる!KOOV®の魅力
✓ 先生はアプリ!一人でもどんどん進められる
専用アプリが、まるで個別の先生のように、組み立てからプログラミングまで丁寧にガイド。お子さまの理解度に合わせて解説やクイズも出るので、一人でもつまずくことなく自分のペースで学習を進められます。
✓ 教材はプロ品質!全国の学校・塾おすみつき
教材は、全国1,000以上の学校や塾で実際に使われている本格派。送迎の手間なく、教室で学ぶのと同じ質の高いカリキュラムをご自宅で体験できます。
✓ 月謝不要!長く使える買い切り型
月謝のかかる教室とは違い、キットは一度購入すればOK。ご兄弟で使ったり、お子さまが大きくなってからも新しい作品に挑戦し続けたりと、ご家庭で長くご活用いただけます。
✓ 目に見える「達成感」
分かりやすい3Dガイドでロボットが完成する達成感。そして、そのロボットが自分のプログラムで動き出す感動。目に見える成功が、お子さまの自信を育みます。
✓ 「失敗」が「学び」に変わる
プログラムは、何度でも簡単にやり直せます。「うまくいかない」は「ダメなこと」ではなく、「どうすれば良くなるか?」を考えるチャンスだと、遊びながら学べます。
✓ 粘り強く工夫する力がつく
「もっと速く走らせたい」「違う動きをさせたい」という欲求が、目標に向かって試行錯誤する原動力に。この経験が、困難なことにも粘り強く取り組む姿勢を養います。
気軽に始められる入門モデル「KOOVエントリーキット」から、ガッツリ学ぶスターターキットまで、子どもの興味関心や価格に合わせて選べます。
工作や折り紙、粘土遊びなど、作ることが好きなお子さんにもおすすめです。
詳細はこちら>>>ソニーのロボット・プログラミング学習キット「KOOV(クーブ)」
関連トピックをご紹介!
・約束を守らない子どもにイライラ!約束を守れない理由と親の接し方
・自分の話ばかり!人の話を聞けない子への関わり方・教えたい「会話力」
・強い意志で未来を切り拓く!子どもの自制心を鍛えるコツを保育士が紹介





