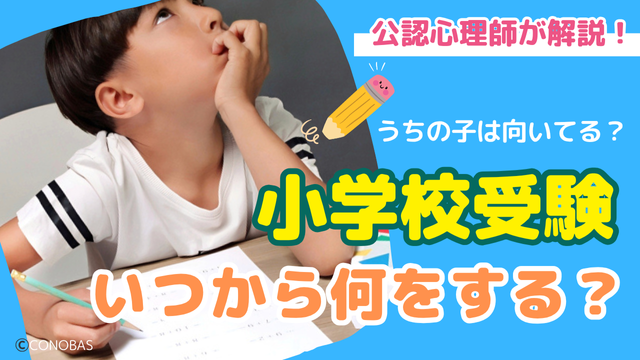
小学校受験の準備はいつから始める?向き不向きや年齢別準備スケジュール
この記事を書いた人
米澤駿
- 公認心理師
- 臨床心理士
公認心理師・臨床心理士として、子どもやご家族のこころや発達の支援に約10年間携わってきました。
学童や放課後等デイサービスの指導員、乳幼児健診の発達相談員、スクールカウンセラーなど幅広い現場で、発達段階に応じた対応や保護者支援を経験しています。
自分自身も一児の父として、毎日の子育てに奮闘中。
心理学の専門知識と現場経験、そして親の目線も大切にしながら、皆さまのお役に立てる情報を分かりやすく丁寧な言葉でお伝えできるよう心がけています。
「小学校受験って、しておいた方がいいの?」「準備はいつから始めればいい?」
そんな悩みをお持ちではありませんか?
SNSやママ友との会話で「小学校受験」という言葉を耳にすると、「うちの子は受験に向いているのかな?」「受験するにしても、何から始めればいいの?」と不安や疑問を感じる方もいるのではないでしょうか。
今回は、小学校受験の基礎知識から受験に向いている子・向いていない子の特徴、さらに年齢別の具体的な準備スケジュール、ご家庭でできる効果的なサポート方法まで、徹底的に解説します。
受験を無理に進めるのではなく、我が子の個性や適性を見極めた上で、最適な教育環境を選ぶための判断材料として、この記事をぜひ参考にしてください。
目次
1.小学校受験の基本知識とメリット・デメリット

近年では小学校受験が益々注目されていますが、「そもそも小学校受験って何?」「公立とは何が違う?」といった疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで、まずは基礎知識や、受験することで得られるメリット・デメリットについて分かりやすく整理します。
1-1.小学校受験とは?概要と最近の傾向
小学校受験とは、公立小学校ではなく私立小学校に入学するための選考試験を受けることです。一般的に首都圏や関西圏の都市部を中心に行われており、近年は教育熱心な家庭を中心に人気が高まっています。
私立小学校の選考方法は学校によって異なりますが、主に以下のような試験が実施されます。
■ ペーパーテスト:図形や数の問題、言語理解などの基礎学力を見る問題
■ 行動観察:グループ活動での協調性や積極性、指示理解力などを見る
■ 運動テスト:基本的な運動能力や体のバランス感覚を確認
■ 面接:保護者面接や親子面接で家庭環境や教育方針の一致を確認
最近の傾向としては、単に知識を問うだけでなく、「考える力」「コミュニケーション能力」「創造性」を重視する学校が増えています。
また、国際教育やICT教育に力を入れる私立小学校も増加しており、グローバル社会を見据えた教育を提供する傾向にあります。
1-2.私立小学校と公立小学校の違い―教育環境・特徴を比較
★ 私立小学校の特徴
- 独自の教育方針・・・学校ごとに特色ある教育カリキュラムを展開している
- 少人数制・・・1クラスあたりの生徒数が少なく、きめ細かい指導が受けられる
- 施設・設備の充実・・・最新の教育設備や広い校庭など恵まれた環境が多い
- 進学実績・・・系列の中学・高校への内部進学や難関校への進学率が高い
★ 公立小学校の特徴
- 地域密着型・・・地域の子どもたちと一緒に学び、地域とのつながりを育める
- 多様な価値観・・・様々な家庭環境や考え方の子どもたちと触れ合える
- 学費負担が少ない・・・義務教育なので基本的に授業料はかからない
- 通学の利便性・・・基本的に自宅から近い学校に通うことができる
1-3.小学校受験のメリット・デメリット
★ メリット
- 教育方針が明確・・・各学校の教育理念に基づいた一貫性のある教育を受けられる
- 質の高い教育環境・・・少人数制で教師の目が行き届き、特色ある教育が受けられる
- 早期からの能力開発・・・受験準備の過程で基礎学力や社会性が自然と身につく
- 中高一貫教育への道・・・系列の中学・高校へ内部進学できるケースが多く、受験の負担が軽減
★ デメリット
- 受験のストレス・・・幼い子どもに過度なプレッシャーをかけてしまう恐れがある
- 経済的負担・・・入学金、授業料、寄付金など相当の費用がかかる
- 時間的制約・・・通学時間が長くなる場合があり、遊ぶ時間が減少する可能性が高い
- 親の負担・・・送迎や学校行事への参加など、保護者の時間的・精神的負担も大きい
2.小学校受験に向いている子・向いていない子の特徴

小学校受験は全ての子どもに適しているわけではありません。お子さんの特性や個性を見極め、受験が適しているかどうかを判断することが大切です。
ここでは、受験に向いている子と向いていない子の特徴、そして我が子の適性を見極めるポイントについて解説します。
2-1.小学校受験に向いている子の4つの特徴
1.好奇心旺盛で新しいことに興味を示す子
「どうして?」「なぜ?」といった質問を積極的にし、物事を知りたがる姿勢がある子どもは、受験準備の様々な学びも前向きに取り組める傾向があります。
2.基本的な生活習慣が身についている子
挨拶や身の回りの整理整頓、時間を守るなどの基本的習慣が身についている子どもは、受験準備と並行して生活リズムを整えやすい傾向があります。
3.新しい環境への適応力がある子
環境の変化に柔軟に対応できる子どもは、受験塾や新しい学校環境にもスムーズに適応できる可能性が高いです。
4.コミュニケーション能力が高い子
初対面の人とも臆せず話せる、集団行動が得意といった特徴を持つ子どもは、面接や行動観察などの試験でも力を発揮しやすいでしょう。
2-2.小学校受験が向いていない子(負担になりやすい子)の4つの特徴
1.マイペースで急かされるのを嫌う子
自分のペースを大切にするタイプの子どもは、受験勉強の計画的なスケジュールに窮屈さを感じる場合があります。
2.こだわりが強く、柔軟な対応をすることが苦手な子
特定のことへのこだわりが強く、予定の変更に対応しづらい子どもは、受験準備の多様な学習内容や試験本番の臨機応変な対応が難しい場合があります。
3.新しい環境に慣れるのに時間がかかる子
初めての場所や人に慣れるまでに時間がかかる子どもは、受験塾や試験会場などの新しい環境でのパフォーマンスが発揮しにくい場合があります。
4.集団行動が苦手な子
一人遊びを好み、集団での活動に馴染みにくい子どもは、行動観察などのグループ活動を含む試験で不利になる可能性があります。
2-3.我が子の適性を見極めるポイントは?
また、お子さんが小学校受験に向いているかどうかを判断するためには、以下のポイントに注目してみましょう。
■ 日常生活での様子
普段の遊びや生活の中で、集中力や好奇心、コミュニケーション能力などを観察しましょう。例えば、絵本を読む時の集中力や、公園での他の子どもとの関わり方などが参考になります。
■ 幼稚園・保育園の先生の意見
集団生活での様子は、幼稚園や保育園の先生が客観的に見ています。定期的に先生と情報交換し、園での生活や集団行動の様子について聞いてみるのもよいでしょう。
■ 幼児教室での反応
幼児教室や体験教室に見学・体験してみて、お子さんがどのような反応を示すかを観察しましょう。楽しそうに取り組むか、ストレスを感じているかなどが判断材料になります。
3.年齢別・小学校受験の具体的準備スケジュール

いざ受験を考え始めたら「いつ、何から始める?」という疑問が浮かびますよね。
ここでは、2歳から6歳までの年齢別に、具体的な準備スケジュールをご紹介します。
3-1. 2〜3歳からの基礎づくり
この時期は、受験のための「勉強」というよりも、学びの土台となる基本的な力を遊びの中で育んでいきましょう。
無理に「勉強」と意識させず、楽しみながら好奇心や学ぶ姿勢を育てることが大切です。
【家庭でできること】
- 生活習慣の確立
挨拶、食事、着替え、片付けなどの基本的生活習慣を身につけましょう。「ありがとう」「ごめんなさい」などの言葉も自然に使えるように促します。
- 手指の発達を促す遊び
折り紙、粘土、お絵かき、ビーズ通しなどの遊びで、手先の器用さと集中力を育てます。
- 絵本の読み聞かせ
語彙力や想像力、集中力を養います。質問を交えながら読むことで、考える力も育ちます。
- 運動遊び
公園でのかけっこやボール遊びなどを通じて、基礎的な運動能力が育めます。
3-2.4歳からの本格準備
4歳になると、少しずつ本格的な受験準備を始める時期です。徐々に「お勉強」という意識を持たせながらも、「できた!」という達成感や成功体験を重視しましょう。
また、小学校受験を真剣に検討している場合は、この時期から専門の幼児教室を利用するのもよいでしょう。
【家庭でできること】
- 知育遊びの時間
市販の知育玩具や幼児ドリルを活用し、「お勉強タイム」として習慣化するとよいでしょう。ただし、楽しく取り組める範囲にとどめることが重要です。
- 体験の拡大
動物園や水族館、博物館など様々な場所に出かけ、体験を通じて知識や語彙を増やします。おでかけの後は「何が楽しかった?」と感想を聞くことで、言語化の習慣づくりにもなります。
- 自分の考えを伝える練習
「なぜそう思うの?」と理由を尋ねたり、「もしも〇〇だったらどうする?」と考えを引き出したりする会話を増やしましょう。
3-3.5〜6歳の受験直前期
いよいよ受験の年を迎え、これまでの学びを整理し、本番に向けた最終調整を行う時期です。
この時期は子どもにとって緊張やプレッシャーを感じやすい時期なので、十分な睡眠と栄養、適度な運動を心がけ、心身の健康を維持することも重要です。
【家庭でできること】
- 復習の習慣化
これまで学んだことを家庭で復習する習慣をつけます。弱点を補強しながら、得意分野はさらに伸ばしていきましょう。
- 生活リズムの調整
試験当日の生活リズムに合わせて、起床・食事・活動の時間を調整します。
- 志望校別対策
志望校が決まったら、その学校の出題傾向や面接スタイルに合わせた対策を取り入れます。本番を想定した模擬テスト(過去問)や模擬面接をして、試験慣れしておくとよいでしょう。
4.親が心がけたい!効果的な受験サポートのコツ

小学校受験の成功には、お子さんの努力だけでなく、親のサポートが欠かせません。
特に「勉強が好きではない」「やる気が出ない」といった場合には、親の関わり方が重要になります。ここでは、効果的な受験サポートのコツをご紹介します。
4-1.勉強嫌いな子へのやる気アップ術
■ 子どもの興味から学びにつなげる
お子さんが好きなキャラクターや乗り物、動物などの興味を活かした教材や遊びを取り入れましょう。例えば、恐竜が好きな子なら恐竜図鑑で数を数えるなど、興味と学びをつなげる工夫が効果的です。
■ ゲーム感覚で学ぶ
カルタやすごろく、カードゲームなど、遊びながら学べる教材を活用しましょう。「勉強」という枠組みではなく、「一緒に遊ぼう」という姿勢で誘うと抵抗感が少なくなります。
■ 短時間で区切って取り組む
集中力の続かない子どもは、最初は5分、10分といった短い時間から始めて、徐々に延ばしていきましょう。「この時計の針がここまで来たら終わりだよ」と、目に見える形で時間を示すと取り組みやすくなります。
■ 選択肢を与える
「絵を描く練習をする?それともパズルをする?」のように、複数の選択肢から選ばせることで、子どもに決定権を与え、主体性を育みます。すべてを大人が決めるのではなく、子どもが選べる部分を作ることで、子どものやる気が引き出されます。
■ 達成感を生み出す
難しすぎず、かといって簡単すぎない“ちょうどよい難易度”の課題を用意し、「できた!」という成功体験を積み重ねることが大切です。小さな成功でもしっかり褒めることで、子どもの達成感や自信につながります。
4-2.「結果よりもプロセス」を大切にする姿勢を教えよう
「正解できてすごいね」「よくできたね」という結果に対する褒め言葉よりも、「あきらめずに最後までやったね」「自分で考えてできたね」など、プロセスに焦点を当てた褒め方をしましょう。
これにより、「結果」ではなく「取り組む姿勢」に価値があることを子どもに伝えられます。
小学校受験は、「子どものため」と思いながらも、ついつい親の期待や願望を押し付けてしまいがちです。しかし、最も大切なのは、子どもが「学ぶことは楽しい」と感じる経験を積み重ねることです。
受験をきっかけに、生涯にわたって学び続ける姿勢を育むよう、長期的な視点でサポートしていきましょう。
5.小学校受験の準備は「我が子らしさ」を大切に

小学校受験は、お子さんの将来の可能性を広げる有力な選択肢の一つです。
受験準備の過程は、お子さんにとっても保護者にとって大変な時期かもしれませんが、それと同時に、お子さんの成長を実感できたり、親子の絆をより深めたりできる貴重な時間にもなります。
ただし、合格という結果にとらわれて無理に子どもを変えようとするのは適切ではありません。
小学校受験の本来の目的は「子どもの特性や個性を活かせる環境を選ぶこと」であり、受験準備は、お子さんのペースに寄り添いながら無理のない範囲で取り組むことが、最終的に良い結果や経験につながります。
どのような選択をするにしても、子どもの“今”を大切にすることが、親子にとって最も価値のある選択となるでしょう。
偏食・野菜嫌いさんにもおすすめ!無添加・手作り冷凍幼児食「mogumo(モグモ)」
[PR]
当たり前のように思われがちですが、毎日食事を作るのは、とても大変ですよね。
「今日はゆっくりしたい」
「手を抜きたくないけれど、時間がない」
「市販の総菜や幼児食を取り入れるのは抵抗がある」
「家事や育児でぐったり…」
「何を作ればいいだろう?料理は苦手だなぁ」
悩みはそれぞれですが、毎日の食事作りのお供に、冷凍宅配幼児食「mogumo(モグモ)」を活用してみるのもおすすめです。
モグモの幼児食は、全て手作りの無添加。管理栄養士が監修しているため、栄養バランスはもちろん、美味しさにもこだわっています。
mogumo(モグモ)の特徴
✓冷凍だから、レンジで温めるだけで簡単に食べられる
✓かわいいパッケージで、子どもの興味もそそられる
✓何食、どれくらいの期間利用するかは、家庭に合わせて自由に選べる
✓予定に合わせて、お届けスキップやプラン変更が可能
独自の冷凍技術で、長期間保存ができるので、冷蔵庫にストックがあるだけで安心です。
幼児食ってどうすればいいの?とお悩みの方には、管理栄養士の無料相談サポートもあります。
利用できるサービスは、上手に活用しながら、無理せず親子で楽しい時間が過ごせると良いですね。
詳細はこちらから>>冷凍宅配幼児食「mogumo(モグモ)」
関連トピックをご紹介!
・3歳児にぴったり!季節感が育つ「ちぎり絵」遊び~知育効果や楽しむポイント~
・学ぶ力の源!想像力(創造力)の鍛え方│遊び・習い事・家庭での関わり方
・子どもの選択肢が広がる!空間認知能力とは?高める遊びや知育ゲームを紹介





