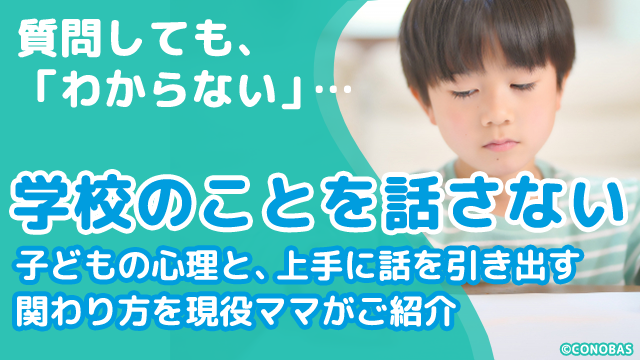
学校のことを話さない…。子どもの心理と、上手に話を引き出す関わり方をご紹介!
この記事を書いた人
横山ミノリ
- 中学校教諭
- 高等学校教諭
- 小学校教諭
- 児童発達支援士
小1と年少、2人の男子の母です。
ASD(自閉スペクトラム症)の長男への関わり方を学ぶため、「児童発達支援士」と「発達障害コミュニケーションサポーター」の資格を取得しました。
自身が産後うつと育児ノイローゼになった経験から”ラクに生きる”がモットーに。
子どもには「自分で決めた!」「自分でできた!」という経験をたくさんしてほしいと思っています。
子どもとの好きな遊びは工作。子育てで好きな本は、高濱正伸著の「こどもの可能性を伸ばす「しない」子育て」です。
少学1年生~3年生のお子さんをお持ちのママで、「子どもが学校のことを全く話さない」「質問しても『忘れた』『わからない』と言って話してくれない」などのお悩みをお持ちの方はいませんか?
周りの親子が仲良く会話している姿を見ると、うらやましく思うこともあるかもしれません。また、子どもから上手に話を引き出すポイントも知りたいですよね。
この記事では、学校のことを話さない子どもの心理や、子どもの話を聞くときのポイントをご紹介します。子どもに学校のことを話してほしいママの心理についても深掘りしますよ!
これを読めば、子どもの気持ちを尊重しながら話を引き出す方法がわかるでしょう。また、親子の会話をきっかけとして、お子さんとの関係を見つめなおす機会になれば幸いです。
目次
1.学校のことを話さない子どもの心理
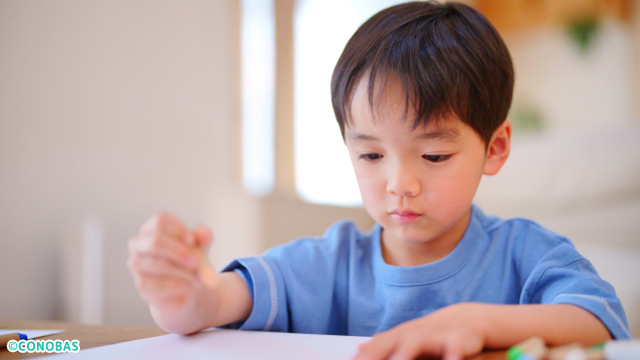
はじめに、学校のことを話さない子どもの心理を5つご紹介します。子どもの気持ちや状況を理解する手がかりにしてみてください。
1-1.「話すことが好きでない」
子どもが学校の話をしないのは、もともと話をするのが好きではないからかもしれません。内向的な性格の子どもの多くは、日常的に自分の考えや感情を言葉にすることにあまり興味を持たない傾向にあります。
自分の中で感情を処理するのが上手いので、誰かに話さなくてもすんでしまい、むしろ、話すこと自体がストレスになる子どももいます。
「話すことが好きではない」と聞くとネガティブにとらえがちですが、話すことが好きではない子どもは、社交的な子どもにはない長所を持っていると言えるでしょう。
1-2.「どう話したらよいか分からない」
学校のことを話したい気持ちはあるのに、「どう話したらよいか分からない」という子どももいます。
「今日は学校どうだった?」のように質問が抽象的すぎると、どう答えたらよいか分からず、つい「分からない」「忘れた」と言ってしまうのです。
この年齢の子どもにとって、その日の出来事を思い出して整理し分かりやすく伝えるのは、言語発達的にまだ難しいことを理解しておきましょう。
1-3.「何でもかんでも話したくない」
子どもが学校のことを話さないのには、子どもの精神的発達が関係していることもあります。
7~10歳は、幼児期に持っていた自分中心の考え方から、他者の視点で物事を考えられるようになる時期です。ママを含め、周りの人からどう思われるのかを気にするようになり、それが言動にも影響を与えます。
また、小学3年生くらいから思春期が始まる子どももいます。「親に全て把握されるのがイヤ」「親から自立したい」という気持ちから、学校のことを話したがらないのかもしれません。
これまでに過干渉を受けていたり、逆に自分の話を聞いてもらえる環境にいなかったりするとなおさらです。
1-4.「心配させたくない」
子どもが学校で何か問題を抱えている場合、「ママに心配をかけたくない」という気持ちから、学校の話をしないというケースも考えられます。今まで学校のことをよく話していたのに、急に何も話さなくなった場合はこの可能性があります。
心配させたくないだけでなく、「話して事態が大きくなるのがイヤ」と思っている子どももいるでしょう。
1-5.「疲れているから話したくない」
学校から帰宅後は子どもも疲れていて、自分のペースでゆっくりしたいと思うものです。そのタイミングで子どもから話を聞こうとしても、何も話さなかったり、てきとうに答えたりするだけかもしれません。
少し休憩すれば、リラックスした状態で話してくれることがほとんどです。
2.学校のことを話さない子どもへの関わり方のポイント

次に、学校のことを話さない子どもに対して、ママが普段からできる関わり方のポイントをご紹介します。
2-1.子どもの様子を観察する
1つ目のポイントは、子どもの様子をよく見ることです。子どもが学校のことを話さなくても、表情や行動から多くの情報を得られるからです。
「ただいま」の声のトーンや帰宅後の過ごし方、食事の様子など、普段からよく観察していれば小さな変化にも気づくでしょう。
このように子どもの様子をよく観察することは、子どもの言葉には表れない気持ちに目を向ける機会にもなります。
2-2.親子でリラックスできる時間を作る
会話をするしないに関係なく、親子が一緒にリラックスできる時間は大切です。お互いにリラックスしていると、子どもは素直な気持ちを話しやすいからです。
おやつの時間や食事中、車や自転車での移動中、寝る前のひとときなど、親子が一緒に過ごす時間はたくさんあります。 慌ただしくしているとあっという間に時間が過ぎてしまうので、1日の中でリラックスできる時間を意識的に作ることをおすすめします。
もちろん特に会話をしなくてOKです。「いつでも話してね」という気持ちを伝え、「何かあったらこの時間に話そう」と子どもに思ってもらえるようにしましょう。
2-3.学校と情報を共有する
子どもへの関わり方ではありませんが、学校と子どもの状況を共有しておくのも良い方法です。担任の先生に、子どもが学校のことを話さないという事情を事前に伝えておくと、何かあったときに教えてもらえるかもしれません。
同時に、家での子どもの様子も先生に伝えられるといいですね。 先生と情報を共有することで、学校で何か問題があったときにも早めに対処することができるでしょう。
2-4.ママが自分の話をする
ママが積極的に自分の話をすることも、学校のことを話さない子どもに良い影響を与えます。ママがその日あった出来事や感じたことを話すことで、子どもは自分の気持ちを言葉で表現する方法を学べます。
また、ママが自分の感情や考えをオープンに話すことで、子どもは「何でも話してもいいんだ」と思えるでしょう。
3.学校の話を聞くときのポイント

ここでは、子どもから学校の話を聞くときのポイントをご紹介します。子どもが自分から話したくなる状態を目指して、できるものから実践してみてください。
3-1.具体的に質問する
子どもにとって抽象的な質問は答えにくいため、学校での出来事を聞くときは、できるだけ具体的に質問しましょう。
例えば、「今日は何の授業があったの?」「給食のメニューは何だった?」のような答えやすい質問をすることで、子どもは話しやすくなります。
具体的な質問は子どもの記憶を引き出しやすく、そこから子どもの心に残った具体的なエピソードを聞けるかもしれません。
3-2.子どもと目線を合わせる
学校の話を聞くときは、できるだけ手をとめて、子どもと目線を合わせるようにしましょう。子どもの顔を見て話を聞くことで、「話を聞きたい」というママの気持ちが伝わり、子どもの表情もチェックできます。
また、子どもも相手の目を見て話す練習になるでしょう。自分と向き合ってもらえる環境があると、子どもは精神的に安心でき、話したいと思ったタイミングで自分から話してくれるはずです。
3-3.相槌を打ちながら聞く
子どもが学校の話をしてくれたときは、相槌を打ちながら聞くのもポイントです。「うん、うん」「そうなんだね」などの相槌があると、子どもはちゃんと話を聞いてもらえていると分かり、安心して話せるからです。
返す言葉が見つからなかったら、子どもの言ったことをそのままくりかえすだけでもOKです。子どもの話すテンポに合わせて相槌を打てば、子どもは気持ちよく会話を続けられるでしょう。
3-4.評価や否定はしない
子どもの話を聞くときは、話の内容を評価したり否定したりしないように気をつけましょう。ただ聞いてほしかっただけなのに話した内容について言われると、もうその人に話したくなくなるのは、大人も子どもも同じです。
また、ママにどう思われるかを気にするあまり、子どもが本当の気持ちを話さなくなることもあります。
そのため、子どもの話を聞くときは、まずその子の気持ちに共感することが大切です。「話してくれてありがとう」と伝えれば、子どもはもっと自分の気持ちを話そうと思ってくれるでしょう。
3-5.詮索し過ぎない
子どもが話したいこととママが聞きたいことが、必ずしも一致するとは限りません。詮索し過ぎて子どもの話したい気持ちを削がないようにすることも、学校の話を聞くときのポイントです。
ママが、自分が知りたいことしか聞いてくれないと分かると、子どもは自分から話しづらくなるかもしれません。
子どもが自分の話したいことを自分のペースで話せるように、「何でも聞くよ」というスタンスを示しましょう。
4.学校の話を聞きたいと思うママの心理

「学校の話を聞きたい」というママの気持ちの裏には、どんな心理が隠れているのでしょうか。
気持ちの正体が分かると、子どもへの関わり方も変わるかもしれません。
4-1.「子どもが学校生活を楽しめているか心配」
多のママが学校の話を聞きたい理由の1つに、「子どもが学校生活を楽しめているか心配」という気持ちがあります。
子どもが学校で何か嫌な思いをしていないか、友達関係や授業内容に不安を感じていないかを知りたいのは、ママとして当然です。子どもが学校で楽しく過ごしている話を聞くだけで、安心できるものですよね。
しかし心配するあまり、つい子どもに話を急かしたり、質問攻めにしたりしてしまうことがあるかもしれません。そんなときには、自分の心配が子どもにプレッシャーを与えていないか、改めて考えてみるのをおすすめします。
4-2.「子どもと仲良くおしゃべりしたい」
「子どもと仲良くおしゃべりしたい」という思いも、ママが学校の話を聞きたい理由の1つかもしれません。
子どもが自分から話してくれるタイプでないと、楽しそうに会話している親子を見てうらやましく思うこともあるでしょう。
確かに、その日あったことを子どもが自分から話してくれるのは嬉しいものです。 しかし、いつも仲良く話せることだけが、良い親子関係ではありません。子どもにとって本当に助けが必要なときに話を聞いて、支えてあげられる存在になりたいですよね。
大切なのは、「おしゃべり」という表面的なことよりも、子どもと「何かあったときに何でも話せる」という信頼関係を築くことなのです。
4-3.「学校で何をしているのか知りたい」
単純に、子どもが学校で何をしているのか知りたいというママも多いでしょう。学校のことを知る術が連絡帳や学校からのお便りだけだと、クラスの様子や休み時間のことなど、もっと詳しく知りたくなりますよね。
学校のことを知りたいときは、ママ友に聞くのがおすすめです。子どもより上の学年のママに聞くと、知らなかった情報も聞けて面白いですよ!
また、役員になったり校内のボランティア活動に参加したりすると、学校の様子が分かるかもしれません。たとえ学校のことは分からなくても、子どもが毎日元気に通っていることは確かです。
「どうして学校のことを話してくれないのだろう」とモヤモヤするより、学校でがんばってきた子どもを「おかえりなさい!」と温かく迎えることに全力を注いでみてはいかがでしょうか。
5.子どもを見守る姿勢と「いつでも話してね!」というスタンスを大切に

子どもが学校のことを話さないのには、性格やその日のコンディション、心理的・言語的発達など、その子なりの理由があります。
「いつでも話してね」というスタンスを忘れず、子どもの様子を見守りましょう。 もし子どもが話したくないのであれば、その気持ちを尊重することが大切です。
一方で、話したいのに話し方が分からない場合には、具体的な質問を使って会話を引き出していきましょう。
小学校に上がると、子どもは物理的にも心理的にもママから離れていきます。この時期に、話をする・しないに関わらず、いつでも自分を受け入れてくれる環境があることは、子どもの健やかな成長にとってとても重要です。
また、今築いた親子の信頼関係は、思春期で会話が減ったにとき強い味方となり、支えとなってくれるはずです!
一人一人じっくり学べる!IT×ものづくり教室「LITALICOワンダー」[PR]
LITALICOワンダーは「好き」を「力」に変えるプログラミング教室です。
お子さんの個性、強み、興味といった「好き」をもとにオーダーメイドのカリキュラムを受講することができます。
その内容はゲームプログラミング、ロボット、デジタルファブリケーションなど様々。
さらに、「LITALICOワンダー」の運営元・株式会社LITALICOは、発達障害・ADHD・学習障害のお子さまへの学習支援・教育支援を行う「LITALICOジュニア」を運営しています。
・学習やコミュニケーションに不安がある…
・集中して授業を受けられるか心配…
・大人数が苦手で集団の習い事を嫌がる…
そんなお悩みをお持ちのお子さまでも、安心して通塾できるのもポイントです。
只今無料体験実施中!
お問い合わせはこちらから>>リタリコワンダー
おすすめの関連記事はこちら
・【新一年生】家庭で子どもの語彙力を楽しく高めるポイントをご紹介!~小学校入学準備をしよう~
・自分の話ばかり!人の話を聞けない子への関わり方・教えたい「会話力」






