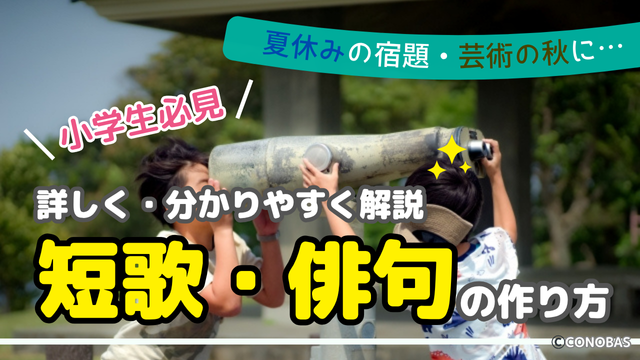
小学生の短歌・俳句の作り方|夏休みの宿題対策&親子で楽しむ実践例つき
この記事を書いた人
米澤駿
- 公認心理師
- 臨床心理士
公認心理師・臨床心理士として、子どもやご家族のこころや発達の支援に約10年間携わってきました。
学童や放課後等デイサービスの指導員、乳幼児健診の発達相談員、スクールカウンセラーなど幅広い現場で、発達段階に応じた対応や保護者支援を経験しています。
自分自身も一児の父として、毎日の子育てに奮闘中。
心理学の専門知識と現場経験、そして親の目線も大切にしながら、皆さまのお役に立てる情報を分かりやすく丁寧な言葉でお伝えできるよう心がけています。
「夏休みの宿題に短歌や俳句があるけど、どう教えたらいいの?」
「そもそも短歌と俳句の違いって何?」「どうすれば子どもが楽しく取り組めるの?」
――そんなお悩みをお持ちではありませんか?
この記事では、小学校低学年のお子さんを持つ保護者の方に向けて、短歌・俳句の基本から書き方のコツ、親子で楽しく取り組むための実践方法まで、分かりやすく解説します。
学生時代以来触れていない方でも安心◎ 短歌・俳句を通じてお子さんの想像力や表現力を育みながら、夏休みの宿題をスムーズに終わらせるためのヒントがたくさん詰まっています。
忙しい共働き家庭でも実践できる時短テクニックや、すぐに使える作例集も用意しました。親子の素敵な夏の思い出づくりにもぜひお役立てください!
目次
1.短歌・俳句ってどんなもの?

日本の伝統的な詩の形式である短歌と俳句。
お子さんの夏休みの宿題として出されることも多いですが、保護者の方自身も「正確な違いは何だっけ?」と思われるかもしれません。まずは基本からおさらいしていきましょう。
1-1.短歌と俳句の違いと特徴
短歌と俳句は、どちらも「感じたことや出来事を言葉で表現する日本の詩」という点で共通していますが。大きな違いは、その「長さ」と「決まり」です。
「短歌」
5・7・5・7・7(合計31音)で構成されます。少し長めなので、気持ちや情景をじっくり表現できます。
【作例】「かき氷 いちごシロップ たっぷりと 口の周りが 真っ赤になった」(5・7・5・7・7の31音)
「俳句」
5・7・5(合計17音)というシンプルさが魅力。季語(季節を表す言葉)が入るのがルールです。
【作例】「かき氷 青いシロップ くちあおい」(5・7・5の17音、「かき氷」が夏の季語)
1-2.小学生の宿題で取り上げる理由
なぜ短歌や俳句が小学生の宿題によく出るのでしょうか?それには重要な教育的意義があります。
- 観察力の向上
何かを詠むためには、まず観察することが大切です。周りの世界をよく見る習慣が身につきます。 - 感性・表現力の育成
感じたことを言葉に変換する力が養われます。 - 短い文章で表現する力
限られた字数で自分の思いを伝える練習になります。
1-3.親子で挑戦するメリット
短歌や俳句づくりは、親子で一緒に取り組むことでさらに価値が高まります
- コミュニケーションの活性化
「どんな言葉が良いかな?」「これは何て表現する?」と相談しながら作ることで、自然と会話が増えます。 - 新たな発見の共有
お子さんの意外な感性や観察眼に気づくきっかけになります。 - 達成感の共有
完成した作品を一緒に読み合うことで、共に喜びを感じられます。
2.短歌・俳句の書き方と基本ルール

短歌・俳句には「音数」や「季語」などの基本的なルールがありますが、小学校低学年では楽しみながら書くことが大切です。
次のポイントを押さえて、親子で短歌・俳句を楽しんでみましょう。
2-1.短歌と俳句、それぞれの構造と決まり
「短歌」
・音数:「5・7・5・7・7」
・決まり:季語が必須ではない(季語は入れても入れなくてもOK)
・作例:かき氷 いちごシロップ たっぷりと 口の周りが 真っ赤になった
「俳句」
・音数:「5・7・5」
・決まり:季語が必須
・作例:かき氷 青いシロップ くちあおい(季語「かき氷」)
2-2. 初めてでも分かりやすい書き方ステップ
①テーマを決める
夏らしいテーマや、印象に残った出来事を選びましょう(例:夏休み、海、セミ、アイス、お祭り、花火など)。
②伝えたいことや気持ちを自由に話す
お子さんから言葉を引き出すために、「何が楽しかった?」「どんな気持ちだった?」など質問をしながら、まずは自由に会話を楽しみましょう。この段階では正しい言葉遣いや表現にこだわらず、素直な感情を大切にします。
③キーワードをメモする
会話の中で出てきた印象的な言葉や表現をメモしておきましょう。お子さんの言葉をそのまま書き留めることで、オリジナリティのある作品につながります。
④音数に当てはめる
メモした言葉を使って、短歌なら5・7・5・7・7、俳句なら5・7・5のリズムに当てはめていきます。細かい調整はあとからでOKです。
⑤声に出して読んでみる
完成したら、親子で声に出して読んでみましょう。リズムが気持ちよく感じられるか、言いたいことが表現できているかを確認します。
2-3.よくある疑問とつまずきポイント
Q:テーマが思い浮かばない・何を書いたらいいのか分からない
A:「今日したこと」「夏休みに楽しかったこと」など、身近な出来事から始めましょう。「どんな場面が一番楽しかった?」「何にびっくりした?」と気持ちを聞き出すのも効果的です。
Q:音数の数え方が分からない
A:最初は指で数えながら、1音ずつ一緒に声に出して読んでみましょう。「あいうえお」を「あ・い・う・え・お」と区切って数えると分かりやすいです。「きょう」「しゃ」などの拗音(ようおん)は1音としてカウントすることも教えておきましょう。
Q:音数が合わない
A: 助詞(「の」「は」「を」など)を入れたり省いたり、言い方を少し変えたりしてみましょう。似ている意味の他の言葉に置きかえたり、余分な表現を省いたりして調整できます。
3.テーマやアイデアはどう見つける?

短歌や俳句を作る際、最初の難関は「何について書くか」というテーマ選びです。
特に小学生は「何を書いていいか分からない」と悩むことが多いもの。ここでは、親子で楽しみながらテーマやアイデアを見つける方法をご紹介します。
3-1.夏休みにおすすめの題材・テーマ例
■ 自然・ 生き物系
- 海や山、川での体験
- アサガオやヒマワリなどの夏の花
- セミやトンボ、カブトムシなどの昆虫
■ おでかけ・イベント系
- プールや水遊び
- 花火大会
- お祭り
■ 日常生活系
- 夏の食べ物(スイカ、冷やし中華など)
- かき氷やアイスクリーム
- 扇風機やエアコン
3-2.子どもの自由な発想を引き出す質問
■ 感覚を刺激する質問
「そのとき、どんな音が聞こえた?」
「どんな匂いがした?」
「触ってみてどんな感じだった?」
■ 感情を引き出す質問
「どんなことが楽しかった?」
「一番びっくりしたのはどんなとき?」
「ちょっと怖かったことはある?」
3-3.常の出来事を作品にするヒント
■ 五感を意識する
- 見る:窓から見える景色、道ばたの花、雲の形
- 聞く:雨の音、風鈴、セミの鳴き声
- 触る:風の感触、水の冷たさ、砂や土の感触
- 嗅ぐ:料理の匂い、花の香り、雨上がりの匂い
- 味わう:夏の果物、冷たい食べ物や飲み物
■ 日常の小さな発見を大切に
- 買い物や散歩での出来事
- 家族との何気ない会話
- ベランダの植物の成長
【実践例(日常→短歌・俳句の変換)】
日常の出来事:「朝、窓を開けたらセミが鳴いていた」
→短歌への変換:夏の朝 窓を開ければ セミの声 夏本番と 教えてくれる
→俳句への変換:窓を開け セミの鳴く声 夏の朝
4.効率よく短歌・俳句の宿題を終わらせるコツ
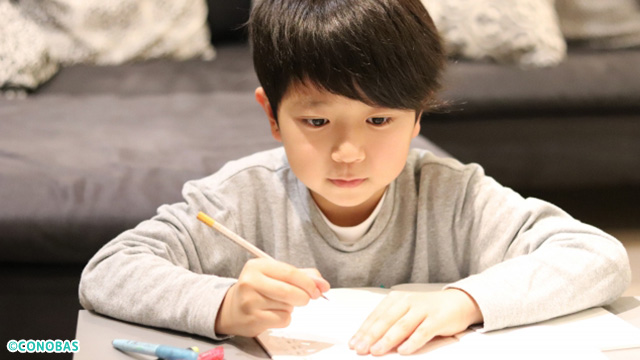
夏休みは楽しい予定がいっぱい。短歌・俳句の宿題を効率よく、ストレスなく終わらせるコツをご紹介します。
忙しい共働き家庭でも無理なく取り組める方法を中心にまとめました。
4-1.時短でできる家庭での進め方
まとまった時間をとるのが難しくても、ちょっとした工夫で短歌・俳句の宿題は進められます。忙しい日々でも気軽に続けられる方法をまとめました。
- 朝の時間を活用する
朝の方が子どもの頭が冴えていて、アイデアも浮かびやすいものです。朝食前や後の10分間を使って、昨日の体験を短歌や俳句にしてみましょう。毎日少しずつ取り組めば、自然と作品が出来上がります。
- 「ながら作業」で効率アップ
車での移動中、または入浴中など、日々の何気ない時間を利用して、「今日はどんなことがあった?」「面白かったことは?」と親子で会話しながら題材やフレーズを考えてみましょう。移動や家事のついでに進められるので負担も少なくなります。
4-2.便利なサポートツール活用法
デジタルツールを上手に活用すれば、短歌・俳句づくりがもっと身近で楽しいものになります。
季語を探したり音数を数えたりといった手間を省き、創作に集中できるウェブサイトをご紹介します。必要に応じてぜひ活用してみてください。
- 『俳句季語辞典』
夏の季語を簡単に検索できる便利なウェブサイトです。季語選びに迷った時に役立ちます。
- 『Google-AI Gemini』
AIを使用すれば手軽に、たくさんのアイデアを発掘できます。また、音数が合っているかの確認にも最適です。
感想も挙げてくれるため、創作意欲が掻き立てられそうです◎
AIへの質問例:
「私は、小学校二年生です。夏をテーマにした短歌づくりのための季語を10個出してください。」
「短歌をつくりました。音数があっているか数えてください。『かき氷 いちごシロップ たっぷりと 口の周りが 真っ赤になった』」
4-3.うまくできないときのフォローの仕方
「何を書けばいいのかわからない」「言葉が出てこない」と悩むお子さんは少なくありません。
創作の途中で行き詰まることは、誰にでもあります。そんなときは、お子さん自身の感じ方やアイデアを大切にし、自信をもって表現できるようサポートしましょう。
短歌や俳句には決まった“正解”はありません。迷ったりつまずいたりすることも、創作の大切な過程です。
一緒に楽しむ気持ちで、お子さんの自由な発想を認め、「この表現、おもしろいね!」など、前向きな声かけを意識してみましょう。
【声かけの例】
「普通とはちがう言い方が新鮮だね」
「それは大人には思いつかない表現だね」
「そんな考え方ができるなんて、すごいね」
5.そのまま使える!参考になる短歌・俳句の作例集

お子さんの創作意欲を刺激する参考作品と、それぞれの作品から学べるポイントをご紹介します。
これらの例を見せながら「こんな風に書くんだよ」と具体的に示すことで、お子さんも取り組みやすくなるでしょう。
5-1.小学校低学年向けの実例紹介
【短歌の作例】
・せみのこえ ぼくがおきたら ひびいてる ねむいおふとん ぬけだしていく
・かきごおり あかあおみどり いろいろね とけるまえには たべおわりたい
・うみべでは おおきなかにを つかまえた てのひらのうえ あるいていった
【俳句の作例】
・あついひは つめたいプール うれしいな
・あさがおに みずをあげたよ おはようと
・せみのこえ きこえはじめた なつやすみ
5-2.作例から学ぶポイントとアレンジ方法
先ほどの作例を参考に、お子さんの作品をさらに魅力的にするコツをご紹介します。これらのポイントを意識するだけで、同じテーマでも表現に深みが出て、より印象に残る作品になります。
- 「自分の体験」をテーマにする
「わたし」「ぼく」を主語に入れることで、共感や表現がしやすくなります。
- 五感を使った言葉を取り入れる
「聞こえた」「匂い」「味」などを表現すると、作品がグッと生き生きしてきます。
- 気持ちを一言加える
「うれしい」「わくわく」「びっくり」など素直な感情を添えてみてください。
5-3.宿題で気をつけたいチェックポイント
短歌や俳句が完成したら、宿題として提出する前に次のポイントを親子でチェックしましょう。
✓ 音数(5・7・5、または5・7・5・7・7)が合っているか
✓ 俳句には季語が必ず入っているか
✓ 自分自身や身近な体験が盛り込まれているか
6.短歌・俳句の奥は深いが難しくはない!楽しんで作ってみよう

この記事では、小学校低学年のお子さんと保護者の方に向けて、短歌・俳句の基本知識から実践的な作り方、夏休みの宿題を効率よく終わらせるコツまでをご紹介しました。
短歌や俳句の宿題は、「難しそう」と感じるかもしれませんが、日常の出来事や夏休みの楽しい思い出・驚きを自由に言葉にする絶好のチャンスです。
また、単なる宿題としてではなく、親子のコミュニケーションや、お子さんの感性を育む素晴らしい機会でもあります。
短歌・俳句づくりをきっかけに、家族の新しい夏の思い出が増えるでしょう。自由な発想で、親子一緒に短歌・俳句づくりを楽しんでくださいね。
毎日ちょっとずつ、世界が広がる「朝日小学生新聞」受験対策にも◎[PR]
「ゲームや動画ばかりで、将来が心配…」 「もっと視野が広がってほしい」
そんなふうに感じたこと、ありませんか?
それなら、子どもの好奇心スイッチを押すきっかけに、『朝日小学生新聞』を活用してみませんか?
毎日のニュース、昆虫のふしぎ、宇宙の話、季節や自然、科学、文化など。
子どもの「なんで?」「すごい!」「やってみたい!」を引き出す新しい発見が、ぎゅっと詰まっています。
読む力はもちろん、考える力・話す力も自然とアップ。好奇心から始まる「知る楽しさ」が、子どもの未来をぐんと広げてくれます。
💡「朝日小学生新聞」の魅力ポイント
- 毎日届く1部8ページの小学生向け新聞
- 全ての漢字にふりがなが付き低学年でも自分で読める
- 時事ニュースを分かりやすく解説。中学受験対策にも最適
- 読み物や漫画など、子どもの興味を引き出すコンテンツが豊富
- 日々新聞を読むことで、自然と考える力や知識が育める
毎日の小さな学びが、未来の大きな成長につながるはずです。
親子でも子どもひとりでも楽しく読めます。
これからの未来を生き抜く力、学びの力を伸ばすために新聞をご活用してみてはいかがでしょうか。
関連トピックをご紹介!
・【小学校低学年向け】読書感想文が書きやすい本の選び方!おすすめ本もご紹介<前編>
・夏休みの工作アイデア!子どもだけで作れる!簡単・面白い作品を紹介
・夏休みにおすすめ!子どもと家でできる簡単な実験遊び3選





