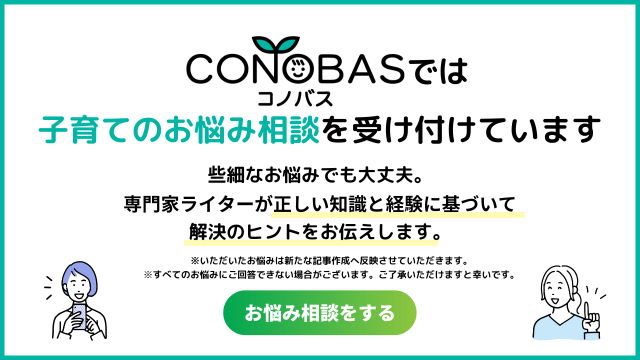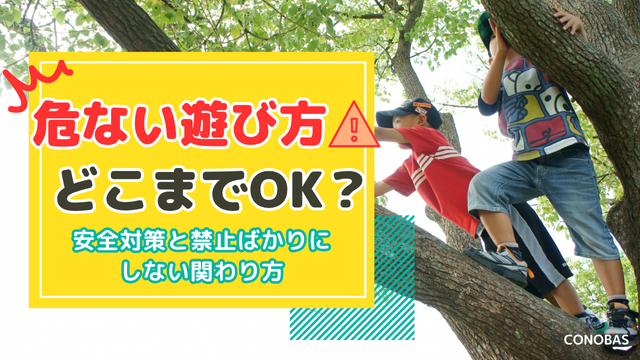
4~5歳|危ない遊び方はどこまでOK?安全対策と禁止ばかりにしない関わり方
この記事を書いた人


中川さくら
- 保育士
- 児童指導員
学生時代に障害児福祉を学び、小学校の特別支援教育支援員や療育施設の保育士、学童保育、小学校などで、子どもたちやそのご家族と関わる仕事を約10年ほど経験しました。
今は、保育園に通う1歳の息子がいます。
昔バックパッカーだったので、いつか家族で世界を旅することが夢です。
「危ないからやめなさい!」
活発な4〜5歳のお子さんの遊びを見守っていると、そんな言葉ばかり出てしまいませんか?
CONOBASにも、危ない遊び方を繰り返す4歳の男の子のママから、お悩みをお寄せいただきました。
ソファーや机から飛び降りる…
4歳男の子 ママからのご相談

「部屋のソファーや机の上に乗り、そこから飛んだりします。ダメと言ってもその時だけで毎日してます。どう言ったらよいでしょうか?」
4〜5歳頃は運動能力も伸び、遊び方がいっそう広がっていく時期ですね。しかし、危険かどうかの自己判断はまだまだ難しいものです。
「失敗や痛い経験から学ぶこともあるし…」と見守ろうと決意しても、目の前にするとやはり止めてしまう…。
大きな怪我をしてほしくない気持ちと、のびのび遊ばせてあげたい気持ちの狭間で葛藤しているママやパパは、きっとたくさんいるでしょう。

ソファーから飛び降りる、高いところに登りたがる、戦いごっこがエスカレートする…
このような危ない遊び方をするのはなぜなのか、安全を守りながらのびのび遊ばせてあげるにはどうしたら良いのか、一緒に考えていきましょう。
目次
1.4〜5歳の子が危ない遊び方をする理由

子どもたちが楽しそうに遊んでいるときに、「あ、危ない!」とヒヤヒヤした経験は、おそらく多くの人がしているのはないでしょうか。
お子さんが危ない遊び方をするのはなぜなのか、4〜5歳頃の発達段階から考えてみましょう。
1-1. 褒められたい、注目されたい
「褒められたい」という欲求から、危ない遊び方を繰り返すことがあります。
高いところに登ったときや、そこから飛び降りたときに、大人やお友だちから「すごいね!」「そんなに高いところまで登れたの?」と褒められた経験があると、「すごいことなんだ!褒めてもらえるんだ!」と誤って学習してしまい、その行動を繰り返してしまうのです。
または、「注目されたい」という気持ちが背景にある場合もあります。
これは「褒められたい」ケースとは違い、「良くないこと」とわかっていて、周囲の大人の反応を見ようとする「試し行動」とも呼ばれます。
試し行動は、子どもの発達過程に現れる姿でもあり、妹・弟が生まれた、幼稚園に通い始めた、などの不安やストレスが原因になっていることもあります。
好ましくない行動をとって周囲が反応することで、「自分に注目してくれている」と感じたり「どこまで許されるか」を試したりしています。
「褒められたい」ことと「悪いことをして注目されたい」ことは、一見真逆のように見えますが、子どもの心の根底にある「自分を見てほしい」という欲求は共通しています。
1-2.運動能力が発達する時期
幼児体育の専門家で、日本福祉大学教授の山本秀人さんは「子どもが何かをやりたがる時期は、その運動ができるようになっていく時期。何らかの運動能力が伸びる時期にそれをやりたがる」と述べています。
つまり、登ったり飛び降りたりする行動は、その力を獲得するのに適した発達時期であり、その行動を繰り返すことで習得しようとしている、というわけです。
運動能力は、特に4~5歳児にかけて一段と大きく発達すると考えられています。
もちろん、登っていい場所や怪我をしない高さなどの判断は大切で、「どこでも登っていい・飛び降りていい」わけではありません。安全管理をした上で、この時期に繰り返し練習する(遊ぶ)ことで、発達段階に合った運動能力が発達し、それが怪我の予防にも繋がります。
1-3. 他人と比較するようになる
4歳頃から自分を客観視できるようになるため、お友だちと比べて「自分はできる、できない」と気がつくようになったり、「○○くんの方が上手、下手」と比較したりすることがあります。
しかし、人と自分との比較ができても「○○くんにはできるけど、今の自分の力ではできないだろう」という判断はまだまだ難しい時期です。
そのため「自分もうまくできるようになりたい」という気持ちから、少々危ない遊び方でも、周囲の真似をしてやってしまうことがあります。
1-4. 感覚の鈍感さがある
お子さんの中には、感覚が人一倍鈍感な子がいます。特に、ASDなど発達障がいをもつお子さんの中に、感覚が極端に鈍感、または敏感な子が多いと言われています。
多くの人は意識しなくとも、自分の体の状態を自分自身で感じているため、「感覚が鈍感、感覚を感じにくい」というのは想像しにくいことかもしれません。
重力を感じてそれに対して垂直に立つことや、自分の体の位置や傾きがわかることは、日常的に意識していない感覚だからです。
しかしそれが生まれつき感じにくい人は、「自分の体」を感じたいという欲求が背景にあり、「高いところから飛び降りる刺激」によって体重の何倍もの衝撃を感じたり、飛び跳ねることで重力を感じようとしたりします。
たとえば、感覚の鈍感さがあるお子さんは、以下のような動作をすることで、感覚を整えたり自分の気持ちを整理、表現したりすることがあります。
・ぴょんぴょん跳ねる
・ぐるぐる回る
・高いところから飛び降りる
・椅子に座っている時にガタガタ揺らす、足をブラブラする
・回転する物をずっと見つめている
このような「高いところから飛び降りる」などの動作を、場所やタイミングに関係なくやってしまうため、「危険な遊び方」と周囲から見られてしまうことがあるのです。
2.危ない遊び方を「全部禁止」にしない方法

危ない遊び方をするには様々な理由がある、とわかっても、大切なお子さんに大きな怪我はしてほしくないものです。しかし「危険だからすべて禁止」にすることも、お子さんの心身の発達を考えると正しいのかどうか、頭を悩ませてしまうことと思います。
お子さんの安全を守りつつ、遊びの欲求や成長意欲も満たせるような関わり方のポイントをご紹介します。
2-1.「危ないことをしたら褒められる・注目される」のではないと教える
「危険なことをすると褒められる」と間違って学習している場合は、そうではないことをはっきりと伝えましょう。
友だちの中には、危ないことをして『すごい』と言う人がいるかもしれない。
でも本当にかっこいいことは、『危ないことを断る勇気があること』や、『安全で楽しい遊び方を考えられること』
など、お子さんが理解しやすい言葉で話してみてください。
また、「悪いことをして注目されたい」という試し行動ならば「赤ちゃんが産まれてから、一緒に遊べなくて寂しいよね」「新しい幼稚園で頑張っているね」など、お子さんの気持ちを受け止める関わりがおすすめです。「悪いことで気を引かなくても自分を見てくれる」と感じられたら、徐々に試し行動は減っていくことが多いです。
今回の相談者様のお子さんのように「ソファーや机から飛び降りるのをダメと言ってもやめない」という場合も、「注目されたい」気持ちからの行動ではないか、一度意識してみてください。
危ない遊び方には大きなリアクションはせず、冷静に叱るのもポイントです。無視すると「もっと悪いことを」とエスカレートしたり、「悪い子ね」などと言うと不安がさらに大きくなったり、逆効果なことがあります。
ダメと言っているのに「わざとやっている」と感じると、イライラしてしまうこともありますよね。そんなときは「注目してほしい気持ちの裏返し」と発想の転換をして、「子どもが安心できる関わりをする方が解決する近道になる」と考えてみてください。
2-2.安全に遊べる服装をお子さんと一緒に用意する
大きな事故や怪我を防ぐためには、安全な服装などの用意を整えておくことも重要です。
・遊具に引っかかる可能性があるため、フードやひもの着いた服、ヒラヒラした服は極力避ける
・水筒やバッグは外してから遊ぶ
・マフラーや手袋は外してから遊ぶ
・走りやすいようサイズの合った靴を履く
上記は一例ですが、体を動かして遊ぶ際には、動きが妨げられない格好をすることが、怪我を未然に防ぐことにつながります。
小学校に入ると、親の目が届かない場所で遊ぶ機会も増えるため、4〜5歳のうちに「安全に遊べる格好」を一緒に練習しておくと、今後の安全対策にもなりますね。
2-3.子どもと一緒に遊びのルールを作る
危険な遊び方とはどんなことなのか、そしてなぜ危険なのか、ぜひお子さんと一緒に考えてみましょう。
たとえば、公園や施設などの遊び方では、以下のようなルールを考えることができます。
・ブランコ・・・こいでいる途中で飛び降りない、近くに人がいないか確認してこぐ
・すべり台・・・立ったまま駆け降りない
・柵や遊具の上など、登ってはいけないところに登らない
そのほかの遊びでは、以下のようなルールも考えられます。
・戦いごっこ・・・棒など尖ったものは使わない
・高いところからジャンプ・・・着地のときに目などに刺さると大事故になるため、手に物を持って飛ばない。着地場所に危ない物がないか確認する。
4〜5歳の子だけで考えるのはまだ難しいときもあるでしょう。そのときには大人の助言が必要ですが、お子さんから出た意見をベースにルールを作ると、「自分で決めたから守らなくちゃ」という責任感にもつながります。
危険性のある遊びを「危ないから全部禁止」にすれば、子どもの安全を守ることはできます。
しかし、戦いごっこで全力で遊ぶ中で、場面に適した力加減を学んだり、ブランコや遊具で運動能力やバランス感覚を育てたりしています。時にはケンカをしながら協調性を学んで、子どもは遊びを通して心身ともに成長します。

子どもの遊びたい欲求と、安全対策とのバランスをとることを目指せると良いですね。
3.感覚の鈍感さがある子への対応

次に、感覚の鈍感さがあるお子さんへの関わり方や、そのようなお子さんにおすすめの遊び方をご紹介します。
楽しく遊ぶことを通して、ご家庭でできることからお子さんの発達を支えていきましょう。気長に着実に育むことを目指して、すぐに成果が感じられなくてもあまり心配しないでくださいね。
3-1. 本人にとって必要な感覚だと理解する
高いところから飛び降りたり、グルグル回ったりしている行動の背景には、そうしたい理由やお子さんが抱える困り感が潜んでいる、ということを1-4で解説しました。
だからと言っても、お店の中でも飛び跳ねるなど場所を問わず動き回っていると、周囲の視線が気になってしまう場面もありますよね。
個人差はありますが、年齢や経験を重ねていく中で、その行動が目立ちにくい動作(ペンを回すなど)や、言葉、ジェスチャーに置き換わったり頻度が減ったりしていく可能性もあります。
もちろん、危険な場合は安全な動作へ代えていく必要がありますが、お子さんの体が必要としていることだと受け止めてあげましょう。
感覚の感じ方はひとりひとり違い、自分以外の人がそれを感じることはできません。「この子はどんな風に感覚を感じているのかな」「どんな工夫があれば心地よく過ごせるかな」と考えると、少し前向きに見守ることができるかもしれませんね。
3-2. 思い切り動いて良い環境を整える
強い感覚を取り入れようとしたお子さんが、高い所から飛び降りたり、激しく飛び跳ねたりすると、大きな怪我をしてしまう危険性があります。そのときは、思う存分に動いても怪我をしないような環境作りや、代わりになる安全な遊び方を提案するようにしましょう。
以下は一例ですが、危険な可能性のある物を取り除くことで、安心して見守ることができます。
・飛び降りる着地場所に布団やマットを敷く
・尖っているオモチャや箱などは片付けて、ゴロゴロ転がっても平気なスペースを作る
・高いところから飛ぶのではなく、室内に置けるコンパクトなトランポリンを用意する
また、これらの安全対策は感覚の鈍感さがある子以外にも、遊び盛りのお子さんがいるご家庭におすすめです。今回の相談者様のお子さんように「ソファーや机から飛び降りる」場合には、まずは上記のような安全な環境作り、そしてトランポリンなど代わりになる遊びの提案、そして2-3でご紹介した遊びのルール作りを取り入れてみてください。
3-3. 感覚の鈍感さがある子へおすすめの遊び
発達障がいのあるお子さんをサポートする専門施設では、ブランコやすべり台などの遊具を使って、その子が必要としている感覚刺激を満たすアプローチを取り入れており、それを「感覚統合療法」と呼んでいます
一見関係ないように見える遊びでも、遊びの中で体の様々な感覚を刺激することで、相互作用となって生きやすさにつながっていきます。
①外遊び
・ブランコ、回転遊具、すべり台などの遊具
・アスレチック
②おうち遊び
・でんぐり返し
・トランポリン
・バランスボール
・シーツに子どもを乗せて大人が引っ張ったり止まったりを繰り返す
・大人があおむけに寝転がり、すねの上に子どもを乗せる「ひこうき」
・雑巾やモップなど体を使うおそうじ
ご家庭は専門施設ではないので、日常の遊びの中で、少しでも意識して取り入れられたら十分です。
発達支援センターや療育施設など、このような感覚統合療法を取り入れてお子さんの発達をサポートする専門機関もあるので、ご家庭だけで悩まずに相談することも検討してみてくださいね。
4.自分の身を守る遊び方を練習していこう

4〜5歳頃のお子さんが危険な遊び方をする理由と、怪我や事故を防ぎながらもすべてを禁止にしない関わり方について、ご紹介しました。
危ない理由やルールを守る必要性が徐々に理解できてくる発達段階の子どもたちなので、安全に配慮しながら、できる限りのびのびと遊びを見守ってあげたいものですね。
お子さんがいつか大人の目の届かないところで遊ぶようになったときに、危険な遊び方をして大怪我をしないよう、今まだ目の届くうちにお子さん自身が「安全」と「危険」の線を引けるようにたくさん練習をしておけたら良いですね。
偏食・野菜嫌いさんにもおすすめ!無添加・手作り冷凍幼児食「mogumo(モグモ)」
[PR]
当たり前のように思われがちですが、毎日食事を作るのは、とても大変ですよね。
「今日はゆっくりしたい」
「手を抜きたくないけれど、時間がない」
「市販の総菜や幼児食を取り入れるのは抵抗がある」
「家事や育児でぐったり…」
「何を作ればいいだろう?料理は苦手だなぁ」
悩みはそれぞれですが、毎日の食事作りのお供に、冷凍宅配幼児食「mogumo(モグモ)」を活用してみるのもおすすめです。
モグモの幼児食は、全て手作りの無添加。管理栄養士が監修しているため、栄養バランスはもちろん、美味しさにもこだわっています。
mogumo(モグモ)の特徴
✓冷凍だから、レンジで温めるだけで簡単に食べられる
✓かわいいパッケージで、子どもの興味もそそられる
✓何食、どれくらいの期間利用するかは、家庭に合わせて自由に選べる
✓予定に合わせて、お届けスキップやプラン変更が可能
独自の冷凍技術で、長期間保存ができるので、冷蔵庫にストックがあるだけで安心です。
幼児食ってどうすればいいの?とお悩みの方には、管理栄養士の無料相談サポートもあります。
利用できるサービスは、上手に活用しながら、無理せず親子で楽しい時間が過ごせると良いですね。
詳細はこちらから>>冷凍宅配幼児食「mogumo(モグモ)」
・注目されたい子どもの心理とは?度がすぎる場合の原因と対応方法を解説!
・わがまますぎる!言うことを聞かない!5歳児「反抗期」への対応のコツ
参考文献
・知っておきたい乳幼児期の運動・認識・ことばの発達/日本福祉大学